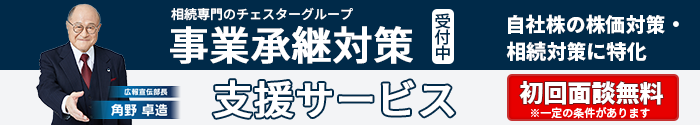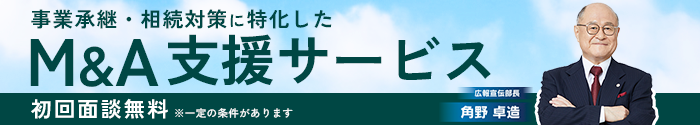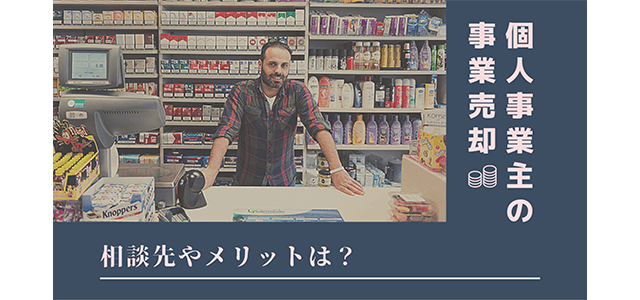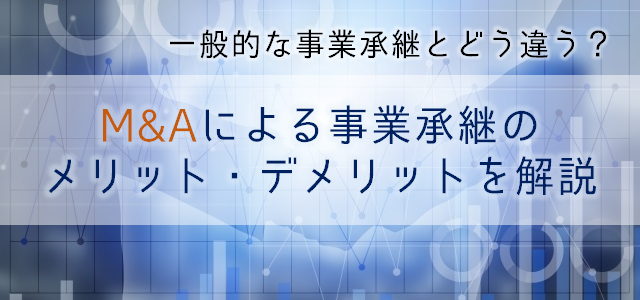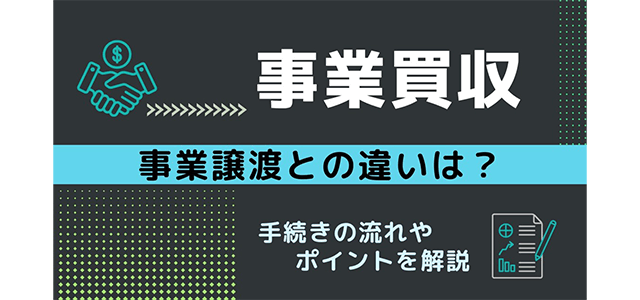個人M&Aは増加中。第三者承継の売却先が個人の場合の具体的な方法・成功のポイントを解説
タグ: #M&A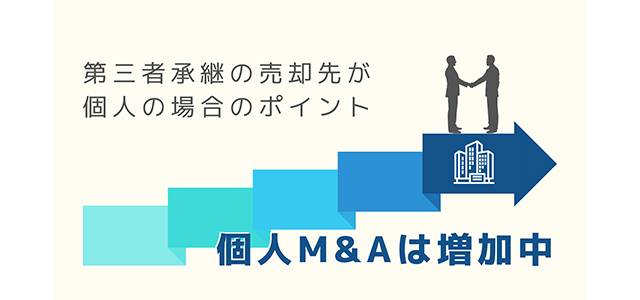
個人M&Aには、どのような特徴があるのでしょうか?売り手と買い手双方のメリット・デメリットを確認しましょう。個人M&Aの件数は増えており、会社売却の買い手が個人の可能性もあります。スムーズにM&Aを行うためのポイントも確認しましょう。
目次 [閉じる]
1.個人M&Aとは何か?

事業承継の手段としてM&Aを実施する際に、個人M&Aが行われるケースがあります。個人M&Aには具体的に、どのような特徴があるのでしょうか?
1-1.個人が買い手のM&Aのこと
個人M&Aは、個人が買い手となるM&Aをいいます。M&Aというと、かつては大企業同士が行うものでした。しかし近年では、中小企業や個人事業主によるM&Aも行われています。
取引規模の小さなM&Aは『スモールM&A』や『マイクロM&A』と呼ばれ、以下のような目的で実施されるケースが多いようです。
- 後継者不在の事業の承継
- 会社員の副業・兼業
- 独立
一般的なM&Aと同じように、各種支援機関やマッチングサイトなどを介して取引相手を探し、価格交渉などを進めます。
参考:スモールM&Aとは何か?手法や進め方、メリットと注意点を解説
1-2.個人M&Aの金額の相場
企業と比較すると、個人の資金力には限界があります。一般的なM&Aの取引規模は、数千万~数百億円に上りますが、個人M&Aは数百万~1,000万円といった手頃な価格帯が中心です。
ECサイトやテイクアウト専門店、レンタルスペースなどは、取引規模が比較的小さく、100万円以下でM&Aが成立するケースも珍しくありまん。
そもそも、M&Aの取引価格に決まった相場はなく、売り手と買い手の交渉によって決まります。売り手の事業に将来性や魅力があれば価格は上がりますが、多額の負債を抱えていたり、設備が老朽化していたりすれば、取引価格は下がるのが一般的です。
1-3.個人M&Aにおいて検討されやすい業種
買い手が個人の場合、買収にかかるコストやその後の運営のしやすさなどを考慮し、以下のような業種が選ばれやすい傾向があります。
- 飲食店
- エステサロン
- 塾
- Webサービス
- 介護事業
中でも飲食店・サロン・塾は案件数が多く、300万円前後で買収できる案件が多くあり、個人の買い手がつきやすいでしょう。
2.個人M&Aが増えている理由

小規模な個人M&Aが増えているのは、売り手にも買い手にも理由があります。どのような理由で件数が増えているのか確認しましょう。
2-1.中小企業のM&Aが増えている
まず挙げられるのは、中小企業のM&A件数が増えている点です。M&Aは、中小企業の後継者不在を解決する手段として用いられています。行政でも、中小企業のM&Aをサポートするさまざまな施策を実施中です。
例えば『事業承継・引継ぎ支援センター』による総合的なサポートや、『事業承継引継ぎ補助金』による資金面のサポート、『事業承継税制』による税負担の軽減などが行われています。
中小企業のM&Aは引き継ぐ資産が比較的少なく、株価も低い傾向があるため、個人でも買収しやすい案件が増加中です。
参考:「中小M&A推進計画」の主な取組状況 〜補足資料〜|経済産業省
参考:個人M&Aは増加中。第三者承継の売却先が個人の場合のポイント
2-2.副業や兼業への注目も後押しの一つ
個人M&Aの増加は、近年の特徴である副業・兼業の広まりにも関連しています。2018年、厚生労働省は『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を策定し、会社員の副業・兼業のルールを明確化しました。ガイドラインを策定した背景には、職業選択の自由やキャリア形成を促す狙いがあります。
すべての会社が副業・兼業を認めたわけではありませんが、会社員として働くかたわら、店舗やサイトのオーナーとして活動する個人が増えています。ビジネスモデルがすでに確立しており、かつ優秀なスタッフがいる事業であれば、本業をしながらの両立は十分に可能といえます。
終身雇用制度が崩壊しつつある昨今では、会社員でも定年まで安定して働き続けられる保証はありません。給与以外の収入源があれば、将来への安心感が増すでしょう。
3.個人M&Aと起業の違い
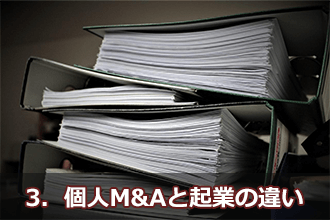
個人が経営者を目指す方法としては、M&Aと起業の2パターンがあります。どちらがよいと一概には決められませんが、事業が軌道に乗るまでにかかる時間を短縮したいのであれば、M&Aが有利です。M&Aと起業の違いを確認しましょう。
3-1.事業のベースがすでにあるのが大きな特徴
M&Aと起業の違いは、事業のベースがあるかどうかという点です。M&Aは、投資回収までの時間を節約できることから、『時間をお金で買う行為』とよく例えられます。
ゼロから起業する場合、ビジネスのアイデアを見つけるところからスタートします。例えば店舗経営では、事業計画書の策定・場所決め・内装・メニューの開発・顧客開拓と、多くの準備をしなければなりません。
さらには、軌道に乗せ利益を出すまでに時間がかかる上、必ずしも成功するとは限らないのが現実です。
他方、M&Aはすでに完成しているビジネスモデルを買収する行為です。黒字の会社や店舗であれば、買収直後から収益が期待できるでしょう。技術やノウハウ、スタッフなどをそのまま引き継げるため、買い手はマネジメントに集中できます。
4.個人M&Aでの売り手側のメリット

親族内にも社内にも後継者がおらず事業承継ができない場合、個人M&Aは解決策の一つです。売り手側が得られる具体的なメリットを紹介します。
4-1.後継者候補がいなくても事業承継できる
後継者候補がいない場合、経営者が引退すれば会社は廃業せざるを得ません。しかし従業員や取引先にかかる迷惑や、築き上げてきた技術などを考えると、できるだけ会社を存続させたいと考える経営者が多いでしょう。
そこで活用できるのが個人M&Aです。親族や社内で後継者にふさわしい人物が見つからない場合には、個人M&Aを利用すれば、後継者探しの範囲を広げられます。
うまくマッチングすれば、自社の事業に役立つ経験を持つ人材を見つけられるかもしれません。
参考:後継者不足を理由に廃業はもったいない。M&A検討で可能性は広がる
4-2.売却により対価を得られる
会社や事業の売却によって対価を得られるのも、売り手にとってのメリットです。子どもをはじめとする親族に事業承継を行っても、経営者は対価を得られません。また後継者がいないからと廃業すれば、清算にコストがかかる可能性もあります。
売却によって対価を得られれば引退後の資金や、やってみたいと考えていた他の事業の資金に使うことも可能です。
4-3.業績の改善へと向かう可能性
社外からやってきた新たな人材が経営の中心に立つことで、業績の改善も期待できます。会社の風土に染まっていない第三者だからこそ、これまでとは違った業績改善の糸口を見つけられるかもしれません。
業績が改善すれば、従業員の待遇もこれまでより改善するでしょう。またこれまで通りの取引量をキープしたり、場合によっては取引量を増やしたりもでき、取引先の業績アップにつながる可能性もあります。
M&Aのメリットについては、以下もご覧ください。
M&Aのメリットを細かく紹介。M&Aによる相乗効果や節税効果とは|税理士法人チェスター
5.個人M&Aでの売り手側の注意点
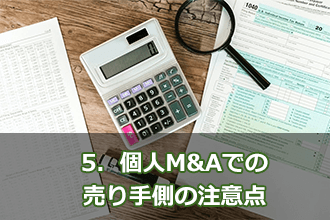
後継者がおらず事業承継が難しい場合に、個人M&Aは解決策となり得る方法です。ただし注意点もあります。タイミングや条件が合わなければ、希望していてもM&Aの手続きは進みません。
5-1.買い手がなかなか見つからない可能性
個人M&Aでは、買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性もあります。会社の雰囲気に合う買い手との出会いはタイミング次第の側面があるため、買い手を見つけるまでに数年かかるかもしれません。
また自社の財務状況や、手掛けている事業の将来性の面で、買い手に選ばれない可能性もあります。例えば債務超過や赤字が膨れ上がっている会社、また今後の縮小が見込まれる分野は、買い手が見つかりにくいでしょう。
5-2.個人保証が事業承継の妨げになる可能性
事業用の融資を受けるにあたり、経営者が個人保証を負っている場合もあります。個人保証があると、万が一事業が立ち行かず会社を廃業することになったとき、会社の債務を経営者個人がすべて返済しなければいけません。
個人M&Aの買い手候補が現れたとしても、個人保証の引き継ぎを負担に感じ、取引がそれ以上進まないケースもあるでしょう。
また買い手が個人保証の引き継ぎを承諾したとしても、債権者である金融機関が買い手の経営者としての能力や資金力を判断し、個人保証の名義変更を許可しない場合もあります。
参考:M&A時の借入金の扱いを解説。連帯保証の解除についても確認を
5-3.手続きに時間がかかる
会社や事業の売買は、単純な物品の売り買いとは異なります。ターゲットを選定したり企業価値を適切に評価すること、数回にわたる条件交渉など、実に多くのプロセスを経なければなりません。
一般的にM&Aにかかる期間は、半年~1年が目安です。引き継ぎや手続きに時間がかかることも考慮し、早めに後継者を探す必要があるでしょう。
M&Aには複数のスキームがありますが、中小企業・小規模事業者の大半は、株式譲渡または事業譲渡のスキームを選択するのが一般的です。ただし株式譲渡に比べ、事業譲渡は手続きが煩雑です。店舗の賃貸・従業員・取引先などに関しては再契約が必要なため、それなりに時間や手間がかかります。
個人事業主の場合は、引き継ぎと同時に『廃業手続き』を行わなければならない点にも留意しましょう。
参考:中小企業のM&Aに必要な準備、期間。売却価格はどのように決まる?
6.個人M&Aでの買い手側のメリット
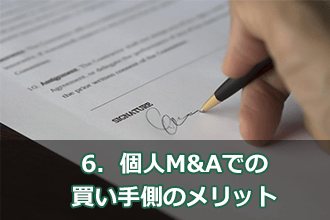
起業を考えている個人が、一から会社を立ち上げるのではなく、M&Aを実施するケースが増えています。買い手にとって個人M&Aにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
6-1.会社のあらゆる資産を引き継げる
M&Aを行うと、会社の持っている有形無形の資産を引き継ぐことができます。商品やサービスはもちろん、ノウハウや従業員も含め、これまで続いてきた事業を引き継ぐことで、軌道に乗せるための時間を大幅に節約できます。
また株式譲渡で会社を丸ごと買収すれば、会社の持つ許認可も引き継げます。個人では取得が難しい許認可が必要な事業にも参入しやすいでしょう。
すでに業界の経験があり十分な知識があるけれど、許認可の取得が難しく独立できなかったという場合に、有効な手段になり得ます。
参考:M&Aで株式譲渡が選ばれる理由は?株式譲渡契約の内容などを解説
6-2.黒字企業なら買収直後から利益を得られる
一から立ち上げた会社で利益が安定して出るようになるまでには、長い期間がかかります。一方、個人M&Aで会社を買収すると、早めに利益を得られるケースがあります。
特に買収した時点で黒字経営の会社であれば、すぐに利益を受け取れます。買収直後からある程度の利益が得られると分かっていれば、比較的安心してM&Aの契約を締結できるでしょう。
6-3.将来は不労所得や売却益を得られる可能性
個人M&Aを活用すれば、趣味や特技を生かして事業展開できるかもしれません。例えば、そば打ちが趣味で仲間内に振る舞い好評という人がそば店を買収すれば、身につけた技術をそのまま事業に使えます。
そば粉に詳しければ複数種類のそば粉を使い分け、新メニューを開発してもよいでしょう。優秀な職人がいる店なら、店の運営自体は職人やスタッフに任せられるかもしれません。
店の仕事を任せられれば、メニューやサービスのアイデア出しに専念してもよく、オーナーとして収入を得る道もあります。将来的に事業の価値を高めてから売却すれば、まとまった利益を得られるのもメリットです。
7.個人M&Aでの買い手側の注意点
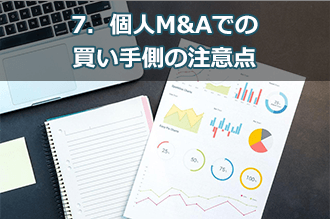
事業に必要なさまざまな資産を引き継げるM&Aは、起業の成功率を高める方法といえます。ただし個人M&Aならではの注意点もあるため、よく精査した上で買収を決めなければいけません。
7-1.引き継ぎに失敗する可能性
個人M&Aでは、設備や技術だけでなく、従業員や取引先なども引き継げます。しかし引き継ぎに失敗する可能性がある点に注意しましょう。
資産にどのようなものが含まれているかよく確認しないと、不要な資産を引き継ぐ恐れがあります。中には買い手が個人だからと、正しい情報を隠す経営者がいる点にも注意が必要です。
また中小企業にとって、経営者の交代は大きな出来事です。従業員の中には経営者に魅力を感じて働いている人もおり、そうでない場合にも「大きく体制が変わるのではないか」と不安を感じる人もいるでしょう。
十分な説明や関係性構築がなされないままでは、従業員が退職してしまうかもしれません。取引先も同様です。経営者が買い手との間を取り持たないと、M&Aを機に関係性が途切れる可能性もあるでしょう。
M&Aにおけるトラブルについては、以下もご覧ください。
買収された会社の末路。考えられる社員や買い手企業とのトラブルは?|税理士法人チェスター
7-2.簿外債務を引き継ぐ可能性
帳簿を入念に調べても出てこない『簿外債務』を引き継ぐ可能性にも、注意が必要です。後から発覚すると、大きな損害につながり、事業の継続に影響を及ぼしかねません。
簿外債務の引き継ぎを避けるには、詳細な調査であるデューデリジェンスを専門家に依頼しましょう。ただし経営者が協力的でない場合や認識の誤りにより、調査では見つからないケースもあります。
後から簿外債務が見つかっても対処できるよう、弁護士に依頼し『表明保証条項』を契約書へ盛り込むといった対策を講じておくとよいでしょう。
専門家に依頼することで、買収価格以外のコストがかかるのも注意点の一つです。
簿外債務の詳細については、以下もご覧ください。
簿外債務の種類や見つけ方。買い手と売り手それぞれの対策は?|税理士法人チェスター
7-3.利益につながるまでに時間がかかる可能性
黒字の会社を買収すれば、買収直後から収益が得られます。一方で、買収価格が安くても売上や利益が少ない会社の場合は、安定して利益が出るまでに時間がかかる可能性があります。
特に会社勤めの経験しかない人は、経営の経験やスキルが欠如しているため、大幅な業績アップを図るのは至難の業でしょう。前の経営者が築き上げた会社を赤字にし、従業員を路頭に迷わせてしまう恐れもゼロではありません。
M&Aで利益が上げられるかどうかは、その人の手腕にかかっています。未知の分野にチャレンジする際は、小さく事業を開始するのが賢明です。本業との親和性や自分の得意なことが生かせるかどうかも考慮すべきでしょう。
8.個人M&Aを検討している買い手の探し方
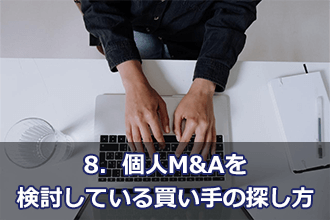
事業承継の手段として会社が個人M&Aの買い手を探すには、『M&Aマッチングサイト』や『事業承継・引継ぎ支援センター』『事業承継マッチング支援』などを利用するとよいでしょう。
個人M&Aの買い手が資金を用意しやすい、数百万~1,000万円の案件が多いサービスをチェックするのがおすすめです。
8-1.M&Aマッチングサイト
比較的小規模な案件が多く掲載されているM&Aマッチングサイトは、個人M&Aの買い手がチェックしていることの多いサービスです。売買の相手を掲載されている案件から探す仕組みになっており、費用が比較的安く設定されています。
提供されているサービスはマッチングサイトごとに異なるため、よく確認しましょう。例えば必要に応じて専門家のサポートを受けられるサイトもあれば、用意していないサイトもあります。
売り手が案件を登録すると、買い手から交渉の申し込みが入るマッチングサイトが一般的です。じかにやり取りできるため、スムーズに進めば短期間でM&Aが成立しやすい傾向があります。
M&A仲介サイトについての詳細は、以下もご覧ください。
M&A仲介サイトで小規模な事業の売買も可能。六つのサイトを紹介|税理士法人チェスター
8-2.事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継とM&A支援をワンストップで行っている、事業承継・引継ぎ支援センターに相談するのもよいでしょう。事業承継に関することであれば、どのような内容でも無料で相談できます。
後継者がおらず第三者承継を希望している場合は、買い手とのマッチング支援を利用可能です。マッチング支援は創業希望者が登録している『後継者人材バンク』や、民間のマッチングサービスを通して行われます。
8-3.事業承継マッチング支援
日本政策金融公庫が行っている事業承継マッチング支援に登録するのもおすすめです。事業を譲渡したい会社と、譲り受けたい人とを結びつけるサービスを利用できます。
譲渡したい会社も譲り受けたい買い手も、無料で利用できる点も魅力です。原則として日本政策金融公庫から事業資金の融資を受けている会社が対象ですが、商工会議所や税理士などの紹介によっても利用できます。
9.個人に会社を売却し事業承継する流れ

個人M&Aによる事業承継をスムーズに実施するには、全体の流れを押さえておくと役立ちます。小規模だから簡単に済ませられると考えず、必要に応じて専門家のサポートを依頼しましょう。
9-1.個人M&Aを検討している買い手を探す
まずは、個人M&Aを希望している買い手を探さなければいけません。M&Aマッチングサイトに登録し買い手を探す場合には、自社の情報をマッチングサイトへ記載する必要があります。
不特定多数の人が見る可能性のある情報のため、社名が特定されない範囲で自社の魅力を伝えます。掲載された情報を見て会社に興味を持った買い手から、交渉の申し込みが入る流れです。
交渉を申し込んだら、会社のより詳細な情報を開示します。万が一情報漏えいが起きた場合に備え、『秘密保持契約』を締結した上で情報を開示しましょう。
『ノンネームシート』や『ネームクリア』についての詳細は、以下もご覧ください。
ネームクリアとは?秘密保持契約、IMなどM&Aの準備を解説|税理士法人チェスター
9-2.面談を行い基本合意書を締結する
詳細な会社の情報を見た買い手が希望すると、面談へと進みます。最初の面談は条件交渉ではなく、お互いの人柄を確認する場です。
自社の雰囲気に合う人物か、経営方針は希望する方向性と合いそうかなどを確認します。買い手も同じように、売り手との相性をチェックしているでしょう。
お互いに交渉を本格的に進めたい意向であれば、ここまでの段階で合意に至った内容を盛り込んだ『基本合意書』を締結します。
基本合意書についての詳細は、以下もご覧ください。
基本合意書の意味と内容。独占交渉権の付与など重要なポイント|税理士法人チェスター
9-3.買い手がデューデリジェンスを実施する
次に行うのは、買い手によるデューデリジェンスです。財務・税務・法務など会社に関して各分野から細かく調べます。調査範囲はさまざまで、小規模なM&Aでは行われないケースもあるでしょう。
ただし調査せずに契約を締結すると、M&A成立後に思わぬ負債が見つかるかもしれません。買い手のリスクを回避するには実施すべき調査といえます。
また買い手が行うデューデリジェンスの前に、売り手側で専門家に調査を依頼しておくと、把握していなかった不備に事前に気付けます。あらかじめ対策しておけば、不備により売却価格が下がる心配がありません。
デューデリジェンスについては、以下もご覧ください。
M&Aにおけるデューデリジェンスの役割。調査項目や進め方を知る|税理士法人チェスター
9-4.最終契約を締結する
デューデリジェンスの調査結果をもとに、必要であれば交渉を行います。調査により帳簿に計上されない簿外債務があると分かれば、その分を売却価格から差し引いた金額で契約締結となるかもしれません。
交渉の結果、合意した内容も入れ込み、先に取り交わした基本合意書をベースに最終契約書を作成しましょう。内容に問題がないことを確認し、契約書を締結します。
9-5.資産の移転やノウハウの引き継ぎなどを行う
最終契約締結後は『クロージング』と呼ばれる段階です。売り手は事業に必要な資産を買い手へ移転したり、事業の継続に欠かせないノウハウの引き継ぎをしたりします。また買い手は買収金額を指定の方法で支払います。
それぞれの手続きをどのタイミングで行うかは、契約書に盛り込んでおきましょう。クロージングでは、契約書のスケジュールに従い手続きを進めます。
参考:M&Aのクロージングで行う手続きや、取引が中止になる条件を解説
10.個人への事業承継で押さえるべきポイント
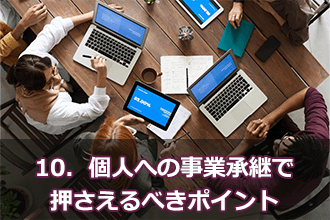
買い手が個人のM&Aは増えていますが、簡単に成立するものではありません。個人M&Aによる事業承継を成功に導くにはポイントがあります。
10-1.自社と買い手の相性を見極める
相性が合うか見極めるのは重要なポイントです。経歴や実績が申し分ない人であっても、自社の社風や従業員と反りが合わなそうな買い手では、M&A成立後の経営がうまくいかないかもしれません。
また買収後の方針が希望と合うかも確認が必要です。今後も事業を残したい、従業員の雇用や取引先との関係を守りたいという目的で個人M&Aを行うなら、希望と合致する方針の買い手を見つける必要があります。
10-2.買い手にとって魅力ある会社へ磨き上げる
スムーズに買い手を見つけ事業承継できるようにするには、会社の磨き上げが欠かせません。組織の体制を見直し整備したり、財務に関する書類をそろえ不備がないか見直したりしましょう。経営体制の強化も必要です。
磨き上げによって会社の魅力が高まれば、多くの買い手から注目されるでしょう。それは売却価格にも反映されます。
10-3.信頼できる人間関係の構築
M&Aで新たな経営者となる買い手は、人間関係の構築に力を入れる必要があります。特に従業員や取引先に対しては、買収に至った経緯や今後の方向性、待遇などを丁寧に説明しなければなりません。
従業員や取引先からの信頼を得られない場合、会社経営を続けていくのは困難です。買い手が経営体制をスムーズに構築できるように、売り手は以下のような点に関して全面的に協力しましょう。
- 従業員への説明
- 取引先・クライアントへの挨拶回り
- 懇親会の開催
- 実務の引き継ぎ
経営が安定するまでの間、売り手の経営者が会社に残留するという手もあります。長い引き継ぎ期間を設けた方が、その後の経営がスムーズに進むという点も覚えておきましょう。
10-4.専門家に相談する
M&Aの取引には幅広い分野の専門知識が必要です。小規模だから大丈夫だろうと売り手・買い手のみで進めようとすると、対応しきれない可能性もあります。
また最終契約の締結まで済んだとしても、後からトラブルが発生するかもしれません。契約締結までスムーズに進め、その後のトラブルも防ぐには、事業承継に関する実績が豊富な税理士や弁護士などへ依頼するのがおすすめです。
税理士に依頼するなら、事業承継の実績が豊富な『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。
11.個人M&Aの相談先を選ぶ際の確認点
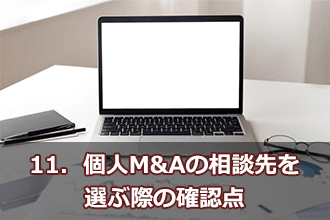
M&Aの経験がない個人や中小企業は、M&Aの仲介会社やアドバイザー、コンサルタントなどに相談をするのが一般的です。個人M&Aの相談先を選ぶにあたり、どのような点をチェックすればよいのでしょうか?
11-1.実績をチェック
まずは、支援機関のウェブサイトや広告などをチェックして、過去の実績を確認しましょう。多くのM&A案件に携わってきた優秀なアドバイザーは、幅広い専門知識とスキルを備えており、各段階で適切な助言やサポートをしてくれるのが特徴です。
ただし、名の知れた大手だからといって、担当するアドバイザーの全員が必ずしも有能とは限りません。スタッフが粒ぞろいの小さなコンサルティング会社もあるため、対面で話を聞いてみる必要があるでしょう。
やり取りの内容や質問に対する返答から、アドバイザーの真の実力が垣間見えます。答えを曖昧にせず、どんな些細な質問にも親身になって答えてくれる担当者は、信頼に値するといえるでしょう。
11-2.強み・得意とする業界をチェック
大企業のM&Aをサポートするコンサルティング会社に相談しても、自社に適した案件は見つかりにくいものです。身の丈に合った相談先を選定しないと、多額の手数料に悩まされます。
支援機関ごとに得意な業種や取引規模が異なるため、相談の予約をする前に以下の点をチェックしておきましょう。
- 取り扱いの多い業種は何か
- 希望するエリアに対応しているか
- 取引規模が自社に見合っているか
例えば飲食店のオーナーであれば、飲食業界に特化した支援機関を選ぶのが理想です。豊富な情報とネットワークを生かし、自社の希望にマッチした取引相手を紹介してくれるでしょう。譲渡価格の相場やアピールポイントについても適切なアドバイスを得られるはずです。
12.個人M&Aを検討している買い手は増加中
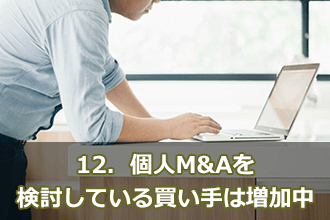
中小企業の後継者不在への対策として、M&Aによる事業承継が増えています。その結果、数百万~1,000万円で買収できる案件も数多くあり、起業する手段の一つとして選ぶ個人が増加中です。
小規模なM&Aは、当事者同士のみで進められるケースもあります。しかしトラブルを避けて確実に契約を締結するなら、専門家のサポートを受けるとよいでしょう。当事者のみでは分からない不備が判明し、事前にトラブル対策ができるかもしれません。
M&Aで必要な調査は多岐にわたりますが、税務に関しては『税理士法人チェスター』が役立つでしょう。相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継にM&Aの活用を検討しているなら、以下もぜひご覧ください。
事業承継対策としてM&Aを利用する際のメリット・デメリット|税理士法人チェスター
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。