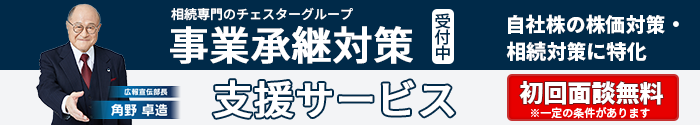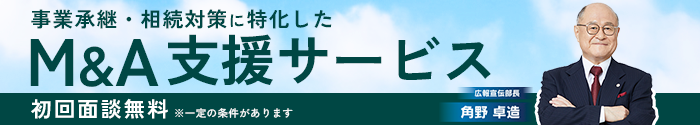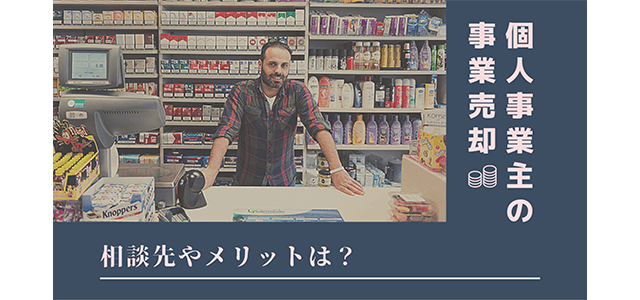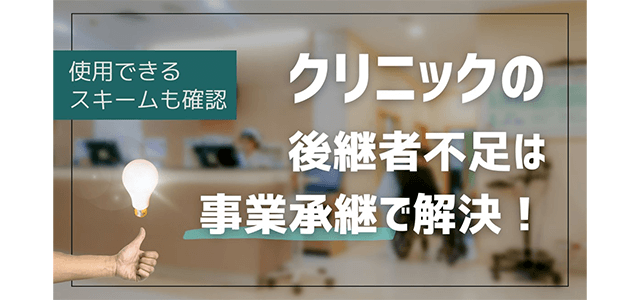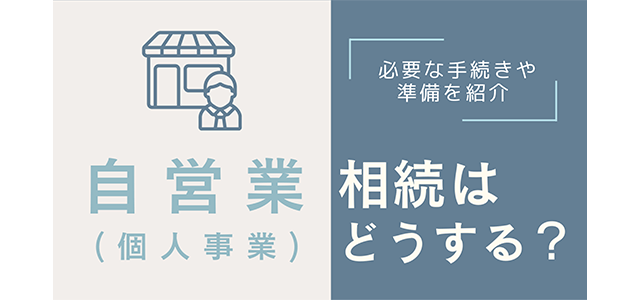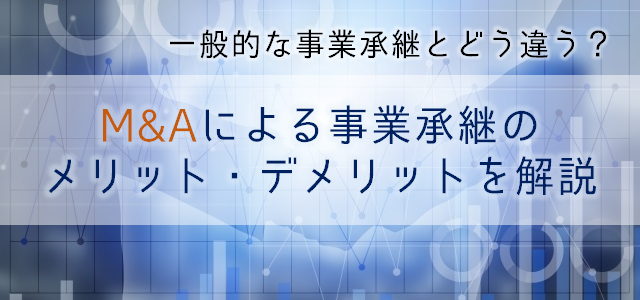個人事業主『事業承継』手続きの流れ。後継者選びや税金対策は早めに
タグ: #M&A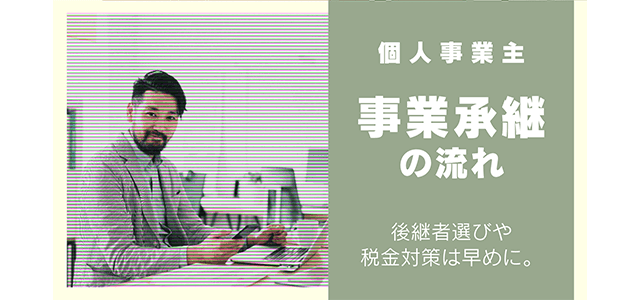
個人事業主が後継者に事業承継する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?加えて事業承継を実施するための3種類の手法や、納税義務が生じる税金についても見ていきましょう。個人版事業承継税制で税額を抑える方法も紹介します。
目次 [閉じる]
1.個人事業主の事業承継とは
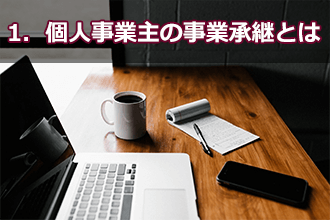
企業の事業承継では、後継者に株式を移転し手続きします。個人事業主の事業承継では、後継者に何を引き継ぐのでしょうか?
1-1.経営権・経営資源などを後継者に引き継ぐこと
個人事業主の事業承継で引き継ぐものは、『経営権』『経営資源』『物的資産』の3種類です。
- 経営権:現経営者の廃業と後継者の新規開業により引き継ぐ
- 経営資源:信用力やノウハウ・従業員・取引先などを引き継ぐ
- 物的資産:店舗・機器・備品などの事業に必要な固定資産や、売掛金・借入金などを引き継ぐ
事業承継では、事業の一部のみを引き継ぐことも可能です。しかし実際に事業承継した個人事業主の89.4%は、事業のすべてを引き継いでいます。
参考:中小企業庁「2019年版 小規模企業白書 第2節 個人事業者の事業承継」
1-2.個人事業主と法人の定義の違い
個人事業主は、『法人を設立せずに個人で事業を営む者』を指します。
法人とは、『法律で人と同じ権利や義務を認められた組織』と定義されています。経営者自身が保有する株式や事業に用いている資産を後継者に譲渡すれば、法人の経営権および財産権の移行が可能です。
株式会社は、事業承継の手段として『株式譲渡』が選択できるのに対し、個人事業主には株式がありません。経営権や財産権は事業主に属するため、事業承継の際は、事業用資産を個別に移転させる手続きが必要です。事業用資産を売却・贈与した後、現事業主は廃業手続きを行い、後継者は開業手続きを行うのが一連の流れです。
2.個人事業主の事業承継方法は3種類
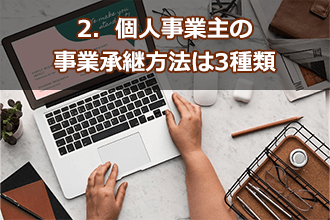
個人事業主が後継者に事業を引き継ぐ際には、『贈与』『相続』『売買』のいずれかによります。それぞれどのような特徴のある手法なのでしょうか?
2-1.贈与でバトンタッチする
現在事業を担っている個人事業主の存命中に、無償で事業用資産を後継者へ譲るのが贈与です。後継者が決まっており、確実な事業承継を目指す場合に用いられます。
事業主の子や孫といった親族が後継者の場合はもちろん、第三者への事業承継でも用いられる手法です。高額な事業用資産でも無償で引き継げる点はメリットですが、贈与税の負担が大きくなるというデメリットもあります。
2-2.相続(遺言)により引き継ぐ
後継者が個人事業主の法定相続人であれば、相続の開始により事業承継するのも一般的です。個人事業主の場合、事業用資産はすべて個人名義のため、ほかの資産と同じように相続財産に含まれます。
相続人が後継者のみであれば、スムーズな引き継ぎが可能です。一方、相続人が複数人いる場合、事業用資産が後継者以外の相続人の手に渡る可能性もあります。
事業に必要な資産を後継者が確実に相続できるよう、事業主は遺言書の作成といった方法で事前に対策をしておかなければいけません。
2-3.第三者に売却する
事業用資産の譲渡によっても、事業承継を実施できます。主に子や孫など親族への承継ができない場合に、従業員や第三者へ事業承継するために用いられる手法です。
所有している資産を売却するため、事業主は対価を取得できます。ただし第三者への承継の場合、事業主が自力で買い手を見つけるのは難しいでしょう。
比較的小規模な事業の売買を扱っているマッチングサービスを利用すると、買い手を見つけやすくなります。また買い手が見つかった後には、価格などに関する交渉も必要です。
『M&A』について詳しく解説している以下の記事も、ぜひご覧ください。
M&Aの代表的な4つの手法
3.個人事業主の事業承継の流れ
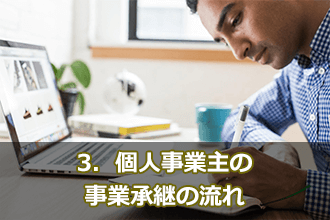
個人事業主が事業承継を行おうとする場合、まず後継者を決定します。そして実際に事業承継するときには、現在事業を営んでいる個人事業主は廃業の手続きを行います。その後、後継者が開業手続きを行い引き継ぐ流れです。
3-1.後継者の選定
まずは誰を後継者とするか決定しましょう。個人事業主として事業を運営する中で、どのようなことを大切にしてきたのでしょうか?その価値観や方針を引き継ぐには、どのような資質を持った人を選べばよいか考えます。
例えば、リーダーシップや論理的な思考・コミュニケーション能力の高さなどが代表的です。実際に事業承継を行った個人事業主は、『専門知識』や『実務経験』『血縁関係』などを重視するケースが多いといえます。
これらの条件を総合し、親族や従業員から後継者を選びましょう。親族や従業員の中で見つからなければ、第三者を後継者とすることも検討します。
参考:会社の跡継ぎは誰が最適?後継者候補の選び方と育成方法
参考:中小企業庁「2019年版小規模企業白書 2 後継者教育」
3-2.後継者への引き継ぎ
後継者が決まったら事業を引き継いでいきましょう。ただし経営権・経営資源・物的資産をすべて一度に引き継ぐと、支障が出る可能性があります。教育期間を兼ねながら、徐々に引き継ぎを進めていくとよいでしょう。
事業に対するお互いの思いや理想、後継者が考える今後の事業構想なども共有します。共通認識を持って臨むことで、より効果的に引き継ぎを進められるはずです。
また個人事業主として事業を運営するときには、信頼や人間関係が重要なため、時間をかけて引き継ぎを行います。
3-3.現事業主の廃業・後継者の開業
後継者に事業の引き継ぎを行った後、現事業主は『廃業手続き』、後継者は『開業手続き』を行います。期限があるため、必要書類を確認して速やかに手続きを進めましょう。
書類の主な提出先は、所轄の税務署です。現事業主は『廃業届』や『青色申告の取りやめ届出書』などを提出します。
後継者は事業開始の1カ月後までに『開業届』を提出しましょう。『所得税の青色申告承認申請書』の提出期限は事業開始から2カ月以内ですが、開業届と一緒に提出すると手間が省けます。手続きの手順は後ほど詳しく解説します。
3-4.屋号の引き継ぎ
個人事業の屋号も後継者に引き継ぐことができます。開業届を提出するときに屋号を引き継ぐ旨を記載するだけで、手続きは完了です。ただし、その屋号が商号登記されている場合は、競業避止義務に違反するため、そのままでは使えない可能性があります。法務局で名義変更の手続きが必要です。
3-5.営業の許認可申請
事業承継するのが飲食店・建設業・理美容業・クリーニング業・酒小売業・旅館業であれば、相続以外で引き継ぐ場合には新たに許認可申請をしなければいけません。
例えば飲食店の場合、相続なら『許可営業者の地位承継届』『営業許可書』『戸籍謄本』『相続人全員の同意書』があれば手続きできます。しかしそのほかの方法で引き継ぐときには、以下の書類をそろえたうえで申請が必要です。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要(調理場の概要など)
- 営業設備の配置図
- 水質検査成績書(貯水槽使用、井戸水使用の場合のみ)
- 許可申請手数料・施設の確認検査など食品衛生責任者の資格を証明するもの
このように事業承継にあたって許認可申請の手続きが必要な個人事業主は、全体の42%にのぼります。
参考:内閣府「個人事業主の事業承継時の許認可手続の簡素化について」
3-6.取引先への連絡、従業員への通知
取引先への連絡も欠かせません。これまでずっと付き合いが続いているからといって、後継者に代替わりしても変わらず取引できるとは限らないからです。
事業承継を行った個人事業主が苦労したこととして、取引先との関係維持を挙げている調査結果もあります。後継者とともにあいさつに行き、顔を覚えてもらいましょう。
また従業員へも事業承継について説明し、後継者を紹介します。事業主が変わることに不安を感じる従業員もいるかもしれませんが、きちんと説明し、理解を得ることが大切です。
参考:中小企業庁「2019年版小規模企業白書 第2節 個人事業者の事業承継」
4.現事業主の廃業手続きを解説
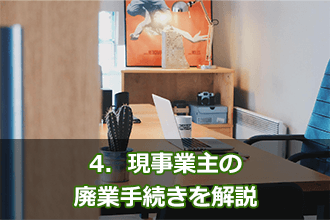
事業の経営権を後継者へ引き継ぐには、まず現事業主が廃業手続きを行わなければいけません。廃業のために必要な三つの手続きをチェックしましょう。
4-1.廃業届などの手続き
個人事業主が廃業する際には、廃業届とも呼ばれる『個人事業の開業・廃業等届出書』という書類を税務署に提出します。書類には『届出の区分』欄の『廃業』にチェックを入れ、後継者の住所と氏名を記載しましょう。
ほかにも以下の必要事項を書き入れ、書類を完成させます。
- 納税地
- 納税地以外の住所地・事業所等
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 所得の種類
- 開業・廃業日等
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
書類は事業承継により後継者へ引き継いでから『1カ月以内』に提出しなければいけません。
4-2.所得税の青色申告の取りやめ手続き
青色申告をしている場合には、廃業届と同じタイミングで『所得税の青色申告の取りやめ届出書』も提出しましょう。廃業届にも、『所得税の青色申告の取りやめ届出書』の提出の有無にチェックを入れる欄があります。
提出期限は事業を廃止した年の『翌年3月15日』までですが、廃業届と同時に提出しておけば手間がかかりません。なお、事業所得のほかに、不動産所得がある場合は、『所得税の青色申告の取りやめ届出書』を提出する必要はありません。
4-3.消費税の事業廃止届出書の提出
消費税の課税事業者であれば、『事業廃止届出書』の提出も必要です。こちらも廃業届に提出の有無をチェックする欄があるため、必要であれば一緒に提出すると手間がかかりません。
提出し忘れると『課税事業者選択不適用届出書』や『簡易課税制度選択不適用届出書』などの効力が消えない点に注意しましょう。廃業したら速やかに手続きが必要です。
5.後継者による開業手続きを解説
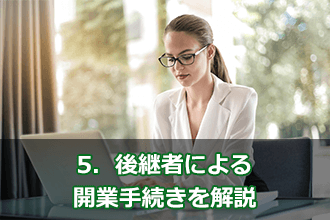
現事業主の廃業手続きが完了したら、後継者が開業手続きを行うことで、経営権の引き継ぎの完了です。後継者が行う5種類の手続きを紹介します。
5-1.個人事業の開業届出の手続き
経営権を引き継ぐ後継者は、個人事業主として開業しなければいけません。開業届とも呼ばれる『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署へ提出します。
現事業主が提出する廃業届と同じ書類ですが、開業時には『届出の区分』の『開業』にチェックし、現事業主の住所・氏名も記入します。
手続きの期限は事業承継をしてから『1カ月以内』です。
5-1-1.給与支払事務所等の開設届出書は不要
従業員のいる事業所を引き継ぐ場合には、『給与支払事務所等の開設届出書』も税務署へ提出します。ただし個人事業主は『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出するため、個別に書類を作成する必要はありません。
『個人事業の開業・廃業等届出書』に『給与等の支払の状況』という欄があるため、記入し提出しましょう。
5-2.青色申告承認申請の提出
確定申告を青色申告で行うなら『所得税の青色申告承認申請書』も、税務署に提出しましょう。『個人事業の開業・廃業等届出書』に提出の有無を記載する欄があるため、チェックの上、同じタイミングで出します。
注意が必要なのは提出期限です。事業承継した年の『3月15日』までが提出期限ですが、1月16日以降に開業した人は、開業の日から2カ月以内に提出します。
青色申告を行っていた現事業主が亡くなり、相続により事業を承継する場合は、事業主の死亡の日から4カ月以内に提出します。ただし、死亡が9月、10月の場合はその年の12月31日まで、死亡が11月、12月の場合は翌年の2月15日までに提出します。
5-3.青色事業専従者給与に関する届出書の提出
納税者と生計を一にする配偶者や親族に対して給与を支払う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出も必要です。税務署に届け出ておくと、これらの人に支払った給与を経費として計上できます。
提出期限は経費として計上する年の『3月15日』までです。ただし1月16日以降に開業した人は、開業の日から2カ月以内に手続きをします。
5-4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
雇用している従業員がいる場合、事業主は従業員の所得税を源泉徴収税として給与から差し引き納税しなければいけません。本来であれば源泉徴収税は徴収した月の翌月10日までに納付する決まりです。
ただし給与を支払う従業員が10人未満であれば、特例によって納付を半年に1回にできます。そのために必要なのが『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』です。
この書類も、『個人事業の開業・廃業等届出書』に届出の有無をチェックする欄があります。必要に応じてチェックし同じタイミングで提出しましょう。
5-5.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書の提出
建物や機械など事業に用いられる資産は、時の経過とともにその価値が減少します。このような資産を『減価償却資産』といいます。減価償却資産を取得した場合、その年分の経費にするのではなく、数年かけて分割して経費として計上していきます。
分割して経費にする方法は『定額法』と『定率法』の2種類があります。特に手続きをしなければ、定額法で減価償却を行います。定率法で減価償却を行うなら、『所得税の減価償却資産の償却方法の届出書』を税務署へ提出しなければいけません。
減価償却資産の種類に応じて、定率法を採用した方が有利な場合には、提出しておくとよいでしょう。期限は、開業の日の属する年の確定申告期限です。
6.M&Aによる第三者承継の流れ
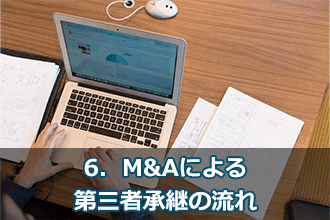
親族や従業員の中に後継者候補がいない場合、M&Aによる第三者承継が選択できます。M&A(Mergers and Acquisitions)とは、事業を他の会社や個人に売却することです。近年は、中小企業や個人事業主の間で事業承継を目的としたM&Aが増加傾向にあります。
※ここでは、事業を譲渡する側を売り手、事業を譲り受ける側を買い手と表記します。
6-1.M&A仲介業者に相談
承継先を個人で探そうとすると、膨大な時間と労力を要します。事業承継の意思が固まった時点で、早めにM&A仲介業者や支援機関に相談しましょう。
M&A仲介業者とは、事業の売り手と買い手を引き合わせるマッチング業務や交渉のサポートなどを行う業者です。契約形態には、売り手と買い手の仲介役をする『仲介型』と、売り手または買い手のどちらか一方をサポートする『FA型』があります。
M&A仲介業者のほかに、以下のような支援機関に相談するのもよいでしょう。
- 事業承継・引継ぎ支援センター
- 金融機関
- 商工会議所
参考:M&A仲介サポートの内容とは?特徴や選び方、相談先の違いも紹介
6-2.事業承継先の選定・交渉
売り手の譲渡情報は、M&A仲介業者に『ノンネームシート』として登録されます。買い手は匿名のノンネームシートから買収先を選定した後、売り手に対して事業内容や財務状況の詳細を記した『企業概要書(IM)』の提示を求めます。
M&Aを実行する手法には、株式譲渡や会社分割、合併などがありますが、個人事業主が選択できる手法は『事業譲渡』です。売り手と買い手の間で、事業の譲渡範囲や価格を交渉した後、基本的な合意内容をまとめた『基本合意書』を締結します。
参考:ノンネームシートの役割とは。記載内容や作成上の注意点を解説
参考:基本合意書の意味と内容。独占交渉権の付与など重要なポイント
6-3.デューデリジェンス
『デューデリジェンス』とは、買い手が売り手に対して行う買収前の調査です。税理士や公認会計士などの専門家の力を借りて、主に以下のような観点から売り手の実態を調査します。
- 売り手から提供された資料が正しいかどうか
- 隠れた債務や税務リスクがないか
- 譲渡価格は適正か
- 保有資産が実在するか
調査で重大な問題やリスクが発覚した際は、譲渡価格の引き下げや条件の変更、M&Aの取りやめなどが選択されます。
デューデリジェンスの費用は、買い手が負担するのが一般的です。売り手は、調査が円滑に進むように、買い手に協力する必要があります。
参考:M&Aにおけるデューデリジェンスの役割。調査項目や進め方を知る
6-4.契約の締結・統合
デューデリジェンス・最終交渉を経て『最終契約書』を締結します。基本合意書には一部を除いて法的拘束力がありませんが、最終契約書はすべての条項に法的効力が生じます。再交渉や内容の変更はできないため、内容を入念にチェックしましょう。
個人事業主の場合、事業資産の譲渡や対価の支払い、引き継ぎ手続きなどを終えると、M&Aの一連の流れは完了です。
現事業主が長年かけて築き上げてきた事業を、短期間で承継するのは容易ではありません。後継者の監督・指導のため、一定期間は現事業主が事業に留まるケースも見受けられます。
7.事業承継により発生する税

先代の事業主から必要な資産を引き継ぎ事業承継を行うと、後継者に税金が課されます。納めなければいけない代表的な税金を確認しましょう。
7-1.贈与税
現事業主から後継者に無償で資産を引き継ぎ事業承継を行うと、後継者は『贈与税』を納めなければいけません。課税対象となる資産の価格から基礎控除額『110万円』を差し引いた残りの金額をもとに、税額を計算します。
父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫への贈与には、『特例税率』が用いられます。税率と控除額は以下の通りです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば引き継ぐ資産の合計額が3,500万円の場合には、『{(3,500万円-110万円)×50%}-415万円=1,280万円』となります。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
参考:贈与税に関する全知識|税率・計算方法から6つの非課税制度まで徹底解説
7-2.相続税
資産を引き継いだ後継者が『相続税』を納めるケースもあります。現事業主が亡くなり、相続で事業用資産を引き継ぐ場合です。
相続税は遺産の価格をもとに計算しますが、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で算出する基礎控除額を下回る価格であれば、相続税は課税されません。
例えば遺産が4,000万円、法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円で相続税は非課税です。基礎控除額を超えた部分は、法定相続分に応じて各相続人に按分し、その金額から以下の税率と控除額を用い相続税を算出します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
遺産が9,000万円、法定相続人が子ども3人の場合、基礎控除額は4,800万円で、遺産のうち4,200万円が課税の対象になります。
4,200万円を3等分した1,400万円に税率15%をかけて50万円を控除し、その金額(160万円)を3人分合算した480万円が相続税の総額となります。この480万円は、3人の相続人が実際に相続した財産の割合に応じて按分します。
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
参考:相続税の計算方法を解説!具体例・シミュレーションソフト付き!
7-3.所得税・消費税・固定資産税など
後継者が事業を引き継いだ年には、先代事業者も後継者も確定申告が必要です。例えば事業承継を行ったのが9月1日なら、先代は8月末までの、後継者は9月1日からの収入について、『所得税』の確定申告を行います。
先代事業者が亡くなった場合は、死亡を知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告が必要です。また『消費税』の課税対象でないかという点も確認しましょう。2年前の課税対象となる売上が1,000万円を超えたりインボイス制度へ対応したりして課税事業者になると、申告と納税が必要です。
また土地や家屋など不動産を引き継ぐと『固定資産税』や『都市計画税』もかかります。
8.税負担の軽減・納税資金の準備を考えよう
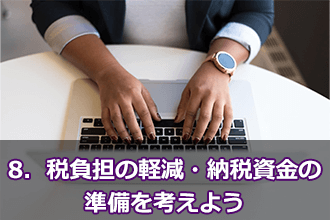
贈与税や相続税は、現金による一括納付が原則です。そのため何も対策していなければ、多額の納税資金でその後の事業が立ち行かなくなる可能性があります。制度や保険を活用し、負担の軽減や納税資金の準備が必要です。
8-1.相続時精算課税制度の活用
『相続時精算課税制度』を使うと、2,500万円までは贈与時点で贈与税がかかりません。ただし贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税制度で贈与した資産は相続財産に持ち戻され、相続税がかかる仕組みです。
この制度の対象は、贈与が発生した年に60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子どもや孫への贈与です。
2024年1月1日以降の贈与からは年110万円の基礎控除が設けられたため、110万円以下であれば贈与税申告も不要となります。基礎控除が適用された部分は、贈与者が亡くなったときに相続財産に持ち戻す必要もありません。
また2,500万円を超える部分には贈与税がかかりますが、一律20%と税額を抑えやすいのも特徴といえます。
相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日に『相続時精算課税選択届出書』の提出が必要です。一度相続時精算課税制度を利用すると、その後は暦年贈与を選択できないため注意しましょう。
参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
参考:相続時精算課税制度とは│必要書類や手続きを分かりやすく解説
8-2.生命保険の活用
相続税を軽減できる可能性のある方法として、『生命保険』の活用も検討しましょう。保険金は『500万円×法定相続人の数』で算出できる非課税限度額までは、相続税がかかりません。相続税が課されるのは、非課税限度額を超えた部分です。
また先代事業主に生命保険をかけ、受取人を後継者に指定すれば、受け取った保険金で相続税を納められます。
8-3.個人版事業承継税制の活用
贈与や相続により事業承継を行うと、後継者は贈与税や相続税を負担しなければいけません。税率が高く大きな負担になりやすい税金のため、納税できたとしても、その後の事業運営に資金面で悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで役立つのが個人版事業承継税制です。青色申告を行っている事業者が、経営承継円滑化法の認定を受けた後継者に贈与か相続で事業用資産を譲る場合、要件を満たしていれば納税が猶予されます。
後継者の死亡時や、一定期間経過後に後継者がさらに贈与で事業承継を行うと、猶予されていた税金が免除される仕組みです。
ただし満たすべき要件が複雑で、途中で要件を満たせなくなると、猶予されていた税金と利子税を支払わなければいけません。
事業承継税制については、以下の記事もご覧ください。
事業承継税制とは│納税猶予の要件や手続きをわかりやすく解説
国税庁「個人版事業承継税制」
8-3-1.要件、書類提出に注意
個人版事業承継税制を活用するには、期限に注意が必要です。対象となるのは『2028年12月31日』までの贈与もしくは相続ですが、適用を受けるには、2026年3月31日までに、後継者が都道府県に『個人事業承継計画』を提出しなければいけません。
(税制改正により『個人事業承継計画』の提出期限は延長されていますが、個人版事業承継税制の適用期限そのものは延長されていないため注意が必要です。)
また引き継ぐ資産を選べない点にも注意しましょう。事業用資産に不要なものが含まれていたとしても、そのまますべて引き継がなければならず、デメリットが大きいケースもあります。
加えて、事業用の宅地については、要件を満たすと事業用の土地の評価額が80%減額される、『小規模宅地等の特例』とは併用できない点にも注意しましょう。
9.個人事業主の事業承継における注意点

個人事業主が事業承継する場合、事業に関する資産や債務を一つずつ引き継ぐ手続きが必要です。加えて相続による事業承継であれば、相続人間のトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
9-1.複雑な手続きが多い
法人の事業承継の場合、事業に関するあらゆるものは、すべて法人が所有しています。そのため必要なのは、代表者が交代するための手続きのみです。
一方、個人事業主が事業承継をする場合には、個別に手続きしなければいけません。現在の事業主の廃業と後継者の開業の手続きはもちろん、納税義務者に関する手続きも必要です。
資産の引き継ぎも個別に行わなければならず、取引先と交わしている契約書の名義変更も行います。また従業員との雇用契約も結び直さなければいけません。
手続きは個人でもできますが、提出書類を不備なくそろえるのは大変です。中には専門的な知識が必要な手続きもあるため、必要に応じて税理士をはじめ専門家へ相談しながら進めるとよいでしょう。
事業承継の際の専門家選びについては、以下の記事もご覧ください。
事業承継の相談ができる専門家とは。選ぶときのポイントなどを解説
9-2.負債や個人保証の引き継ぎ
事業承継によって後継者が引き継ぐのは、プラスの資産だけではありません。『負債』や『個人保証』も後継者が引き継ぐのが一般的です。
ただし負債や個人保証の引き継ぎには、金融機関の同意を得なければならず、手続きが煩雑になりやすいでしょう。スムーズな事業承継を目指すなら、あらかじめ借入金を返済し、個人保証をはずしておくのがおすすめです。
事業資金で返済する方法のほか、事業者の個人資金を貸し付けて返済に充てる方法もあります。
9-3.相続時にトラブルになる場合がある
個人事業主の場合、事業用に使っている資産もすべて個人名義です。そのため相続時には、相続人間の遺産分割協議の対象財産に含まれます。
後継者がすべての事業用資産を引き継ぐには、遺言書の作成が有効です。しかし後継者が事業用資産を相続することで、他の相続人が最低限引き継ぐ権利のある『遺留分』の侵害が起きた場合、『遺留分侵害額請求』により金銭の支払いを求められる可能性があります。
また後継者以外の相続人が事業に用いている資産を引き継ぐと、第三者に売却する可能性もあるでしょう。トラブルが発生すれば、スムーズな事業の継続に支障が出るかもしれません。
遺留分侵害額請求については、以下の記事もご覧ください。
遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説
9-4.早めに準備を開始することが重要
事業承継は、先代の想いや知恵を後継者に引き継ぐことでもあります。単なる物品の売買と違い、事業承継にはそれなりの時間・労力がかかるものです。後継者をしっかりと育成する場合、5~10年ほどの準備期間が必要でしょう。
親族や従業員の中に後継者がいない場合は、後継者探しからのスタートとなります。理想の人物がすぐに見つかるとは限らないため、スケジュールには十分な余裕を持つことが重要です。
病気や加齢による急な引退の可能性も想定して、事業承継の準備は体力があるうちに進めておきましょう。
参考:事業承継に必須のスケジュール作成。いつ、どんなことを実施するのか
10.専門家へ相談しスムーズに進めよう
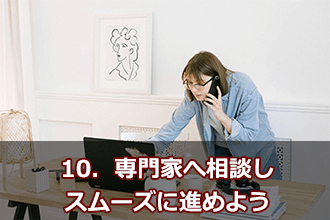
個人事業主の事業承継は手続きが複雑です。資産の引き継ぎを個別に行わなければならず、契約の名義変更も行わなければいけません。
廃業や開業の手続きのほか、事業内容によっては許認可の取得も必要です。個人版事業承継税制で節税するには、その手続きも行います。専門知識が必要な手続きもあるため、必要に応じて税理士や司法書士などに相談しましょう。
税理士法人チェスターでは、相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。