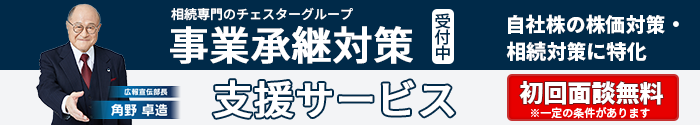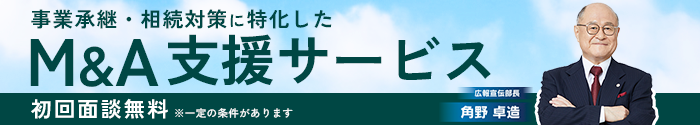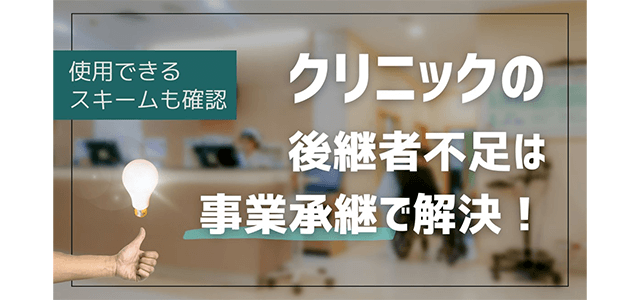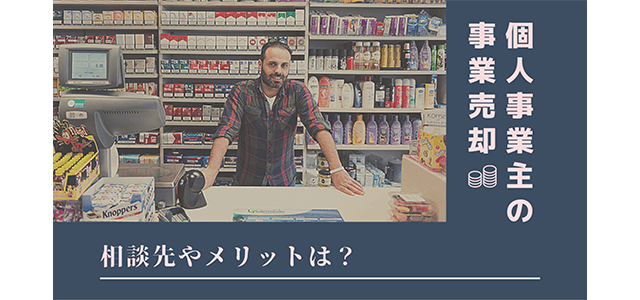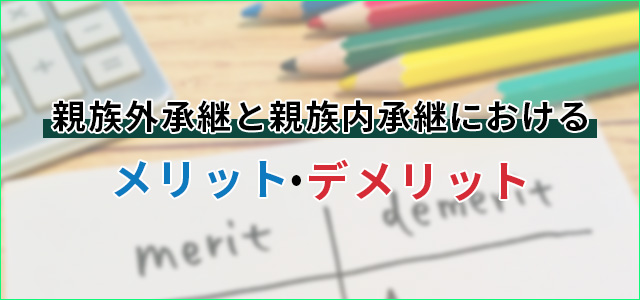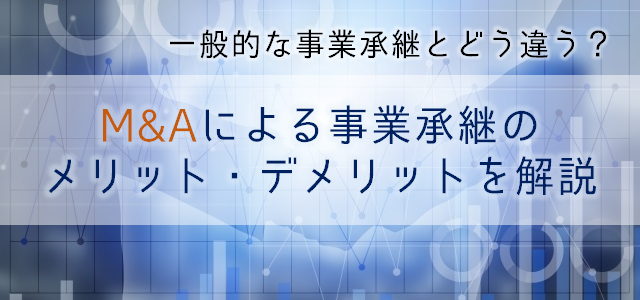事業承継の相談はどこでできる?主な相談先と選び方を確認
タグ: #M&A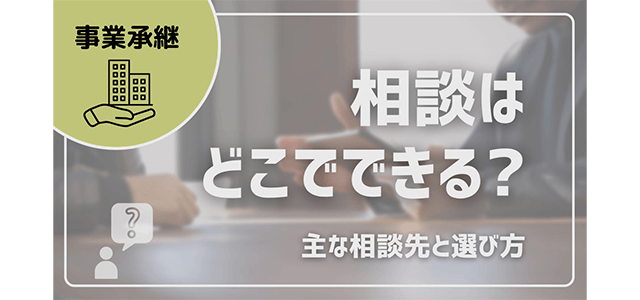
事業承継の検討を始めたら、プロに相談するとスムーズに進めやすくなります。自社に最適な相談先を選ぶポイントを押さえた上で、相談先を決めましょう。あわせて事業承継の準備や進め方も解説します。事業承継計画についても確認しましょう。
目次 [閉じる]
1.事業承継の相談先

事業承継の相談先は複数あります。代表的な相談先として、『M&A仲介会社』『金融機関』『商工会議所』『事業承継・引継ぎ支援センター』『士業』の特徴を解説します。
1-1.M&A仲介会社
会社を第三者へ売却するM&Aにより事業承継する計画なら、M&A仲介会社への相談がおすすめです。豊富な案件を扱った実績のある仲介会社であれば、社内にノウハウが蓄積されており、スムーズなM&Aにつながりやすいでしょう。
担当するM&Aアドバイザーも、M&Aに関する幅広い知識を持つスペシャリストです。豊富な知識を持つ担当者に任せることで、不備なく手続きを進められるのもポイントといえます。
M&A仲介会社ならではのネットワークを生かし、買い手候補の紹介を受けられるのも、仲介会社を利用するメリットです。
参考:M&A仲介サポートの内容とは?特徴や選び方、有名な5社も紹介|税理士法人チェスター
1-2.金融機関
日ごろから付き合いのある金融機関に相談するのもいいでしょう。事業承継に力を入れ始めている金融機関が増えているため、充実したサポートを受けられる可能性があります。
金融機関ならではのネットワークにより、自社とのシナジー効果を期待できる買い手候補が見つかる可能性もあるでしょう。
必要に応じて提携している専門家の紹介を受けられ、また買い手候補による買収資金の調達をサポートできるのも金融機関ならではです。
参考:銀行がM&Aで果たす役割は何か?企業との関係で異なる役割を確認
1-3.商工会議所
入会しているなら、商工会議所に相談するのも一つの方法です。所属している弁護士や税理士などから、事業承継へ向けたアドバイスを受けられます。事業承継に関するセミナーを開催するケースもあるため、参加してみてもよいでしょう。
事業承継の手続きに関するサポートは依頼できないものの、「何から始めればよいのだろう?」「どの専門家にサポートを依頼するとよいのだろう?」など、最初に抱く疑問を解消するのに向いている相談先です。
1-4.事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する相談窓口です。中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に、無料で対応しています。各都道府県にあるため、会社の所在地にある窓口へ問い合わせてみましょう。
親族内承継を実施予定なら、スムーズな引き継ぎに役立つ事業承継計画策定のサポートを受けられます。M&Aによる第三者承継なら、マッチングや各種手続きのサポートを期待できるでしょう。
また事業承継では、会社の債務に対し経営者個人が負う連帯保証である経営者保証が課題として挙げられるケースもあります。事業承継・引継ぎ支援センターなら、経営者保証の解除についても相談が可能です。
1-5.税理士や弁護士などの士業
税理士や弁護士などの士業に相談してもよいでしょう。まずは会社の事業や内情にくわしい、顧問税理士や顧問弁護士に相談するのも一つの方法です。
顧問税理士や顧問弁護士が事業承継にそこまでくわしくない場合、横のつながりで専門知識を持つ士業の紹介を受けられるかもしれません。
自社に現時点で付き合いのある税理士がいないなら、税理士法人チェスターに相談してみてはいかがでしょうか?事業承継の豊富な実績により、的確なアドバイスを受けられるでしょう。
2.事業承継の種類別でおすすめの相談先
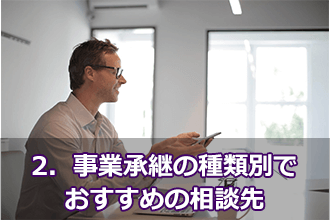
事業承継は『親族内承継』『従業員承継』『事業承継型M&A』に大別されます。プロセスや手続き方法、リスク対策は承継パターンによって異なるため、いつ・誰に・何を相談するかを見極めるのが肝要です。
2-1.親族内承継
親族内承継とは、会社の後継者を血縁・親族関係者から選ぶ方法です。
オーナー企業の大半は非上場企業であるため、自社株式の価値がいくらなのかを確認しないまま、事業承継の時期を迎えてしまうケースが少なくありません。
株式の評価額が高額になれば、後継者となる親族に多額の相続税や贈与税が課せられる可能性があります。自社株対策や相続対策にくわしい税理士に相談するのが賢明でしょう。
親族間での相続・贈与トラブルに備えて、弁護士にアドバイスを求めるのも有用です。後継者の持株比率を増やすにあたり、株式の買い取りが難航する際も、適切な助言が得られるでしょう。
参考:事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方
2-2.従業員承継
従業員承継では、自社の従業員の中から後継者を選びます。後継者候補の選択肢が広い上、自社の事業に精通した人物に会社を任せられるのがメリットです。
株式譲渡では、現経営者の株式を従業員が買い取るのが通例です。従業員に十分な資金がない場合、従業員は銀行やファンドから融資を受けなければなりません。自社株の評価額が高すぎれば、事業承継自体が失敗する可能性もあるでしょう。
税理士や金融機関に早めに相談し、資金対策・税金対策をしっかりと行う必要があります。
参考:株式譲渡にはどんな手続きが必要?契約や税金に関する基礎知識
2-3.事業承継型M&A
事業承継型M&Aとは、親族や従業員以外の第三者に事業を承継する方法です。第三者承継を選択する企業のほとんどは、後継者不在の状態からスタートするため、後継者探しをサポートしてくれる支援機関に相談するのが望ましいといえます。
事業承継・引継ぎ支援センターには、創業を志す起業家と後継者不在の中小企業を引き合わせる『後継者人材バンク』があります。登録料が不要なため、最初の相談先としてふさわしいでしょう。
手厚いサポートを受けたい場合は、民間のM&A仲介会社を利用するのがおすすめです。中間金や成功報酬などの各種手数料が発生しますが、豊富な知見と経験に基づき、依頼者に適した相手を探してくれます。
参考:M&Aで事業承継問題を解消。M&Aの流れ、コツ、かかる費用を解説
3.M&A仲介会社の種類

M&A仲介会社は仲介型とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)型に区別されます。厳密には、『M&A仲介会社=仲介型』であり、FA型は売り手と買い手を取り持つ業務は行わないのが一般的です。両者の特徴や違いを見ていきましょう。
3-1.売り手・買い手を取り持つ「仲介型」
仲介型は、売り手と買い手の両方と契約を結び、中立的な立場に立ってサポートを行います。マッチングでは、売り手・買い手の要望を聞き、それぞれにふさわしい相手を探します。
利益のバランスを考慮しながら、双方が納得できるような落としどころを探っていくため、友好的で円満な取引を望む企業に向いています。国内の中小企業のM&Aは仲介型が一般的で、FA型はそれほど多くない傾向です。
仲介型は成約する確率が高い半面、条件や価格面である程度の妥協を覚悟する必要があります。建前上は中立ですが、仲介会社を通じて売り手の戦略が買い手に筒抜けになり、高値で売却できる機会を失う可能性もゼロではありません。
参考:M&A仲介のビジネスモデルを解説。メリットやデメリットも要確認
3-2.売り手・買い手どちらかの専任になる「FA」
FAは売り手または買い手のどちらかと契約を交わし、契約者の利益の最大化を目指します。M&A仲介会社の主な業務はマッチングですが、FAは助言業務がメインです。
仲介型のような利益相反が起こらない上、交渉では自社の意向を最大限に反映してくれるのがメリットです。相手に戦略が筒抜けになることがなく、戦略策定からアフターフォローまでを安心して任せられます。
一方、双方に公平な着地点を目指しているわけではないため、交渉の長期化や破談のリスクがある点には注意が必要です。
好条件での成立を望む企業や絶対に譲れない条件がある企業、事業承継までに時間的な余裕がある企業は、FAが向いているでしょう。
参考:M&Aアドバイザリーとは?サポート内容や契約時の確認ポイント
4.相談先を選ぶポイント

事業承継の相談先を選ぶ際には、実績・専門家とのつながり・規模感がポイントです。担当者との相性のよさもM&Aの成否に深く関わるため、実績や数字だけに捉われないようにしましょう。相談先を選ぶ際にチェックすべき点を解説します。
4-1.事業承継の実績がある
専門的な知識や経験が重要な事業承継については、豊富な実績のある相談先を選びましょう。実績は、これまでに携わってきた事業承継の件数をチェックします。あわせてどのような支援を行ってきたのか、内容も確認しましょう。
自社の業種に関する経験についても確認しておくと役立ちます。相談先が業種について深く理解していれば、最適なサポートを受けやすいでしょう。その分、シナジー効果を得やすい買い手候補と出会いやすくなるかもしれません。
自社の強みを生かせる相手へと事業承継できれば、引き継いだ事業が長く続き、より拡大していくことを期待できるでしょう。
4-2.専門家との連携が可能
後継者や買い手に会社を引き継ぐ事業承継の実施時には、税務・法務・労務など幅広い専門知識が必須です。分野ごとに内容を深く理解し、会社の状況を的確に判断する必要があるため、専門家との連携が重要といえます。
相談先が専門家と連携していれば、必要に応じて依頼が可能です。相談先への連絡のみで必要なサポートを受けられるため、事業承継をスムーズに進めやすくなるでしょう。
4-3.自社の規模に合っているか
自社の規模に合う相談先かという点も、確認が必要です。仲介会社や金融機関でも、大企業のM&Aを専門に扱っている相談先と、中小企業をターゲットにしている相談先とがあります。
同じ金融機関でも、メガバンクは大手企業向けのサポートを、地方銀行は中小企業向けのサポートを実施しているのが特徴です。
中小企業が大企業をターゲットにしている相談先を利用すると、希望するようなサービスを受けられないでしょう。最適な買い手候補が見つかりにくいのに加え、手数料は高額です。
これまでの実績や抱えている案件をチェックし、自社の規模に合うことを確認した上で相談しましょう。
4-4.話しやすさ・相性も大切
M&Aの成否は、担当者との相性にも影響されます。特に売り手にとって、会社の売却は1回きりの大きな決断です。
『従業員の今後が心配』『赤の他人への事業承継に抵抗がある』といった本音を理解してくれる担当者であれば、満足のいく事業承継が成立しやすいでしょう。
一方、担当者との相性がよくないと、情報共有が滞ったり勝手に話を進められたりといったトラブルが生じかねません。相談先の実績や規模も大事ですが、担当者の人柄をしっかりと見極める必要があります。
4-5.費用・報酬面も確認
相談先によって、費用や報酬が異なります。資金が潤沢でない中小企業や個人事業主は、どのタイミングで・いくら費用がかかるのかを事前に把握しましょう。
M&A仲介会社の多くは『成功報酬』を導入しています。取引価格が高額になれば、報酬額も高くなる傾向があるため、手数料の相場や計算方法をチェックしておくことが重要です。
完全報酬型の場合、M&Aが成約した段階ではじめて報酬が発生しますが、完全報酬型以外では、相談料・着手金・中間金・リテイナーフィー(定額顧問料)などがかかるケースがあります。
参考:M&A手数料の相場を確認。レーマン方式の計算方法も解説
5.事業承継時に必要な対策や準備
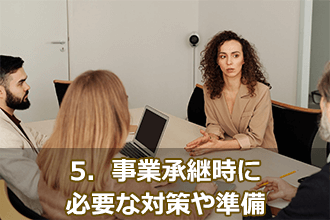
事業承継をするときには、スムーズな引き継ぎができるよう、事前の対策や準備が必要です。具体的に検討・実施すべきこととして、相続対策や自社株対策・事業承継税制の利用について解説します。
5-1.相続対策
子どもをはじめ親族への事業承継を行う際には、相続を利用するケースが多いでしょう。ただし自社株や事業用資産の価値は高くなりやすく、高額な相続税の納税が必要です。現状のまま後継者に引き継ぐと、納税資金が不十分な場合もあります。
納税のために借入をしたり、手元の現金を大きく減らしたりする結果になれば、事業の継続に支障が出るおそれもあるでしょう。このような事態が起こることのないよう、相続税を抑えられないか検討するのが相続対策です。
あわせて納税資金の用意や、後継者以外の相続人との財産の分け方について準備する遺産分割対策も欠かせません。
参考:【相続税対策22選+7つの控除】注意点・節税効果を税理士が解説!|税理士法人チェスター
5-2.自社株対策
自社株対策は大きく二つに分けられます。後継者が引き継ぐ株式の議決権割合が100%に近くなるよう実施する対策と、相続税額を抑えるために行う評価額を下げる対策です。
後継者が経営権を取得できるよう、十分な自社株を引き継ぐには、ほかの相続人へ預貯金や不動産といった別の相続財産を用意しておくとよいでしょう。法定相続人が最低限受け取れる相続財産の割合である遺留分を侵害しないよう、分与の割合に注意が必要です。
株価を下げるには、事業用以外の資産の処分や設備投資・役員退職金などが役立ちます。
参考:企業オーナーの事業承継対策について専門の税理士が徹底解説
5-3.事業承継税制の利用を検討する
後継者の納める相続税の負担を減らす方法として、納税猶予や免除を受けられる『事業承継税制』を活用するのも有効な方法です。ただし利用するには、たくさんの要件を満たし続けなければいけません。
スムーズな利用には、専門家のサポートが必要です。また利用にあたり円滑化法の認定を受けなければいけません。認定を受けるまでに時間がかかるため、制度の利用を検討しているなら、早めに対策を始めましょう。
事業承継税制に関して解説している以下も、ぜひご覧ください。
自社株式の生前贈与・相続税が無税になる事業承継税制の特例を徹底解説|税理士法人チェスター
6.事業承継の進め方
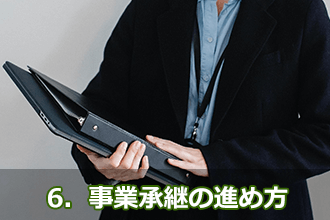
事業承継を行うには、会社の経営に必要なあらゆる資源を後継者に引き継がなければいけません。手続きや教育に手間と時間がかかるため、進め方の手順を確認し、順を追って行うと効率的です。
6-1.自社の現状把握
まず行うのは、自社の現状把握です。買い手候補へのアピールになる強みは何か、あらかじめ伝えておくべき弱みは何かという点をはっきりさせましょう。
会社の現状に課題があるなら、洗い出しと解決も行います。例えば調査を依頼した結果、未払い残業代があると分かったのであれば、対象者に残業代を支払いましょう。経営者保証が課題であれば、解除に向けて取引している金融機関に相談します。
後継者が「継ぎたい」と思うような魅力ある会社になるよう、状況を改善するのがポイントです。会社の経営理念やビジョンも明確にしましょう。事業承継時に後継者と共有することで、自社ならではの長所も引き継いでいけます。
6-2.後継者の選定と育成
自社の現状やビジョンをはっきりさせたら、後継者選びを行う段階です。自社の今と理想の未来が明確になることで、どのような後継者を選べばよいのかがはっきりします。
経営者に必要なリーダーシップを発揮し、組織を運営する力があるかも見極めが必要です。事業承継することに対する覚悟も、あわせて確認しましょう。従業員・取引先・金融機関など、周囲の関係者から協力を得られそうな後継者であるかもポイントです。
また後継者を決定したら育成も行います。一般的な育成期間は4~5年ですが、業種や後継者の現状によっては、10年以上かかるかもしれません。余裕を持って育成するには、早めに後継者を選定するとよいでしょう。
参考:後継者育成にかかる期間や必要な準備は?社内、社外の教育方法も紹介
6-3.関係者への説明
後継者が決まったら、関係者への説明も行います。会社の関係者は株主・金融機関・取引先・従業員などが代表的です。これまで築いてきた信頼関係が壊れないよう、細心の注意を払います。
例えば従業員の協力を得やすくなるよう、まずは現場に配属するとよいでしょう。会社の事業に対する理解につながり、仕事を通して従業員との関係性も構築しやすくなります。
金融機関や取引先へは、後継者とともに訪問しておくのが有効です。あらかじめあいさつしておき、繰り返し訪問することで、後継者への信頼を得やすくなるでしょう。
参考:事業継承したい場合、何から始める?準備と活用必須の支援制度|税理士法人チェスター
7.事業承継計画が役立つ

スケジュール通りに事業承継を進めるには、『事業承継計画』の作成が役立ちます。いつまでに何をしなければいけないかが明確になり、あらかじめ決めた期限に合わせ事業承継を完了させられます。無料でダウンロードできるひな形を利用すれば、手軽に作成しやすいでしょう。
7-1.ひな形を利用すると作成しやすい
事業承継計画を立てるときには、経営計画やスムーズな事業承継に向けた計画などを盛り込む事業承継計画書や、年度ごとに実施する項目や目標を書き込む事業承継計画表のひな形を利用するのがおすすめです。
ひな形には、事業承継計画を立てるのに必要な項目が最初から記載されています。記入例を参考に自社に照らし合わせて書いていけば、事業承継計画書と事業承継計画表が完成するはずです。
ただし、ひな形に記載されている項目をそのまま埋めればよいというわけではありません。自社の状況に合わせて必要な項目をプラスしたり、不要な項目を削除したりすることで、適切な事業承継計画を作成できます。
7-2.作成の手順
作成するときには、まず後継者と会社の経営理念を共有しましょう。従業員に十分に浸透し、会社として実践できているのであれば、そのまま承継するとよいでしょう。時代とともに従業員の共感が得にくくなっているようであれば、見直しも検討します。
同時に経営ビジョンを明確にします。何を目的とした事業なのか、目的達成のために具体的にどのような数字を達成するのか、これらの内容を経営の基本方針とともに策定しなければいけません。
次に行うのは、事業承継の対策や実施時期の決定です。後継者を育成したり、事業関係者への理解を関係各所へ促したり、実際に手続きを行う時間も検討します。
明確になった内容を、ひな形を利用して書面に落とし込み、後継者と共有しましょう。
参考:事業承継計画は後継者への引継ぎに必須。策定のコツや手順を解説|税理士法人チェスター
8.事業承継は相談先があるとスムーズ
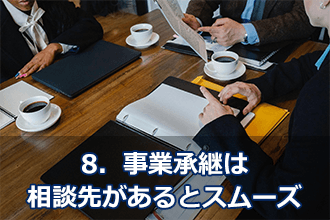
事業承継を行うには、事前に対策や準備が必要です。スムーズに手続きを進めるには、事業承継計画の策定も役立ちます。ただし、自社のみですべてを行うのは難しいでしょう。
専門的な知識や手続きのサポートが必要なため、相談先があると安心です。M&A仲介会社や金融機関、商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センター、士業は代表的な相談先といえます。自社の業種や規模なども考慮しつつ、適切な相談先を選びましょう。
税務に関する調査であれば、税理士法人チェスターを検討するとよいでしょう。相続事業承継のコンサルティングに特化した専門税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。