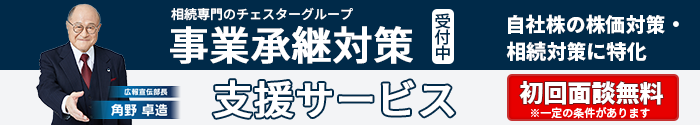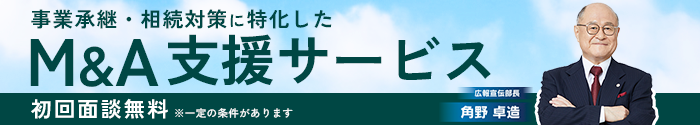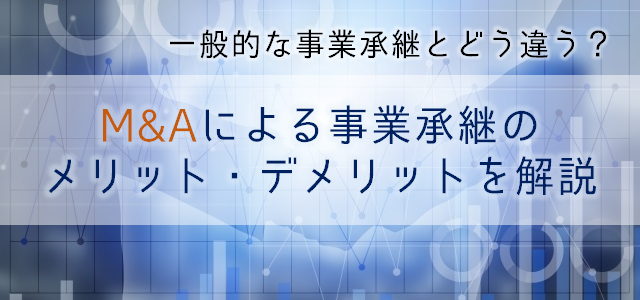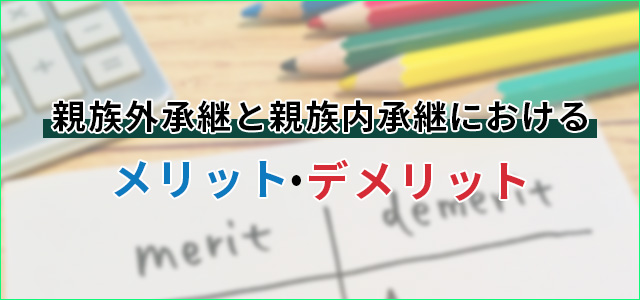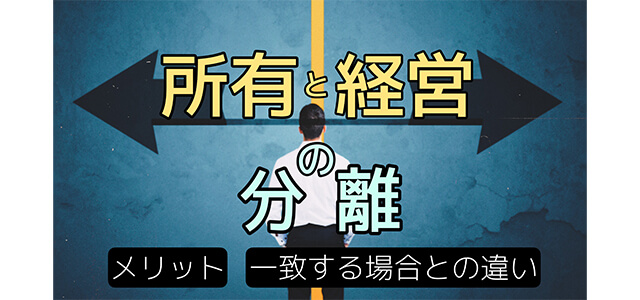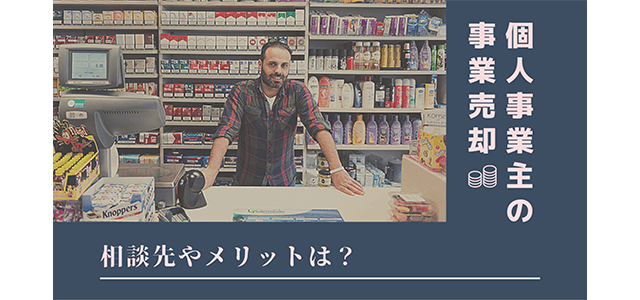企業オーナーの事業承継対策について専門の税理士が徹底解説
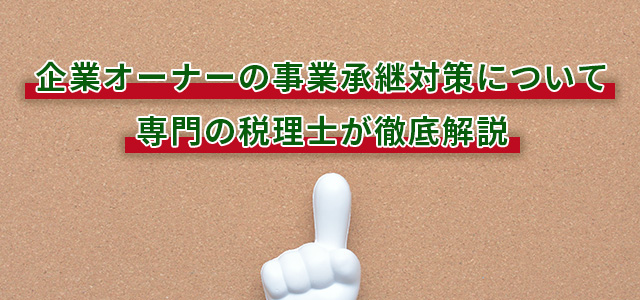
オーナー経営者にとって、事業承継は、経営者人生の集大成ともなる重要な取り組みです。望んだ通りの事業承継に成功すれば、その後も、会社の成長・発展は約束されるでしょう。逆に、事業承継に失敗してしまうと、会社の存続も危うくなる恐れがあります。
また、非上場のオーナー企業で親族内承継となる場合には、法人の事業承継と個人の相続を切り離すことができません。そのため、個人の相続対策も見据えて総合的に事業承継を考える必要があります。
本記事では、非上場のオーナー企業経営者を対象に、事業承継対策の基本と全般的な流れを解説します。
目次 [閉じる]
1.事業承継とはそもそも何か
最初に、「事業承継」という言葉に含まれる内容を正確に理解しておきましょう。
事業承継とは会社を承継させることですが、「誰に」「何を」承継させるのかは、さまざまなパターンがあります。
1-1.承継相手の3つのパターン
事業承継は、承継させる相手が誰かにより、次の3つのパターンがあります。
| 親族内承継 | 子や配偶者など、親族に承継させる |
| 社内承継 | 役員、従業員など、親族関係がない社内の人間に承継させる |
| 第三者承継 | M&Aにより、第三者に承継させる |
1-2.事業承継に含まれる内容
事業承継には、2つ、あるいは、3つの内容が含まれています。
1つ目は、会社と事業の「経営」を後継者に引き継ぐことです。
2つ目は、会社の「オーナーシップ」を引き継ぐことです。オーナーシップとは株主としての権利のことで、「所有権」「支配権」とも言い換えられます。
この2つは、事業承継に必ず含まれます。
そして3つ目として、親族内承継の場合に限っては、「相続」に関連する内容も含まれます。
上の3つは、必ずしも同時におこなわれるとは限りません。例えば、代表取締役として経営は後継者に引き継がせるものの、株式は承継せずに、オーナーシップはそのまま、ということもあります。
1-3.オーナーシップと業務意思決定権
株式会社には、必ず株主と取締役がいます。
株主は株主総会において会社の存続や取締役の選任・解任など、会社に関する重要事項を決定したり、配当金などの利益配分を受けたりする権利を持ちます。株主総会の議決権を左右できる議決権数(株式数)を持つ株主が、その会社の最高意思決定者となります。
一方、取締役は株主から委任されて、経営上の意思決定(業務的意思決定)をおこなう権利が与えられます。
このように、株主と取締役(社長)の役割は、本来異なるものです。会社の最終意思決定機関は株主総会なので、取締役(社長)より株主のほうが、立場としては「上」です。
なお、会社のトップであることを示すために、代表取締役は「社長」とも呼ばれますが、「社長」は法律に規定されている役割ではありません。
1-4.非上場企業の大半は、オーナーシップと経営が一体化したオーナー企業
株主と取締役を同じ人間が担ってもかまいません。1人の経営者が、株主として会社のオーナーシップを持ち、同時に代表取締役として業務意思決定もおこなっている状態を、俗に「オーナー経営」と呼びます。また、オーナー経営状態の会社は「オーナー企業」、その経営者は「オーナー経営者」などと呼ばれます。
非上場企業の大半は、創業者であり代表取締役である経営者(経営者と意思を同じくする親族などを含めて)が、株式のすべてあるいは大半を保有しているオーナー経営になっています。
1-5.オーナーシップを表す自社株は、相続財産となる
オーナーシップ(株主としての権利)を表す自社の株式(以下「自社株」と表記)は、相続税法において、財産的な価値を持つものとされ、相続財産となります。
親族内承継や社内承継の場合は、この財産をどうやって移転させるかという論点も重要であり、事業承継に含めて考えることが一般的です。
2.オーナー企業で早めの事業承継対策が必要な3つの理由
オーナー企業においては、次の3つの理由から、なるべく早く事業承継対策に取り組む必要があります。
2-1.安定した承継を実現して、適切な会社経営を継続させるため
事業承継の最大の目的は、会社をこれまでどおりに存続させ、事業を継続・発展させていくことです。したがって、承継後も安定的な経営ができるように、後継者に経営者としての考え方、知識、スキルなどを引き継がなければなりません。
また、後継者が滞りなく経営を続けられるように、役員、社員や取引先など、社内外の理解を得て環境を整備する必要もあります。
これらのことは一朝一夕にできるものではないため、早期からの準備が必要になるのです。
さらに、経営者に複数の子がいる場合など、承継候補者が複数いる場合は、誰に経営権を承継させるのか、他の候補者はどう扱うのかなども、慎重に考慮して決めなければならず、これも事業承継対策の一部となります。この点をおろそかにすると、事業承継後に、経営権を巡っていわゆる「お家騒動」が勃発することにもなりかねません。
2-2.自社株を適切な評価額で移転するため
オーナーシップを承継するためには、後継者に自社株を移転しなければなりません。
自社株を後継者に移転する方法は、誰に承継させるのかによって、以下のとおりとなります。
| 親族内承継 | 贈与/相続/譲渡(後継者が買い取る)のいずれか |
| 社内承継 | 譲渡(場合によっては贈与や遺贈も) |
| 第三者承継(M&A) | 譲渡 |
いずれの場合においても、移転時の自社株の株価が重要なポイントになります。
自社株の評価額は、会社の業績や財務によって変化します。そこで、自社株が適切な評価額となるタイミングを見計らって承継することがポイントです。その準備にも時間がかかります。
2-2-1.親族内承継や社内承継の場合
この場合、後継者の経済的な負担を低く抑えることが考慮されます。そのために、なるべく株価が低くなるタイミングで自社株を移転することが基本となります。株価が低ければ、贈与税、相続税の負担や譲渡対価も低くなるからです。
2-2-2.第三者承継の場合
この場合、親族内承継や社内承継とは逆に、株価が高ければ高いほど、経営者が受ける経済的メリットが大きくなることはいうまでもありません。
第三者承継(M&A)での譲渡における自社株の評価額の算定は、相続や贈与における評価とは考え方が異なります。ただし、業績や財務の内容に応じて変わるので、タイミングを見計らうことが大切だという点では同じです。
2-3.相続と一体で考える必要があるため
自社株は経営権を表すものであると同時に、相続財産としての価値も持ちます。そのため、親族内承継において、相続人が複数いる場合(例えば、親が経営者で、子が3名いる場合など)、経営権を誰に、どのように承継させるのかという経営権承継の問題と、遺産分割の問題とが、密接に関連してきます。
親族内承継の場合、会社経営の安定と、すべての相続人が納得する遺産分割が両立できるような事業承継を目指す必要があるのです。その準備や対策にも時間がかかります。
なお、親族外への第三者承継(M&A)をする場合であれば、事業承継と相続は直接には関係しません。
3.事業承継対策をすぐに検討すべき会社のケース
事業承継をすぐにでも検討したほうがいいケースは、以下のとおりです。
3-1.オーナー経営者が60歳程度になった場合
オーナー企業において、経営者に不測の事態が生じて経営の執行が不可能になれば会社は混乱に陥ります。
経営者が高齢になればなるほど、健康上の理由などで、突然仕事ができなくなるリスクは高まるでしょう。病気や事故などだけではなく、最近とみに増えているのが、認知症によるトラブルです。
経営者が認知症を発症し、意思能力に問題が生じた場合には、株主総会で経営者を交代させようにも、経営者自身が株主であれば、株主総会を開催することもできなくなります。重要な決定がなにもできなくなってしまうのです。
そのような事態を防ぐためにも、遅くとも、オーナー経営者が60歳くらいになったら、事業承継の準備を具体的に進めておくべきといえます。
3-2.親族内に後継候補者が不在の場合
子が親の後継者となって会社を引き継ぐ親族内承継の割合は、現在では4割以下しかありません。半分以上は、親族外への承継となっています。
親族内に「必ず後継者となる」という人がいる場合は、その人を育成すればいいのですが、そういう人がいない場合、事業承継をどうするのか、早めに考えておく必要があります。
社内の役員、社員から後継者を抜擢するのであれば、経営者としての教育とあわせて、オーナーシップ(株式)の移転方法をどうするのかを検討しなければなりません。
また、第三者承継を検討する場合、そもそも相手が見つかるのかどうかが問題となり、M&A仲介会社などへの相談も必要です。
3-3.自社株の株価が高額となっている場合
業績が良かったり内部留保が多かったりする会社の株価は、想定以上に高くなることがあります。
親族内承継や社内承継の場合、自社株の株価が高騰していると、移転コストが高くなるため、承継の妨げになります。
株価が下がりそうなタイミングを見極めるための対策が必要となりますが、その準備や実行には時間がかかるため、早めの取り組みが必要です。
4.事業承継対策の流れとステップ
事業承継の準備と実行までは、以下のような流れで進みます。
4-1.(1)現状分析
会社の経営状況、経営課題、経営資源(人、モノ、カネ)などを、分析して把握します。具体的には以下のような項目を確認します。
- 自社の経営理念、ミッション、ビジョン、バリューやそれを達成するための長期戦略
- 自社の事業を巡る現在の市場環境や、将来の市場成長性
- 市場における自社事業のポジション、強みや弱み、収益力の源泉
- 新しい市場や収益源の開拓可能性
- 組織や人材の強み、弱み、改善余地
- 収益、費用、利益、キャッシュフローなどの現状と改善余地
- 財務状況、資産状況の現状と改善余地
4-2.(2)後継候補者の選定・育成
後継候補者を選定して、経営者として必要な業務知識を教育して、育成します。
親族内承継の場合、早いうちに子などに、「会社を継ぐ気はあるのか」とはっきりたずね、明確な回答を得ておくべきです。そして、本人にその気があるのなら、一定期間、一通りの現場業務につかせて業務を覚えさせ、次にマネジメント業務を担当させます。
注意しなければならないのが、親が「子は、当然後継経営者になるだろう」と思い込んでいたところ、いざ承継をしなければならなくなった時点で、実は子にはその気がないとわかった、というケースがよくあることです。親子だからと思い込みをせず、必ず言葉に出して確認することが大切です。
また、社内承継をさせる場合にも、「君には次期社長になってほしい」と明言して、本人の意向を確認することが大切です。
「うちの会社には経営者になれるような人材がいない」と社長は思い込んでいるものの、きちんとたずねてみたら、やる気のある人物が登場するということもあります。経営者としての資質があるかどうかの判断は別ですが、「社内には経営人材はいない」という思い込みはしないほうがいいでしょう。
もし、親族内にも、社内にも後継候補者がいなければ、M&Aを検討します。
4-3.(3)事業承継のための経営改善
事業承継成功のためには、経営改善が必要です。
親族内や社内に人はいるのに後継者候補が現れない場合、経営状態が理由となっているケースはよくあります。
債務超過に陥っていたり、毎期赤字が続いたりしている会社、市場や事業内容に将来性が見込めないような会社では承継しても苦労するのは目に見えています。そんな状態の会社では、経営者の子でも、引き継ぎたいと思わないでしょう。
そこまで悪い内容の会社ではないにしても、後継者にやる気を持って経営にあたってもらうには、業績や財務状態を改善し、将来の成長性が感じられる事業をおこなうことが大切です。
また、非上場の中小企業では、組織運営や業務プロセスに、非合理的な面や不透明な部分があったり、経営者の属人性に頼りすぎていたりすることが、よくあります。このような状態があるなら、組織運営や経営手法を見直して改善をします。
事業内容や組織運営などの経営改善は、俗に「磨き上げ」とも呼ばれます。
経営を磨き上げておけば、第三者承継をする場合でも、買い手が現れやすく、株価が高くなりやすいというメリットがあります。
親族内承継や社内承継の場合、経営改善は、後継候補者の選定に先立って進めておければそれに越したことはありませんが、後継候補者が決まった後で、その人物と一緒に進めることでもいいでしょう。どちらが先でもかまいません。
4-4.(4)事業承継計画の策定・計画書の作成
事業承継を進めていくにあたっては、自社の現状を整理するとともに、承継後の会社が中長期的に何を目指していくのか(承継後の経営ビジョン)を確認します。そして、承継のために「いつまでに・誰が・何をするのか」という、具体的な実施計画を策定します。これらをまとめたものが、事業承継計画です。
事業承継計画をまとめたら、工程表・計画表に落とし込んだ、承継計画書を作成します。
事業承継計画は、一般的に事業承継の予定時期の10年ほど前に作成しておくことがベターだといわれています。
また、一度策定した事業承継計画は、毎期見直し、事業環境や社内の状況などに変化があれば、それに応じて計画内容を変更・調整します。
詳しくは「事業承継計画は後継者への引き継ぎに必須。策定のコツや手順を解説」をご覧ください。
4-5.(5)相続対策の実施
親族内承継の場合は、自社株の株価対策や自社株移転に伴う課税対策、納税資金対策、将来の遺産分割対策などの、相続対策も事業承継計画に含まれます。
場合によっては、生前贈与や組織再編、事業承継税制の活用などが検討されることもあります。また、遺言の作成も必要になります。
4-6.必要に応じて、士業や支援機関への相談を
現状分析から、事業承継計画の策定、相続対策まで含めた総合的な事業承継の実施には、法務や税務も含めた専門的な知識が必要です。経営者だけでおこなうことは困難であり、会社の顧問弁護士、顧問税理士はもちろん、相続にくわしい専門税理士などの力を借りることが必要です。
何から取り組めばいいかわからないという状態であれば、まずは、商工会、商工会議所、メインバンクや、事業承継・引継ぎ支援センター(中小機構)などの公的機関に相談するのがよいでしょう。
5.親族内承継、社内承継における自社株移転コスト対策
中小企業でも、財政状態が良好なら、自社株の株価が数億円~数十億円の評価となることもあります。高額な株価は、親族内承継または社内承継においては、阻害要因となることがあります。
そこで、自社株の株価が下がるタイミングを見定めたり、税制上用意されている特例制度などを利用したりすることで、なるべく有利な自社株の移転タイミングを計画することが大切です。
以下で、対策方法の概略を説明しますが、いずれの方法も、中途半端な知識で実施すると、かえって負担が大きくなったり、脱税行為と認定されるリスクがあります。
自社株対策の実行にあたっては、必ず、相続税にくわしい専門税理士に相談をした上で、検討するよう、ご注意ください。
5-1.株価が下がるタイミングをとらえる
非上場企業の株式を相続、贈与などによって移転する場合、その株価は、国税庁が公表している「財産評価基本通達」に定められた方法で算定します。
計算方法は複雑なので詳細は省略しますが、基本的には、そのタイミングの直前期、直前々期、直前々々期の3年間の決算における、①利益、②純資産、③配当の3つの要素を基準にして決められます。
ごく大雑把にいえば、①利益、②純資産、③配当のいずれか、あるいはすべてが高ければ、株価は高くなり、低ければ株価は低くなるということです。
株価が下がるのは、①利益が減る、②純資産が減る、③配当が減る、のいずれかのタイミングなので、そのタイミングを狙って自社株を移転するというのが、基本的な考え方になります。
5-1-1.利益が減るタイミングを見定める
利益は損益計算書に計上されるもので、「売上-費用」で求められます。売上の動向を正確に予測・コントロールすることは難しいですが、費用は会社の行為によって支払われるものなので、ある程度正確に予測できます。
例えば、代表取締役が退職して、高額な役員退職金を支給すれば、その期の利益は大きく減るでしょう。そのタイミングで自社株も移転するのは、よく用いられている方法です。ただし、過大な退職金は、税務署から損金算入が否認される場合がある点に注意が必要です。
その他、会社で契約する生命保険や、オペレーティングリースなどの課税繰り延べ商品を使って、費用を増やす方法などもあります。
5-1-2.時価純資産が減るタイミングをとらえる
ここでの純資産は、貸借対照表に計上されている資産額(簿価)を、相続税評価額で洗い直した純資産です。
よく用いられるのが、会社で事業用不動産を購入して純資産を圧縮する方法です。これは不動産の評価における実勢価格と相続税評価額との乖離に着目するものです。
ただし、会社で不動産を購入してから3年間は利用できないなどの制限があるため、注意が必要です。
他にも、なんらかの支出をすることで純資産を減らす方法はありますが、無駄な支出で財務内容が悪化しては本末転倒であることに注意してください。
5-1-3.配当額を調整する
いままで高額な配当を出していた会社なら、減額することで株価が下がる場合があります。ただし、一定期間、配当と利益の両方がゼロ以下だと、今度は特別な計算方法が適用されて株価が逆に高くなることがあり、注意が必要です。
5-2.会社組織再編の活用
会社組織を再編することで、自社株式の評価額を下げる方法もあります。よく用いられている代表的な方法は、持株会社を作る方法です。
まず、後継者(子)が新しく会社を作り、そのオーナー経営者となります。新会社は銀行から融資を受けて、その資金で、オーナー経営者(親)が経営している事業会社の株式を、オーナー経営者(親)から買い取ります。すると子が経営する会社は、事業会社に対する持株会社(親会社)となり、事業会社の実質的な経営支配権は子に移ります。
その後、事業会社は持株会社に対して毎期配当を出します。持株会社は、受け取った配当で、銀行への融資を返済していきます。
この時点で、事業会社の元のオーナー経営者(親)が持っていた自社株は、子がオーナー経営者となっている持株会社に100%移転されており、事業承継は完了しています。その後に親が亡くなっても、自社株の相続は発生しません。
ちなみに、少し専門的な話になりますが、事業会社の株価が将来上昇した場合、その株を100%持つ持株会社の株価は、その分上昇するのではなく、37%の控除がおこなわれて割り引かれた上昇になる仕組みがあります(一定の条件に該当する場合)。
この仕組みにより、後継者である子が将来、次の後継者(孫)に持株会社を承継させる際の、自社株の株価を下げることができるという効果も生じます。
5-3.生前贈与の活用
自社株の評価額が一時的に下がるタイミングが予測できれば、そのタイミングにあわせて、自社株を贈与することで、計画的にオーナーシップの承継が可能となります。
生前贈与には、贈与税の暦年課税と相続時精算課税のいずれかを利用する2通りの方法があります。
5-3-1.贈与税の基礎控除を利用して、節税を図る
暦年課税には、年間110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられています。
また、相続時精算課税には、2024年以後の贈与から暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除が設けられています。
いずれも、年間に110万円と、比較的少額の非課税枠ですが、毎年利用できるため、10年で1,100万円、20年なら2,200万円分の資産を、非課税で移転することができます。
これを利用して、長い年月をかけて自社株を毎年少しずつ後継候補者に贈与すれば、税負担を減らすことができます。
ただし、この長年かけて贈与をする方法には、注意点が3つあります。
1つ目は、その贈与が、もともとまとまった財産を贈与する意図があって、それを分割して贈与している「定期贈与」だと税務署から見なされると、そのまとまった金額に対して1回の基礎控除しか認められなくなる点です。毎年贈与する場合、定期贈与だと見なされないように注意する必要があります。
2つ目は、基礎控除額が年間110万円と比較的少額のため、自社株の評価額が数億円から数十億円になるような場合には、金額が小さすぎて手間のわりには効果が薄いことです。
3つ目は、一度おこなった贈与は、状況が変化しても取り消せないことです。
例えば、最初は子を後継者にしようと考えて自社株を毎年生前贈与したものの、そのうち親子の考え方に違いが出てきて、やはり子は後継者にふさわしくないという判断になったとします。しかし、過去に実施した自社株の贈与を取り消すことはできません。子は株主となるため、経営に混乱が生じる恐れも出てきます。
5-3-2.相続時精算課税による贈与を利用して節税を図る
相続時精算課税は、年間110万円の基礎控除以外に、贈与時点では課税されない2,500万円の特別控除枠が利用できます。ただし、この制度で贈与した財産のうち基礎控除を行った残額は、贈与者に相続が発生した時点で、贈与者の相続財産に戻されて、相続税が計算されます。
相続時点で課税される「課税の繰り延べ」をできることが、相続時精算課税の特長です。
なお、2,500万円の特別控除枠を超えた分の贈与税は、一律20%での課税となります。
ここでのポイントは、相続税を計算する際の課税評価が、「贈与時点の財産評価額」でおこなわれる点です。
例えば、相続時精算課税の特別控除枠で贈与した2,500万円分の自社株の株価が、相続時には贈与時の2倍の5,000万円になっていたとしても、贈与時の2,500万円で評価されて課税されるので、有利になります。
ただし、逆に相続時の株価が贈与時よりも下がっていたとしても、贈与時の高い株価を適用して相続税を計算しなければなりません。
このようなリスクがあることが、相続時精算課税の注意点です。
また、特別控除枠は2,500万円しかないので、やはり株価が数億円を超えるような場合は、全体の課税額から見て、得られる効果は限定的といえます。
5-4.事業承継税制
一定の条件を満たすことで、自社株の贈与または相続にかかる課税がすべて猶予されるという、非常に大きな節税効果を得られるのが「事業承継税制」という制度です。
同制度には、一般措置と特例措置との2種類があります。一定の要件を満たして特例措置を用いれば、後継者が相続や贈与によって自社株を引き受けた場合、その自社株にかかる相続税や贈与税がすべて納税猶予されます。つまり実質的に、自社株の課税がゼロになります。
(特例措置ではない、通常の事業承継税制(一般措置)では、発行済議決権株式総数の3分の2までの税額について相続税は80%、贈与税は全額が猶予されるという制限があります)。
ただし、本制度はあくまで納税の「猶予」制度であり、「免除」されるわけでないことに注意が必要です。事業承継後の期間内に経営を辞めるなどして、条件から外れた場合は、その時点で利子を加えた税金を納税する義務があります。
他にも、本制度は、適用条件など細かいルールがありますので、制度にくわしい税理士に相談の上、検討してください。
なお、事業承継税制の特例措置は時限措置となっており、本記事執筆時点では、2026年3月31日が「特例承継計画」という必要書類の提出期限、また、2027年12月31日(個人事業の場合は、2028年12月31日)が、相続や贈与をおこなう期限となっています。
事業承継税制について、詳しくは「事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ」をご覧ください。
6.事業承継における遺産分割争い防止対策
例えば3人の子がいるオーナー経営者が、3人の間での公平を考えて、自社株を分散して3分の1ずつ贈与または相続したとします。このようにすると、株主となった3人の子たちの間で会社経営を巡って意見対立が起きた場合に経営が混乱します。
経営の安定化という観点からは、後継者(代表取締役)となる1人の相続人に、なるべく集中して自社株を承継させることが望ましいとされています。
しかし、オーナー経営者に、自社株以外の相続財産が少なければ、後継者となる1人以外の子が承継できる遺産が少なく、不公平な遺産分割となって、今度は遺産分割をめぐってもめる恐れが生じます。
特に、一部の相続人の遺留分を侵害するような遺産分割になれば、トラブルは必至です。
そこで、後継経営者以外の相続人にもなるべく公平に、最低でも遺留分は侵害しないように遺産分割ができるように準備をしておくことも、オーナー経営者の事業承継の大切なポイントです。自社株以外の資産をたくさん残せればいいですが、そうできなかった場合には、以下のような方法もあります。
6-1.生命保険金を用いた代償分割
オーナー経営者である被相続人が契約者となり、後継者が受取人となる生命保険に加入しておきます。死亡後に、後継者は自社株を集中して承継し、また、生命保険金(相続財産ではない)を受け取ります。そして、その生命保険金で、他の相続人に遺産代わりの代償財産を支払って納得してもらうのです。このような方法を代償分割といいます。
詳しくは「代償分割の要件と相続税の計算方法をわかりやすく解説!」をご覧ください。
6-2.種類株式の発行
通常の株式とは異なる特殊な株式が「種類株式」です。オーナー経営者の生前に、自社株の一部を種類株式にしておくことで、遺産分割争いを防げることがあります。
例えば、「配当をもらう権利はあるが、株主総会での議決権はない」というタイプの種類株式を発行し、後継経営者以外にはその株を贈与し、議決権のある株式は後継者だけに贈与します。それなら、株主総会が混乱することはありません。また、後継者以外の相続人も、配当がもらえれば不満は生じにくいでしょう。
6-3.遺言の作成
遺言の作成は、遺産分割対策の基本ですが、事業承継が関連する場合には、特に有用性が高く、必ず早期に作成しておくべきものです。オーナー経営者に突然、万一のことがあった場合も想定して、その後の経営や財産分割を指定しておけば、会社も家族も混乱は最小限ですみます。
逆に遺言が残されていなかったばかりに、相続人に加えて会社の役員なども巻き込んだ争いが起き、いわゆる「お家騒動」の状態になって、あっというまに会社が傾いてしまうことは、よくあります。
また、遺言には、自由に書ける付言事項があります。後継者に自社株を集中して承継させる場合などは、付言事項に「会社のことを考えてこうしたのであって、決して他の相続人をおろそかに考えているわけではありません」といった具合に、自分の考えを率直に書き残しておけば、多少不平等な遺産分割になっていても、たいていの相続人は納得してくれるものです。
詳しくは「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」をご覧ください。
7.まとめ:オーナー経営者の事業承継対策は、やることが多い
事業承継においてもっとも大切なのは、承継後も会社を存続させ、事業を発展させることです。その上で、課税対策や遺産分割対策など、考えなければならない事柄が多く、時間もかかることが、オーナー経営者の事業承継の特徴です。
経営の承継と相続を総合的に考慮した事業承継計画を立てるためには、早期に動くことと、サポート経験の豊富な専門家のアドバイスを受けることがポイントです。最初はどこから取り組めばいいのかを、まずは気軽に相談してみましょう。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。