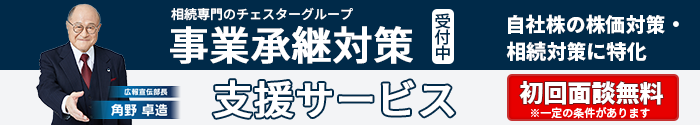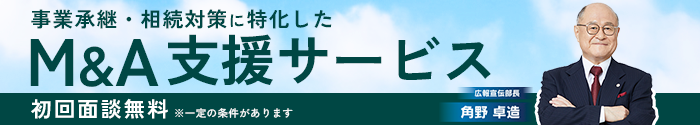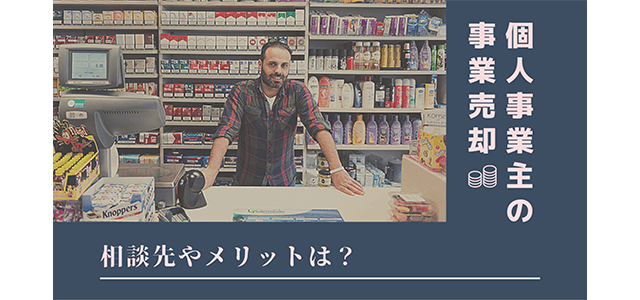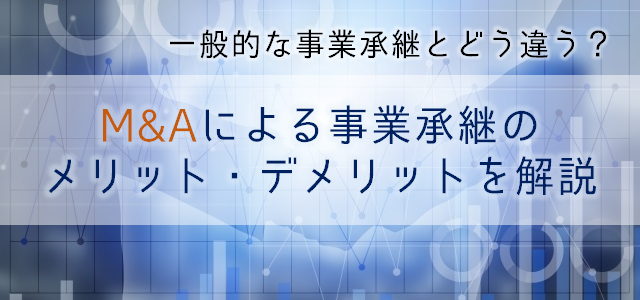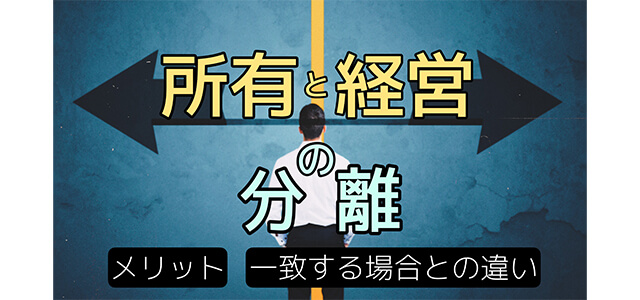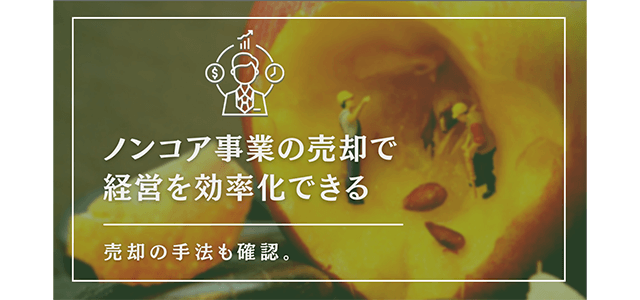製造業のM&Aを成功させるポイントは?事例とともに紹介
タグ: #M&A, #M&A×業種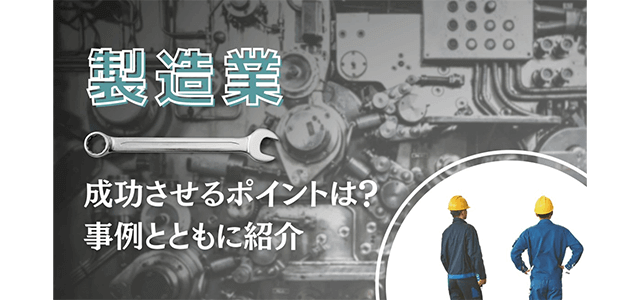
製造業では、中小企業が大手企業の傘下に入るM&Aが多い傾向があります。どのような企業であれば高額で売却できるのでしょうか?またM&Aを行うメリットもチェックしましょう。製造業で行われたM&Aの成功事例も紹介します。
目次 [閉じる]
1.製造業のM&Aの動向は?

製造業は全体で見ると業績が低下しつつあります。その結果、開発に取り組みたくても資金が不足している企業も多いでしょう。M&Aによって中小企業が大手企業の傘下に入るケースが多い傾向です。
1-1.製造業の現状
日本の製造業は、1980年代までは国際的にも高い競争力を持ち、業績は好調に推移していました。安くて高品質の製品が人気を得て、世界を相手に多くのヒット商品が生まれた時期です。
しかし1990年代以降は、安くて高品質という特性は中国や韓国企業に取って替わられてしまいます。商品間の質の差も以前ほどありません。競争力が低下した日本製品のシェアは下がり、全体の業績も低下中です。
経済産業省の『令和3年度(2021年度)の中小企業の動向』によると、製造業の開業率は5%にも満たない状況です。設立時に多額の設備投資を要する点において、製造業は他業種よりも参入障壁が高い傾向があります。
参考:令和3年度(2021年度)の中小企業の動向 I-31|経済産業省
1-2.中小企業の売却が多い傾向
全体の業績が落ち込んでいる製造業では、中小企業が大手企業の傘下に入るM&Aが数多く実施されています。以前ほどのシェアを獲得できなくなった企業は、業績の落ち込みにより、次の商品を開発する体力が残っていないケースも少なくありません。
そこで資金力のある大手企業に自社を売却し、培ってきた技術力を生かした開発や、従業員の雇用継続を目指します。資金力の不足で低迷している中小企業を、ファンドが買収するケースもあります。
1-3.廃業を減らす流れが必要
帝国データバンクの調査によると、2022年の休廃業・解散件数(全国)は5万3,426件で、そのうち製造業は2,734件でした。業界全体では、黒字での休廃業が過去最低の54.3%を記録しています。
廃業の要因はさまざまですが、中小企業では『経営者の高齢化に伴う後継者不足』が顕著です。中小企業は国内企業の99%以上を占めており、このまま休廃業が続けば、日本経済の成長力が損なわれかねません。
廃業を食い止める有効な手段として、第三者への事業承継が挙げられます。中小企業の事業承継を支援するため、政府は2017年に『事業承継5カ年計画』を策定しました。さらに、2019年には『第三者承継支援総合パッケージ』を発表しています。
参考:全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年)| 株式会社 帝国データバンク[TDB]
2.「第三者承継支援総合パッケージ」とは
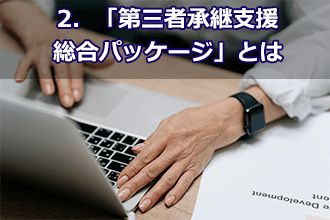
事業承継の後継者は、親族の中から選ぶのがかつては通例でした。しかし近年は、子どもや孫が家業を継がないケースも多く、第三者承継(M&A)が増加傾向にあります。
第三者承継をサポートする『第三者承継支援総合パッケージ』とは、どのような施策なのでしょうか?
2-1.第三者承継を促すための施策
第三者承継支援総合パッケージは、中小企業の黒字廃業を回避するための施策です。中小企業の事業承継には、以下のような課題が存在します。
- 売り手案件が少ない(自社の売却に抵抗がある経営者が多い)
- 経営者の個人保証を理由に、後継者に承継を拒否される
- 承継後の経営統合がうまくいかない
第三者承継の目標件数は、10年間で60万人(毎年6万人)です。第三者承継を阻む課題を解決するため、『機運の醸成』『マッチングの円滑化』『マッチング後の取組支援』の三つのフェーズで、切れ目のない支援を行います。
2-2.主な支援策
マッチング前の段階では、『事業引継ぎガイドラインによる情報提供』や『事業引継ぎ支援センターや民間プラットフォーマー等による仲介の促進』により、事業承継の機運醸成を目指します。
マッチング時においては、経営者の個人保証がボトルネックとなり、事業承継が成立しない事例が多々あります。政府は、新たに『経営者保証解除パッケージ』を策定し、先代経営者と後継者からの保証の二重取りを原則禁止としました。
マッチング後は、経営統合や後継者の育成を促進するため、以下のような施策を用意しています。
- 事業承継補助金の充実化
- 専門家派遣による経営指導
- 登録免許税・不動産取得税の軽減
- その他金融支援
3.M&Aによる事業承継の種類
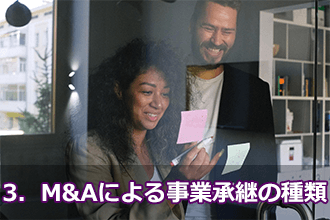
M&A(第三者承継)には複数のスキームがあります。スキームとは、会社または事業の支配権を移行させるための具体的手法です。代表的なものとして、『事業譲渡』『株式譲渡』『会社分割』などが挙げられます。
3-1.事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を売却する手法です。買い手は承継する資産を選択できるため、不要な資産や負債を引き継ぐリスクが抑えられます。
売り手に多額の簿外債務があることが発覚した際、株式譲渡から事業譲渡へとスキームの変更が行われるケースもあります。
雇用関係や取引先、許認可なども譲渡対象となりますが、再契約や許認可の再取得が必要です。移転する資産に税法上の課税資産が含まれている場合、課税資産×10%の消費税が生じる点にも留意しましょう。
参考:事業譲渡の目的、主な特徴とは。専門家の知識が欠かせない理由
3-2.株式譲渡
株式譲渡とは、売り手の株主が保有する株式を買い手に売却し、会社の経営権を移行させる手法です。株式譲渡の成立後、売り手は買い手の子会社となります。
売り手の権利・義務の一切を引き継ぐ『包括承継』のため、従業員や取引先、許認可に関する手続きは不要です。事業譲渡に比べて手続きが簡便で、消費税も発生しません。
一方で、買い手は売り手の負債や不要な資産も引き継ぐリスクがあるため、買収前の調査(デューデリジェンス)をしっかりと行う必要があります。
参考:株式譲渡にはどんな手続きが必要?契約や税金に関する基礎知識
3-3.会社分割
会社分割とは、事業の権利・義務の一部またはすべてを会社から切り離し、承継会社に承継させる手法です。承継先が新設会社の場合は『新設分割』、既存会社の場合は『吸収分割』と呼ばれます。
経営の立て直しなどの企業再生局面で選択されるのが一般的ですが、会社分割で切り離した事業部門の経営を後継者に任せ、経営者としての経験を積ませるケースも見受けられます。
特段の合意がない限り、従業員や取引先との契約関係は承継会社に承継されますが、許認可については『承継されるもの』『行政庁の承認を要するもの』『再申請が必要なもの』に分かれる点に注意しましょう。
なお、中小企業の事業承継では、事業譲渡と株式譲渡が頻繁に用いられます。
参考:会社分割とは何かわかりやすく解説。メリット、デメリットは?
4.高額で売却しやすい企業の特徴
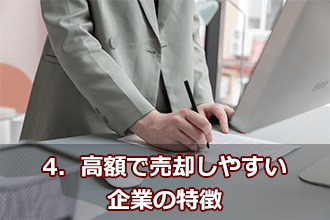
製造業の中でも、設備が新しい・高い技術がある・大手企業との取引があるといった特徴を持つ企業は、比較的M&Aの対価が高くなりやすいでしょう。できるだけ高額での売却を目指すために、役立つポイントを紹介します。
4-1.設備が整っている
製品作りには設備が欠かせません。必要な設備を適切に更新してきており、新しく整った設備が導入されているなら、売却にあたっての対価は高額になりやすいでしょう。買い手は買収しただけで事業を継続できるためです。
メンテナンスをして使い続けている古い設備は、いつ故障するか分かりません。場合によっては、M&A後すぐに入れ替えなければいけないケースもあります。
買い手は買収にかかった費用に加え、設備投資も必要になり、より大きなコストがかかります。新しい設備の導入に必要なコストを考慮し、価格交渉が行われるかもしれません。
設備が古い場合、新しい設備への入れ替えにいくらかかり、どの程度効率化できるかが、対価を決める上でのポイントです。
4-2.製造技術や生産能力が高い
高い製造技術や生産能力を持っている企業は、売却による対価が高くなりやすいでしょう。技術や生産能力があるのに業績が落ちている企業は、資本力の弱さが原因であるケースが多いためです。
資本力が弱いだけであれば、資本力のある買い手が買収することで、すぐにV字回復する可能性があります。利益につながりやすい買収ができるため、M&Aの対価は高額になりやすいでしょう。
4-3.大手企業との取引がある
どのような取引先があるかも対価に影響します。大手企業のように取引を開始するのが難しい企業が取引先にあると、つながりが評価される可能性があるでしょう。
特に買い手が営業力を強化したいと考えている場合には、取引先が充実していることで、対価が高額になるかもしれません。M&Aを行うときには、自社と関係のある取引先を一覧にし、参照しやすいようにしておくと効果的にアピールできます。
5.製造業M&Aの成功事例

実際に製造業の企業が行ったM&Aの成功事例を紹介します。どのような企業が何を目的にM&Aを行い、どのような結果を得られたのか見ていきましょう。
5-1.たから抜型工業と大創の資本提携
たから抜型工業と大創は、どちらも抜型で知られている企業です。たから抜型工業は親族内承継による事業承継も行っていましたが、今後の会社の発展や社会貢献を意識し、大創への売却を決断しました。
どちらも抜型を扱っていますが、手掛けている製品は異なります。お互いの得意分野をかけ合わせることで、M&Aによって高いシナジー効果を期待できると判断したそうです。
またM&A後は大創の営業力とたから抜型工業の技術力によって、これまでカバーできなかった分野への進出も期待できます。
5-2.中央自動車工業によるABTの子会社化
中央自動車工業はボディーコーティングやオイル添加剤など、自社開発製品を中心に取り扱っている企業です。損害保険会社から全損認定を受けた車両の処分に関わるABTの買収を実施したのは、シナジー効果を得る目的でした。
ABTのネットワークを生かし、新しい商品の開発を目指した取引です。またこれまで事業の柱であったカー用品の卸売や部品販売から撤退していたため、新たな事業の柱を獲得したいという思いもあり実施されました。
5-3.商栄機材とJRCのM&A
全国の自治体に自社の環境プラントが導入されている商栄機材は、1976年の創業から少しずつ着実に拡大してきた企業です。環境問題への意識の高まりもあり、業績も安定していました。
しかし親族内承継も社内承継もうまくいかず、いつの間にか経営者は70代を迎えていたそうです。M&Aを実施し会社を売却した話を周りから聞いたことから、M&Aが最適と考え、JRCへの売却を決定しました。
M&Aにより新しく大きな工場が便利な立地に建設され、より多くの人材が集まり成長が期待できる見込みだそうです。
参考: 商栄機材の社名変更および本社・工場移転に関するお知らせ|株式会社 JRC
5-4.日本電産による三菱重工工作機械の株式取得
三菱重工のグループ会社として、ものづくりに携わってきた三菱重工工作機械は、ギヤに関する高い技術力や優れた人材を保有している点が強みです。同社の強みである技術や人材を獲得するため、日本電産は株式を買収し子会社化しました。
技術開発・製造・営業でシナジー効果が期待できるのはもちろん、資金を投入することで三菱重工工作機械が展開していた工作機械事業の拡大や発展も期待されたM&Aです。
両社のブランド力や顧客基盤の活用で、グローバルな活躍が見込まれています。
参考:三菱重工工作機械株式会社の株式取得に関する譲渡契約締結のお知らせ|日本電産株式会社
5-5.ヤマシナによる山添製作所の子会社化
ヤマシナは山添製作所の株式を取得し子会社化しました。2社はどちらも自動車部品をメインにネジを作るメーカーです。中でも山添製作所は、品質管理水準の高さを強みとしています。
山添製作所を買収するM&Aによって、ヤマシナは生産拠点の分割や物流コストの低減が期待できると考えました。同業だからこそ経営改善に取り組みやすい点もポイントだそうです。
また営業面・開発面での相乗効果も期待できることから、M&Aが行われました。
参考:株式会社山添製作所の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | 株式会社ヤマシナ
5-6.シェアリングテクノロジーによる電子プリント工業の子会社化
シェアリングテクノロジーは企業価値の拡大を目指し、電子プリント工業の株式を取得し子会社化しました。電子プリントは白物家電や照明器具のプリント配線板を製造している会社です。
取引先には大手電気メーカーもあり、ここ数年の業績は安定しています。買収によりシェアリングテクノロジーでは、電子プリント工業の持つ取引先も獲得が可能です。
大手電気メーカーとのつながりを生かした、新たな営業戦略も実施できるでしょう。
参考:電子プリント工業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |シェアリングテクノロジー株式会社
6.製造業を売却するメリット
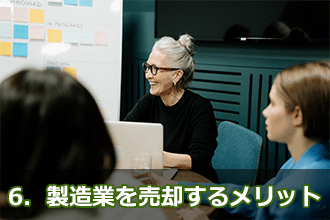
業績が悪化している製造業の中小企業の中には、このままでは経営が続けられなくなってしまうというケースもあるでしょう。また後継者候補がいないために事業承継が進まない事態も起こり得ます。
売却によって、製造業の中小企業が直面している課題の解消につながるかもしれません。
6-1.事業承継できる
かつては親の会社を子どもが継ぐのは当たり前のことでした。しかし近年は価値観の変化もあり、子どもが必ず事業承継するとは限りません。
社内に優秀な人材がいれば、社内承継による事業承継も選択肢の一つです。ただし、ふさわしい人材がいない場合もあるでしょう。親族にも社内にも後継者となる人材がいない場合、M&Aによる第三者への売却で事業承継が可能です。
また業績が悪く今後も改善する見込みがないため、自分の代で廃業しようと決めている経営者もいるでしょう。この場合にもM&Aを活用すれば、自社の技術や製品に魅力を感じる買い手に売却できるかもしれません。
参考:事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説 |税理士法人チェスター
6-2.対価を得られる
企業を売却すると対価を得られます。例えば経営者が保有している自社の株式を買い手に売り、経営権を移転する株式譲渡を行うと、経営者は株式の売却により大きな資金を手にできます。規模や技術などによっては、数千万円以上で売れる可能性もあるでしょう。
経営者は取得した対価を引退後の生活費にあててもよいですし、新しく取り組みたい事業の資金にもできます。売却すれば創業時にかかったコストの回収も可能です。
6-3.廃業を避けられる
経営者が引退するときに後継者がおらず事業承継できなければ、廃業しなければいけません。廃業するには登記や官報公告などが必要で、そのための費用がかかります。弁護士や司法書士に手続きを依頼すれば、その報酬も必要です。
設備や在庫・原材料なども処分しなければいけません。中には売れるものもありますが、すべてを売り切るために、仕入れにかかった金額より安く売らなければいけない場合もあるでしょう。
また廃業すれば従業員は仕事を失うことになり、取引先へも迷惑をかけてしまいます。売却し第三者が会社を引き継げば、廃業によって生じるコストや手間、迷惑をかける事態などを避けられるでしょう。
参考:事業承継できず廃業する際の注意点|税理士法人チェスター
6-4.選択と集中による経営改善の可能性
経営改善にも売却が役立ちます。選択と集中によって、会社の保有する事業から不採算事業を切り離して売却すれば、資金も人材もメイン事業に集中させられます。
業績が改善すれば、設備投資や開発に適切な投資ができるでしょう。魅力ある会社へと成長させられれば、親族や社内で後継者として会社を引き継ぎたいと希望する人も出てくるはずです。
また親族内承継や社内承継は難しくても、より好条件で売却できる可能性が高まります。
参考:ノンコア事業の売却で経営を効率化できる。売却の手法も確認|税理士法人チェスター
7.製造業を買収するメリット

製造業のM&Aは、買い手にもメリットがあります。新しい事業を立ち上げてから利益が出るようになるまでには、多くの時間や手間が必要です。現存する企業を買収すれば、買い手はスピーディーな事業展開ができる可能性があります。
7-1.スピーディーな事業の立ち上げ・拡大が可能
事業の立ち上げには時間や手間がかかります。しかも製造業では設備が必要不可欠です。製品の製造に適切な設備を作るには時間がかかるでしょう。設備を設置する工場を作るためには土地を探す必要もあり、建物も建てなければいけません。
市場で必要とされている製品を作るのに5年かかると、その間に陳腐化しているおそれもあるでしょう。かつては十分なニーズのあった製品も、時期が過ぎれば期待ほど売れなくなってしまいます。
M&Aで企業や事業を買収すれば、必要なものはすべてそろった状態です。事業の立ち上げは既に終わったも同然で、すぐに利益を上げることもできるでしょう。スムーズな拡大に役立つ方法です。
7-2.事業に必要な人材や設備を獲得できる
人材を採用して育成する手間やコストが不要なのも、買収のメリットです。従業員も一緒に引き継ぐ契約にすれば、十分な経験や技術のある人材をすぐに獲得できます。指導しなくても、すぐに自走できる現場の構築が可能です。
また必要な設備もあります。適切な更新とメンテナンスを行っている企業を買収すれば、買収後もそのままで設備を使い続けられるでしょう。
事業を始めるために必要なすべてがそろっているため、買収するだけで事業拡大を実現できます。
参考:中小企業のM&Aが増加する理由。第三者への事業承継とは|税理士法人チェスター
8.知っておきたいM&Aのよくある失敗
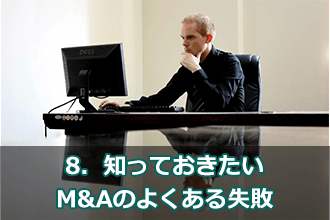
中小企業におけるM&Aは増加傾向にあるものの、すべての事案が成功しているわけではありません。買収後の経営統合がうまく進まなかったり、意図せぬ相手に事業を売却してしまったりして、後悔の念に駆られる経営者も少なくないのが実情です。
8-1.相手企業の言いなりになってしまう
買収意欲の高い買い手はストロングバイヤーと呼ばれ、積極的に企業買収を行います。M&Aの経験が豊富な買い手に対し、売り手は自社売却が初めてのケースがほとんどです。
知識がない上に廃業の危機が迫っていれば、買い手の言いなりになって話を進めてしまう可能性が高いでしょう。
また、M&A仲介会社から進められるがままに交渉を進め、希望価格での売却・買収を実現できずに終わる事例も見受けられます。M&Aの目的や経営戦略、絶対に譲れない条件を明確にした上で、すべてのプロセスに主体的に関わることが重要です。
8-2.M&Aを考えるタイミング
後継者育成を含め、事業承継にかかる期間は5~10年といわれています。M&Aによる第三者承継であれば、数カ月~1年程度で引き継ぎが完了する場合もありますが、十分な引き継ぎ期間を確保するのが理想です。
売り手が事業承継の時期を見誤れば、企業価値が下がったり、経営者の体調が悪化したりして、企業売却が困難になるおそれもあります。
M&A仲介会社に依頼したからといって、理想の売り手・買い手がすぐに見つかるとは限りません。経営者に十分な体力があり、かつ経営が安定しているうちに、事業をさらに拡大させてくれる後継者を探しましょう。
9.M&A成功のポイント

M&Aを成功させるには、相乗効果を意識して買い手を選定しましょう。また適切な時期になるまで、従業員や取引先など関係者に情報が漏れないよう注意が必要です。必要に応じて専門家の活用も検討します。
9-1.相乗効果を期待できる買い手へ売却する
相乗効果を発揮できれば、買い手はより大きな利益を獲得できるでしょう。利益を期待できる分、M&Aが成立しやすく、高額で売却できる可能性があります。
自社の買収によって相乗効果を期待できる買い手へアピールするには、まず自社の強み・弱みを明確にしなければいけません。その上で強みを生かせる買い手候補をリストにし、アプローチする際の優先順位をつけます。
アプローチの結果、自社の価値が十分に伝わり理解してもらえれば、より高額で売却できるでしょう。
参考:M&Aのメリットを細かく紹介。M&Aによる相乗効果や節税効果とは|税理士法人チェスター
9-2.M&Aに関する情報漏えいに注意する
M&Aを進める上では、情報漏えいに注意が必要です。M&Aを検討しているという事実自体、関係者に漏れると混乱を引き起こしかねません。
中小企業にとって経営者の交替は大きな変化です。従業員の中には経営者の考え方や姿勢に魅力を感じて働いている人もいるため、M&Aが行われるタイミングで退職する人が出てくるかもしれません。
M&Aを実施するかもしれないという情報が取引先に漏れると、取引量の縮小や契約終了も起こり得ます。適切なタイミングで関係者に伝えられるよう、検討段階で情報が漏れないよう注意しましょう。
9-3.専門家を活用する
自社を売却するときには、強みや弱みを把握し相乗効果が生まれそうな買い手候補にアプローチします。買い手候補となる企業とのつながりがなければいけません。また交渉を行い条件をすり合わせ、契約書を締結するまでには、法律の知識も必要です。
幅広い分野の専門知識が必要なため、M&Aの専門家に依頼するとよいでしょう。製造業の技術や業界の動向を正しく理解している専門家であれば、スムーズに話を進める上で貢献してくれるはずです。
M&Aは税務にも関係します。買い手による調査の前に自社の税務の状況を確認したい、できるだけ税額を抑えたいという場合には、税理士法人チェスターに相談するとよいでしょう。
10.M&Aで製造業の事業継続に活路が

製造業は、1980年代くらいまでに築いていた業績を近年では上げられていません。その結果、適切な投資ができず、行き詰まりを感じている企業も数多くあります。
経営状況が厳しいままでは後継者候補が現れにくく、事業承継できずに廃業していく企業も少なくありません。
M&Aにより会社を売却すると、親族や社内に後継者がいない場合にも事業を引き継げます。廃業の手間やコストがかからず、従業員の雇用も維持できます。取引先へも迷惑をかけずに済むでしょう。
買い手にとっても、スピーディーに新しい事業を立ち上げられるメリットがあります。ただしM&Aを成功させるには、相乗効果を期待できる買い手を見つけなければいけませんし、情報漏えいへの注意も必要です。
スムーズなM&Aには専門家のサポートも欠かせません。M&Aに関わる税務については、税理士法人チェスターへの相談がおすすめです。
税理士法人チェスターでは、相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。