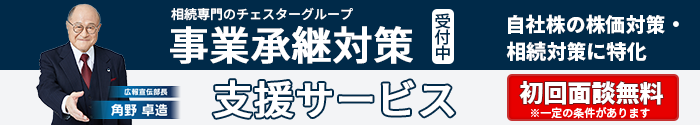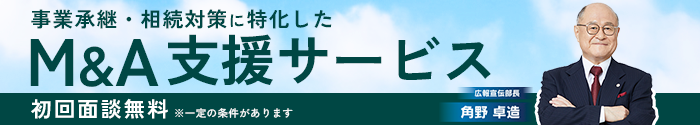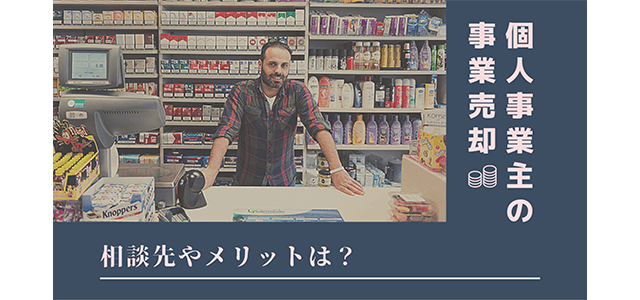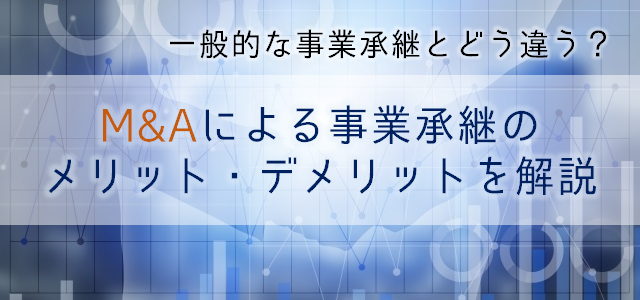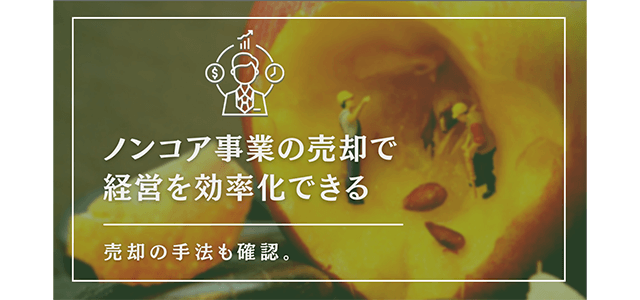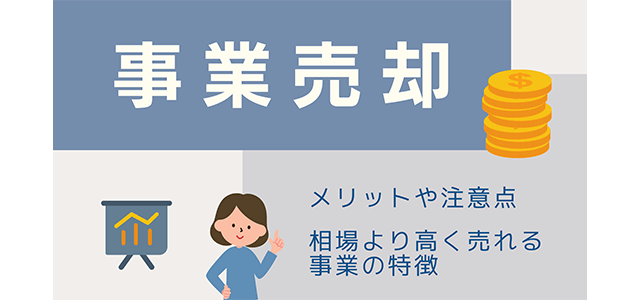事業承継と事業譲渡の違いとは?それぞれの手順や選択基準も解説
タグ: #M&A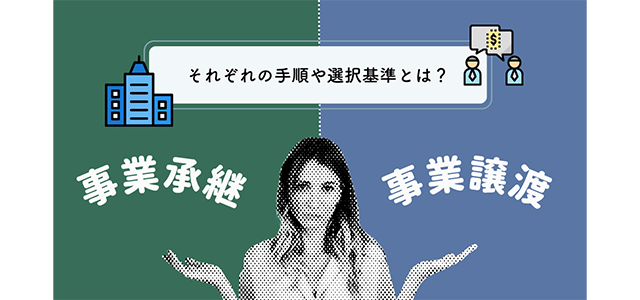
事業承継と事業譲渡は似た言葉ですが、意味は異なります。それぞれどのような意味があるのでしょうか?また、実施するときの手順も異なるため確認しましょう。事業承継と事業譲渡のどちらを選ぶとよいかについても解説します。
目次 [閉じる]
1.事業承継と事業譲渡の違い

事業承継を実施するのは、後継者へ会社を引き継ぐタイミングです。一方、事業譲渡で売却するのは事業のみで、会社はそのまま経営者の元に残ります。事業承継と事業譲渡の違いを把握するために、それぞれの特徴を解説します。
1-1.事業承継は後継者へ会社を引き継ぐこと
後継者へ会社を引き継ぐ事業承継を実施すると、経営者が変わるのが特徴です。これまで経営者が持っていた自社株や事業用資産は、全て後継者へ移転します。株式の承継に伴い経営権を保有するのも後継者です。
親族への承継は贈与や相続で行われるケースが多く、無償で自社株を引き継ぐ場合がほとんどです。一方、会社の従業員や第三者への承継は有償であることが多く、経営者は利益を得られます。
事業承継の始め方やポイントについては、以下もご覧ください。
事業継承したい場合、何から始める?準備と活用必須の支援制度|税理士法人チェスター
1-2.事業譲渡は買い手へ事業を売却すること
事業譲渡は事業の一部もしくは全部を売却することです。移転するのはあくまでも事業のみで、会社の経営権はそのまま経営者が保有し続けます。
売却した事業を所有していたのは会社です。そのため事業譲渡によって得た利益は会社が獲得します。例えば不採算事業を切り離し、利益の出ている事業に集中する場合に利用される手法です。
事業譲渡については、以下もご覧ください。
事業譲渡の目的、主な特徴とは。専門家の知識が欠かせない理由|税理士法人チェスター
2.事業承継の手順

経営者から後継者へ経営権を引き継ぐ事業承継は、誰を後継者とするかによって3種類に分類できます。一般的な進め方とともに見ていきましょう。
2-1.事業承継の種類
事業承継は以下の通り3種類に分類でき、それぞれ後継者に誰を選ぶかが異なります。
- 親族内承継:子どもや孫など親族
- 社内承継:役員や従業員など社内の人材
- 第三者承継:会社を買収したい企業や個人など第三者
親族内承継は関係者の納得を得やすい形態ですが、子どもや孫がいなければ実施できません。子どもや孫がいても自分の仕事があり、事業承継を希望しないケースもあるでしょう。
事業や社風についてよく理解している役員や従業員への社内承継では、企業理念といった会社の核となる考え方も伝えやすいはずです。ただし、後継者が必要な資金を工面できず難航するケースもあります。
第三者承継は、親族内承継も社内承継も難しい場合に検討する企業が多い方法です。
事業承継の種類やポイントについては、以下もご覧ください。
事業承継に必要な準備や引き継ぎ内容は?親族内承継、M&Aの違い|税理士法人チェスター
2-2.事業承継の進め方
後継者へ会社を引き継ぐ際には、以下の手順で進めるのが一般的です。
- 会社の資産や負債などの現状把握
- 後継者候補の選定
- 後継者への教育
- 事業計画書の作成
- 取引先や金融機関など関係者への説明
- 経営改善
- 経営権の移転といった手続き
教育に必要な期間を含めると、事業承継が全て済むまでに10年ほどかかるケースもあります。スムーズな承継には早めの準備が欠かせません。
事業承継時に考慮すべき事業承継対策について解説している以下も、ぜひご覧ください。
企業オーナーの事業承継対策について専門の税理士が徹底解説|税理士法人チェスター
事業承継における節税対策については、以下もご覧ください。
参考:相続税の節税をしよう! 事業承継対策を専門の税理士が分かりやすく解説
3.事業承継のメリットと注意点

事業承継により会社を後継者へ引き継ぐと、経営者の引退後も会社を存続させられます。ただし次の経営者となる後継者を育成する手間がかかる点に注意しましょう。
手掛けている事業によっては、10年以上の長い期間をかけて育成しなければいけない可能性もあります。
3-1.会社の存続が可能
経営者が後継者へ会社を引き継がなければ、会社は廃業しなければいけません。長年かけて築き上げてきた技術やノウハウが失われるだけでなく、取引先や顧客との関係性もなくなってしまいます。
事業承継を行えば後継者が会社の資産を引き継ぎ、会社は存続可能です。今ある資産を生かし、経営者となった後継者がさらに会社を成長させる未来も期待できます。
工場の機械類などの設備やオフィスの備品など、今あるものをそのまま活用できるため、無駄にすることがないのも特徴です。会社が存続を続けることで、事業を通した地域への社会貢献にもつながります。
3-2.従業員の雇用を守れる
従業員の仕事を残せるのも事業承継のメリットです。会社を廃業すると、今働いている従業員の仕事はなくなります。
生活を維持するため再就職を目指すことになりますが、場合によっては再就職が難しいケースもあるでしょう。年齢によっては、そのまま仕事が見つからない可能性もあります。
廃業せざるを得ないが、これまで一緒に働いてきた従業員の仕事がなくなってしまうのが心苦しいという経営者もいるでしょう。事業承継を行えば、従業員はこれまでと同じく働き続けられます。
従業員のために今後も働き続けられる環境を整えた上で引退できる方法です。
参考:後継者不足を理由に廃業はもったいない。M&A検討で可能性は広がる
3-3.後継者の育成が必要
事業承継を行うと経営者は引退し、後継者がその仕事を引き継ぎます。経営者の引退までに、後継者が会社経営を担えるだけの能力を身に付けられるよう、育成しなければいけません。
後継者の育成にかかる期間は、事業内容や後継者の能力によって異なります。日々の業務フローを伝えるだけであれば数カ月で済むかもしれませんが、会社経営の手腕を身に付けるには10年以上かかるケースも珍しくありません。
また後継者の能力が十分であっても、周りの承認を得られなければ、事業承継はスムーズに進まなくなってしまいます。育成を進めつつ、取引先や役員などに後継者として認めてもらえるよう、機会があるごとに経営者に同行させることも必要です。
長い期間をかけて取り組まなければならず、手間に感じる可能性もあるでしょう。
参考:後継者育成にかかる期間や必要な準備は?社内、社外の教育方法も紹介
4.事業譲渡の手順

事業譲渡は引き継ぐ事業の範囲に応じて、2種類に分類が可能です。それぞれ必要な手続きが異なる点にも注意しつつ、手順も紹介します。
4-1.事業譲渡の種類
事業譲渡には、事業の全部を売却する『全部譲渡』と、一部のみを売却する『一部譲渡』の2種類があります。会社が保有している事業を売却するかどうかは、経営に関する重要な事項のため、基本的には株主総会の承認を受けなければいけません。
全部譲渡では、買い手が売り手の株式を9割以上保有している場合を除き、株主総会の特別決議での承認が必要です。一方、一部譲渡においては以下の条件を満たした場合に、株主総会の特別決議の承認を得なければいけません。
- 重要な事業であること
- 事業譲渡する資産が売り手企業の総資産の1/5を超えていること
4-2.事業譲渡の進め方
自社の現状把握は、事業譲渡を実施する場合にも欠かせない手順です。まずは資産や負債を正しく把握し、会社の強み・弱みを確認します。
- 会社の資産や負債の現状把握
- 取締役会の承認
- 買い手とのマッチング
- 基本合意書の締結
- 買い手が実施する売り手の調査であるデューデリジェンス
- 事業譲渡契約書(最終契約書)の締結
- 株主総会の特別決議で承認を得る
- 資産や契約ごとの引き継ぎ
事業譲渡を実施する上で、買い手とのマッチングが欠かせません。仲介会社を利用してもよいですが、マッチングプラットフォームなら比較的安価に利用が可能です。
また実際に引き継ぐ際には、資産や契約ごとに手続きを行わなければいけません。例えば従業員も買い手へ移籍するなら、買い手は雇用契約を個別に結び直します。
M&A仲介サイトについての詳細は、以下もご覧ください。
M&A仲介サイトで小規模な事業の売買も可能。六つのサイトを紹介|税理士法人チェスター
5.事業譲渡のメリットと注意点

会社が保有する事業を売却する事業譲渡では、会社の独立性はそのままに事業のみを切り離せます。会社経営には携わり続けたいけれど不採算事業を整理したいという場合や、売却益を得たいという場合に役立つ手法です。
ただし手続きに時間がかかる点や、税金を考慮しなければいけない点に注意しましょう。
5-1.譲渡する事業を選べる
事業譲渡では、選んだ事業のみを売却できます。利益につながりやすい主要な事業のみを残し、不採算事業を売却可能です。不採算事業がなくなることで、会社の持つさまざまな資産をメイン事業に集中させられます。
例えば事業譲渡で獲得した利益や元々ある資金や人材などです。多くの資金と人材を集中的に投入することで、経営状況の改善や業績の向上などを目指せるでしょう。
また今ある事業を売却し、新しい事業に挑戦したいと考えている場合にも向いています。事業売却で得た資金を元手にすれば、新しい事業を最初から大きく展開できるかもしれません。会社をより大きく成長させるきっかけになる可能性もあります。
5-2.売却益が得られる
買い手へ事業を売却すると対価を得られます。得られる対価の目安は、資産の現在価値に売却後数年間で得られると考えられる価値を足した金額です。
まとまった利益は今後の事業資金や、今ある負債の返済に充てられます。会社の経営状況を改善する上で役に立つでしょう。
より多くの売却益を得るには、自社の事業との相乗効果を期待できる買い手へ売却するのがおすすめです。
事業譲渡の売却価格は、算出した事業の価値を元に交渉することで決まります。より大きな価値を見出す買い手に売却することで、高額な売却益を得られるかもしれません。
5-3.手続きに時間・税金がかかる
選んだ事業のみを売却できるのは事業譲渡のメリットですが、手続きが増えて煩雑になり、時間がかかるのはデメリットです。事業譲渡では引き継ぐ資産を選べる性質上、個別に契約や引き継ぎの手続きをしなければいけません。
例えば不動産を引き継ぐには変更登記が必要であり、従業員の引き継ぎには従業員の意向を確認した上で個別に買い手との契約に向けた調整を進める必要があります。
また、法人税や消費税などの税金を納める必要がある点にも注意しましょう。法人税は課税所得が多いほど税額が高くなるため、事業譲渡によって税額が跳ね上がる可能性があります。
消費税を負担するのは買い手ですが、納税義務は売り手にあるため、忘れず手続きしましょう。
税金の計算は複雑な部分もあり、把握が難しいと感じる人もいるでしょう。M&Aの実績が豊富なチェスターなら、事業承継についての相談とともに税金についてもサポートを受けられます。
事業承継・相続対策に特化した売主オーナー様目線のM&A支援サービス|事業承継M&Aならチェスター
6.事業承継と事業譲渡のどちらを選ぶべき?
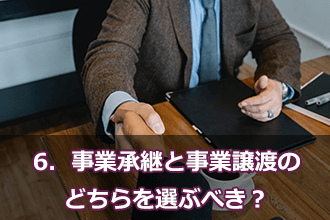
それぞれの特徴を踏まえた上で、事業承継と事業譲渡はどちらを選ぶとよいのか確認しましょう。自社の状況に合う方法を選べるよう解説します。
6-1.会社を存続させるなら事業承継
今後も会社を存続させるには、事業承継を行いましょう。事業承継をすると後継者が会社を引き継ぐため、経営者が引退しても会社はなくなりません。
従業員の雇用を守りやすい点もメリットです。経営者の下で技術や知識を身に付け長年働き続けてきた従業員を、引退後も守れる方法といえます。
また取引先からの理解が得やすいため、経営者の交代後も関係性がスムーズに引き継がれやすい方法です。
6-2.赤字なら事業譲渡
会社の経営が赤字に陥っているなら、事業譲渡を選ぶとよいでしょう。事業の売却によって会社が利益を得られる可能性があるためです。獲得した利益を使い債務を返済できます。
また買い手も事業譲渡であれば、債務を引き継がずに必要な事業のみを買収可能です。売り手にとっても買い手にとってもメリットのある手法といえます。
7.事業承継か事業譲渡かは自社に合わせて選ぶ
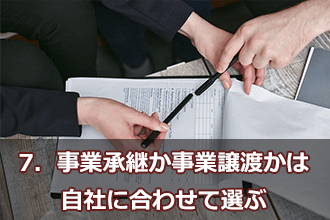
事業承継・事業譲渡ともに、実施すると税金が課されるため、税額の計算も必要です。税理士法人チェスターでは、相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。