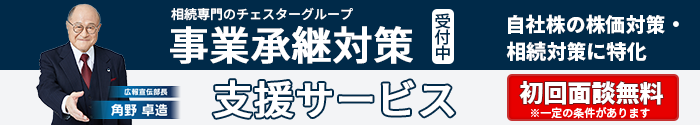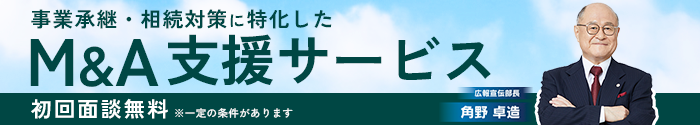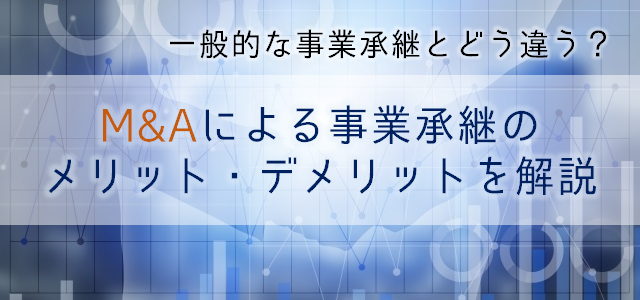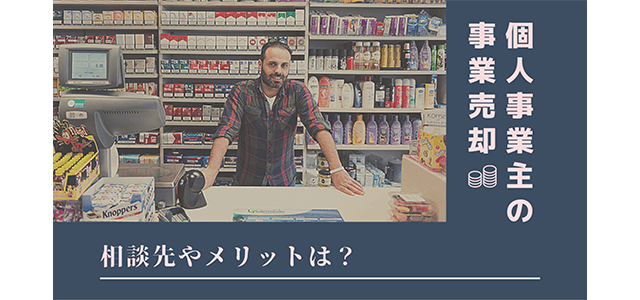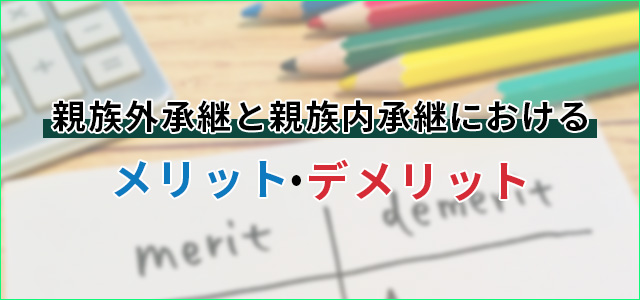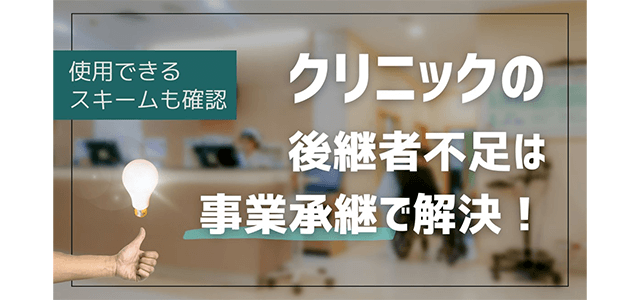会社の跡継ぎは誰が最適?後継者候補の選び方と育成方法
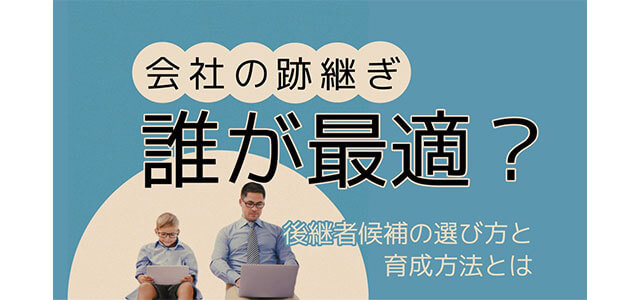
会社の次世代を担う跡継ぎの担い手は、かつては経営者の子どもでした。しかし近年の傾向では、従業員や第三者が跡を継ぐケースも増えています。事業承継のスケジュールに加え、会社の跡継ぎに求められるものや、教育の仕方について見ていきましょう。
目次 [閉じる]
1.経営者を悩ませる「跡継ぎがいない」問題
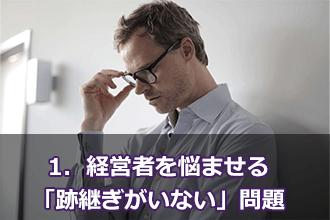
跡継ぎがいない中小企業は多く、問題を先延ばしにしているケースも少なくありません。その結果、黒字のまま廃業を余儀なくされる会社もあります。従業員や取引先にも影響するため、できるだけ早い対策が必要です。
1-1.跡継ぎとは
会社の跡継ぎ(後継ぎ)は、後継者や後継者候補を指します。会社の保有する有形無形のあらゆる資産を引き継ぐ人です。そのため設備やノウハウはもちろん、会社の理念も承継します。
しかし後継者不足が深刻化している昨今では、経営者が引退を考えているにもかかわらず、後継者がいないケースも多くあります。
子どもがいても必ず跡継ぎになるとは限らず、優秀な従業員に引き継がせたくても雇用できるとは限りません。引退はまだ先のことと考えて対策をしなかった結果、跡継ぎ不在のまま引退のタイミングを迎えるケースもあります。
1-2.事業承継問題の放置による影響
中小企業庁が発表した『中小企業・小規模事業者における M&Aの現状と課題』によると、2025年までに70歳を超える中小企業経営者は約245万人おり、そのうち約半数の127万人は後継者が決まっていないそうです。
このまま約127万人の経営者が事業承継問題を放置していると、多くの中小企業が廃業する結果になります。会社がなくなれば、働いていた従業員は失業し、価値が生み出されなくなります。
約650万人の雇用と22兆円ほどのGDPが失われかねない事態です。廃業の影響は取引先にも及びます。取引量によっては、自社の廃業に伴い倒産に追い込まれる取引先もあるかもしれません。
また後継者不在による廃業のリスクがある中では、会社の将来を考えた戦略を立てにくくなり、事業が衰退していく可能性もあります。
参考:中小企業・小規模事業者における M&Aの現状と課題|中小企業庁
後継者不在の解決策については、以下もご覧ください。
後継者不足を理由に廃業はもったいない。M&A検討で可能性は広がる|税理士法人チェスター
2.今から考えておきたい事業承継

事業承継には時間がかかります。そのため経営者の引退間近になって動き始めても、希望をかなえる形での事業承継はできないかもしれません。相続対策のためにも、早めの準備がポイントといえます。
2-1.事業承継のスケジュール
会社を後継者へ引き継ぐには、すべての工程を合わせると『5~10年』はかかるといわれています。株式の相続や贈与・M&Aの手続きだけでも半年~1年はかかり、後継者の教育やその後の統合にはさらに時間が必要です。
必要な期間は事業内容や後継者のこれまでの経験によっても異なるものの、後継者が見つかったからといってすぐにできるものではありません。後継者の教育が不十分であれば、その後の経営に影響が出るでしょう。
統合に不備があれば、他の役員や従業員が離れていってしまい、組織として機能しない事態も考えられます。そのため余裕を持ったスケジュールによる事業承継がポイントです。
事業承継の準備については、以下もご覧ください。
事業承継に必須のスケジュール作成。いつ、どんなことを実施するのか|税理士法人チェスター
2-2.相続争いへの対策
子どもへ事業承継する場合には、相続争いにも注意が必要です。後継者となる相続人に事業に関係する資産を引き継がせると、他の相続人が最低限引き継げる『遺留分』を侵害する可能性があります。
遺言書で引き継ぐ資産を指定していても、遺留分侵害請求をされた場合は応じなければいけません。その結果、後継者以外の相続人が株式を保有する事態が起こり得ます。
保有割合によっては、事業に直接関わらない相続人が、経営に介入するケースもあるでしょう。このような事態に陥らないよう対策するためにも時間が必要です。
遺留分侵害額請求については、以下もご覧ください。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ|税理士法人チェスター
3.誰を後継者に選ぶか

事業承継を考え始めたら、まずは後継者にする人を選ばなければいけません。後継者の選択肢は、子どもをはじめとした親族か親族以外に分けられます。後継者ごとに異なる事業承継の仕方も見ていきましょう。
3-1.親族内での承継
子どもや、おい・めいなどの親族を後継者とする事業承継を、『親族内承継』といいます。かつては、子どもが親の会社を引き継ぐのが当たり前とされていました。
しかし昨今は、必ずしも親族内承継が行われるとは限りません。後継者候補の親族は既に自分で選んだ仕事をしており、事業承継を希望しないケースもあります。できるだけ早い段階で事業承継について伝え、意思を確認しましょう。
親族内承継の場合、『株式売買』『相続』『生前贈与』のいずれかの方法で承継を実施します。どの方法にもメリット・デメリットがあるため、状況に合わせた選択が必要です。
親族内承継については、以下もご覧ください。
事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方|税理士法人チェスター
3-2.親族以外への承継
親族以外へ事業承継する親族外承継が増えています。子どもが引き継ぎを希望しない場合、自社の事業についてよく知っている『従業員』に承継してもらいたいと考える経営者は大勢います。
従業員へ事業承継する場合、『経営権の譲渡』『株式の贈与』『株式譲渡』のいずれかで実施されるでしょう。どの方法でも後継者となる従業員の負担が発生するため、あらかじめ役員へ選任し、報酬や賞与によって資金を準備します。
会社の外部の『第三者』へM&Aによって事業承継するケースも増加中です。社内に後継者候補となる従業員がいない場合でも事業承継できます。M&Aによる事業承継で代表的な手法は『株式譲渡』や『事業譲渡』です。
親族内承継と親族外承継について詳しく知るには、以下もご覧ください。
親族外承継と親族内承継におけるメリット・デメリット|税理士法人チェスター
4.後継者に求められること

会社を引き継ぐ後継者には、従業員として働くのとは異なるスキルが求められます。従業員から協力してもらえるよう、信頼を得る必要もあるでしょう。事業承継時には、スキルと信頼を獲得するための期間も考慮しなければいけません。
4-1.経営に必要なスキル
会社を経営するために必要なスキルは多岐にわたります。すべてのスキルの基礎となるのが論理的思考です。物事を論理的に考えられれば、会社が発展していくために必要な経営戦略や事業計画を立案するのに役立つでしょう。
加えて、自社の強みや弱みについて詳しく知ることも重要です。現状を正しく把握できれば、活用できる資源や解決しておくべきポイントを押さえ、効果的なかじ取りができます。
同時に経営を引き継いでいく覚悟も求められます。会社や経営に関する知識・スキルを身につける中で、会社の今後を担う立場である自覚を促していきましょう。
4-2.従業員からの信頼
スキルだけでなく、信頼もポイントです。どれだけ優秀な人物であっても、従業員から信頼されなければ、経営者として会社を引き継ぐのは難しいでしょう。
信頼を得るためには、良好な人間関係を築ける人物でなければいけません。ただしそれだけでは不十分で、必要なタイミングでは交渉力も求められる上、全体をまとめ目的に導くリーダーシップも必要です。
経営者に必要な人間性を備えることで、従業員の信頼も得られるでしょう。
会社を継ぐための準備については、以下もご覧ください。
親の会社を継ぐメリットとデメリットを解説。必要な準備や相続対策も|税理士法人チェスター
5.後継者の育て方

後継者が必要なスキルを身につけるには、社内外でさまざまな経験をしてもらうことが有効です。会社の全体像を把握するために社内の各部門をローテーションしたり、業界外のことを知り経営に生かすために外部の研修に参加したりします。
引き継ぎ期間中に計画的に実施しましょう。
5-1.社内での育成方法
社内で後継者を育成するには、まず各部門の仕事に触れる必要があります。会社として事業を進めるのに必要な業務の経験が、今後の経営判断に役立つはずです。
加えて役職を与え、経営へ参画させましょう。意思決定や外部との交渉を段階的に任せていくことで、経営者としての責任感を育みます。内外に対して後継者であると示すことにもつながるでしょう。
経営理念や経営ノウハウなど、経営者だからこそ知っていることも伝えなければいけません。業界や市場の動向・今後の展望なども、経営者から後継者へ直接指導します。
5-2.社外での育成方法
広い知見を持って経営に携われるようにするには、社外での育成も大切です。子会社や同業他社で勤務することはもちろん、業界外の情報や人脈を得られるセミナーや研修会などへの参加も役立ちます。
商工会議所や金融機関・大学などが開いているセミナーを、積極的に活用するとよいでしょう。経営について体系的に学ぶ機会や、異業種について知り新しい視点を自社へ取り込むきっかけになるかもしれません。
参考:後継者育成にかかる期間や必要な準備は?社内、社外の教育方法も紹介
6.後継者問題が解決しない場合の選択
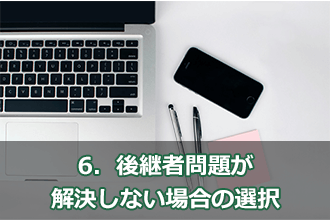
跡継ぎがおらず後継者問題が解決しない場合には、廃業して会社を消滅させるか、M&Aで売却する方法が考えられます。それぞれどのような方法なのか見ていきましょう。
6-1.廃業する
廃業すると会社が消滅します。これまで築き上げてきた技術やノウハウはもちろん、取引先との関係性も消えてなくなってしまいます。従業員も解雇しなければいけません。地域社会に対する影響が出ることも考えられます。
保有する建物や機械などの資産を売却すれば利益を得られる可能性もありますが、それほど高額な値段はつきません。場合によっては処分費用がかかる場合もあるでしょう。
また、経営者が連帯保証人になっている負債があるなら、廃業後も返済を続ける必要があります。跡継ぎについての心配はなくなりますが、手間もコストもかかる方法です。
6-2.M&Aによる事業承継という選択も
跡継ぎがいない場合には、株式譲渡などM&Aによる事業承継も検討するとよいでしょう。買い手に会社そのものや事業を売却することで、事業承継する方法です。希望の条件に合う買い手を見つけられれば、会社や事業を存続させられます。
取引をスムーズに行うには、仲介会社や弁護士・税理士などの専門家のサポートが必要です。サポートを受けるための費用や、受け取った対価に対する税金など、負担しなければいけないコストがある点に注意しましょう。
7.M&Aによる事業承継のメリット

M&Aを行うと事業承継先の選択肢が増えるほかに、事業の成長や資金の面で事業にプラスに働く可能性も考えられます。どのようなメリットがあるのでしょうか?
7-1.廃業の回避・承継先の選択肢が増える
経営者に子どもがおらず、社内にも後継者候補となる従業員がいなくても、M&Aを実施すれば廃業せずに済みます。会社を売却することで買い手に引き継げるため、従業員の雇用を守れるのもメリットです。
子どもや従業員への事業承継では、跡継ぎの選択肢が少なく経営者に適した人材がいない場合も考えられます。M&Aにより売却すれば、より幅広い選択肢の中から、自社を売却するのに向いている法人や個人を選べるでしょう。
自社の社風に合うか、自社の持つ技術との相乗効果を期待できるかなど、複数の面で買い手を比較するのもポイントです。
7-2.事業に新しい価値観を導入できる
M&Aによって新しい経営者がやってくると、業績アップに向けてそれまでとは違った手法に取り組む可能性もあります。新しい考え方や仕事の進め方を導入することで、従業員のスキルアップにつながるケースもあるでしょう。
自社の持つ技術に買い手の持つノウハウや販売網などが合わさり、これまで考えられなかったスピードでの成長も期待できます。
7-3.まとまった資金が得られる
会社や事業を売却することで、まとまった資金を得られる可能性があるのもメリットです。経営者が引退した後の暮らしを支える退職金代わりに利用できます。
また、会社に負債がある場合でも、M&Aで獲得した対価を使って返済できるでしょう。交渉次第では、買い手が負債ごと引き継ぐ可能性もあります。資金の心配をすることなく、安心して引退できる方法といえます。
8.M&Aによる事業承継のポイント
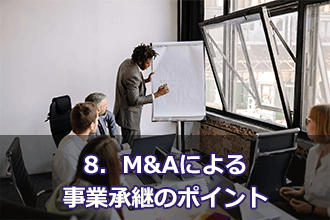
M&Aを利用した事業承継をスムーズに進めるには、計画性が重要です。早めに準備に取り組み、計画的に進めましょう。専門的な知識が必要なため、専門家への相談も欠かせません。
8-1.できるだけ早めに着手する
事業承継をM&Aで行うと決めたら、できるだけ早めに取り組みましょう。M&Aはタイミングが重要です。
同じ会社や事業でも高値で売却できる場合もあれば、そこまで高い価格がつかない場合もあります。業界の動向をよくチェックし、タイミングを逃さないよう早めに動き出しましょう。
買い手がなかなか見つからない事態も考えられます。たまたま自社の事業に興味を持つ買い手がいれば、とんとん拍子に話が進むかもしれませんが、数年かけても希望に合う買い手が現れない可能性もあります。
早めの行動は万が一の際への備えにもなります。病気や事故による経営者の死亡や重度の障害を負う事態は起こり得るものです。万が一の事態が起こってからでは、M&Aによる事業承継をしようと思っても難しいでしょう。
参考:事業承継に必須のスケジュール作成。いつ、どんなことを実施するのか
8-2.専門家の手を借りる
スムーズにM&Aを行うには、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。買い手を探すときには、仲介会社を利用すると、希望に合う買い手とマッチングしやすくなると期待できます。
多くの案件に携わっているM&Aアドバイザーのサポートを得られれば、価格や条件に関する交渉がうまく進みやすくなるかもしれません。
M&Aでは契約書も締結します。弁護士に依頼し契約書の内容について確認を受けておけば、法的に不備のない内容で契約が可能です。
税金についての相談は、M&Aの実績が豊富なチェスターを利用するとよいでしょう。買い手が実施する税務に関する調査への対策や、手法ごとに異なる税金についても相談できます。
事業承継・相続対策に特化した売主オーナー様目線のM&A支援サービス|事業承継M&Aならチェスター
9.計画的に後継者候補を育てよう

跡継ぎの不在は、日本の中小企業の多くが抱える問題です。経営者が引退するタイミングでスムーズに事業承継するためには、早めにスケジュールを把握し後継者候補を選ばなければいけません。
事業承継は後継者の教育や引き継ぎ期間を考慮すると、5~10年はかかるといわれます。経営者に求められるスキルは多岐にわたるため、早めに教育を始めるのがよいでしょう。
相続問題への対策も必要です。適正に対策しない場合、事業に携わらない相続人が権利を主張することで、事業の遂行が難しくなる可能性もあります。
後継者問題や事業承継対策の相談を専門家にするなら、税理士・会計士・弁護士といったプロフェッショナルが多数在籍し、相談対応実績が豊富な『税理士法人チェスター』がおすすめです。
税理士法人チェスターでは相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士がお客様にとって最適な方法をご提案致します。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。