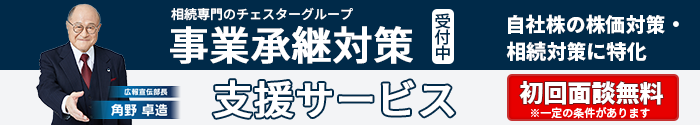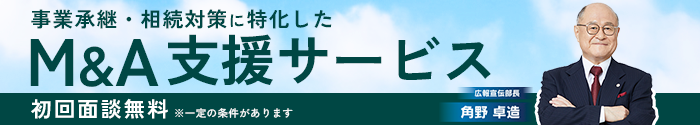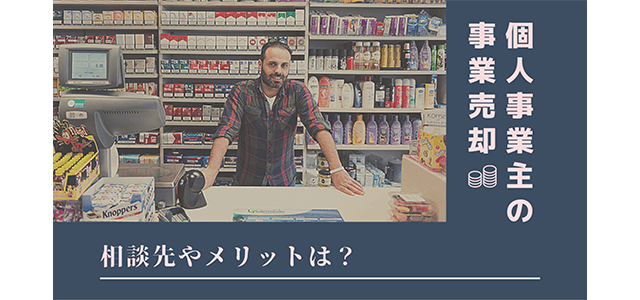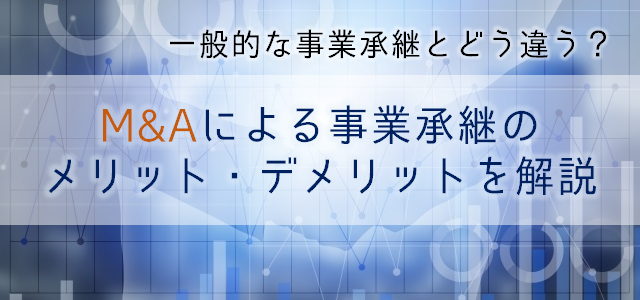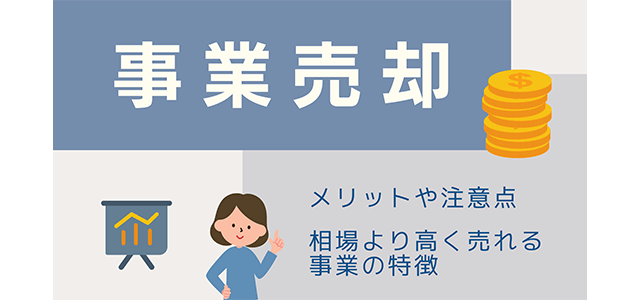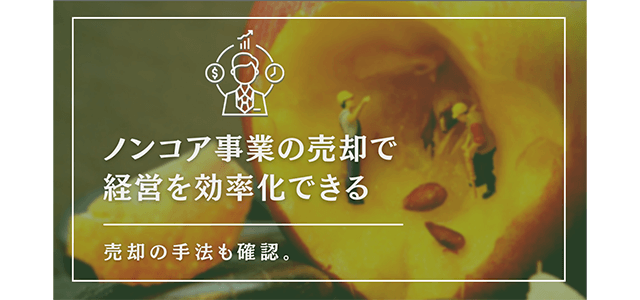飲食店がM&Aで事業承継する方法。閉店コストを節約しよう
タグ: #M&A, #M&A×業種
小規模な事業体が多い飲食店でも、M&Aによる事業承継はできるのでしょうか?M&Aの流れと併せ、代表的な手法である株式譲渡・事業譲渡の方法を見ていきましょう。飲食店でM&Aよりも一般的に行われている居抜き譲渡についても解説します。
目次 [閉じる]
1.飲食店の経営者が引退を考えたら

飲食店の経営者が引退するときには、後継者への『事業承継』をまず検討するでしょう。しかし店を継ぐ親族や従業員が見つからなければ、『廃業』を検討せざるを得ない事態です。
1-1.後継者を探す
引退を考えたとき、まずは後継者を探し始める経営者が多いでしょう。子どもをはじめとした親族や、従業員に打診する人もいるかもしれません。
かつて飲食店は、親から子どもへと引き継がれるケースが多くありました。しかし子どもには自分の仕事があり、事業承継するのが当たり前という価値観ではなくなった現在では、子どもが継ぐケースは減っています。
また飲食店は6割以上が個人事業で、7割以上は資本金1,000万円未満と、小さな事業がほとんどです。従業員に事業承継してほしいと考えていても、快諾は難しいでしょう。上記のような事情から、なかなか後継者が見つからない可能性も考えられます。
1-2.廃業する
後継者が見つからず事業承継ができなければ、経営者の引退と同時に廃業するしかありません。廃業は単に飲食店がなくなるだけではなく、コストもかかります。
大きな負担となるのが、原状回復のための『解体費用』です。1坪あたり2~5万円が相場のため、30坪の店舗であれば60~150万円かかります。
別に廃棄費用がかかるケースもあるでしょう。解約予告期間内の賃料も支払わなければいけません。
また水道光熱費やリース料の支払いはもちろん、中途解約違約金が必要な場合もあります。従業員がいて30日以上前に解雇予告をできないなら、『解雇予告手当』として30日分の平均賃金を支払います。
参考:後継者不足を理由に廃業はもったいない。M&A検討で可能性は広がる|税理士法人チェスター
2.第三者への売却という選択肢も

後継者探しは難しいけれど廃業にかかる費用負担も重いと感じているなら、第三者への売却であるM&Aが有効です。小さな飲食店であれば『スモールM&A』で売却すれば、廃業を免れます。
2-1.スモールM&Aとは
M&Aは企業の合併や買収のことです。大企業が行う取引の印象があり、自分の飲食店には無縁だと感じている経営者もいるかもしれません。
しかしM&Aの中には、小規模な事業者や個人が行うスモールM&Aもあります。そのため個人経営の小さな飲食店であっても、M&Aによる売却は可能です。
かつては敵対的買収のイメージが強かったM&Aですが、近年では成長戦略のために行う企業が増えています。それに伴いスモールM&Aの市場も活発化しており、経営者の引退や設備の老朽化を理由に売却される小さな事業が増加中です。
参考:スモールM&Aとはどんな企業が対象か。プロのサポートが必要不可欠|税理士法人チェスター
2-2.飲食店のM&A相場
飲食店をM&Aで売却するときには、価格の相場はありません。同じ飲食店であっても、業績・立地・規模・設備・従業員のスキル・知名度・人気メニューなどが違えば、価値は異なるからです。
状況によって異なる飲食店の価値を算出する方法は複数あります。中でも比較的簡単に計算できるのが『年買法』です。『事業の純資産+営業利益×3〜5年分』に当てはめて計算すれば、売却価格の目安が分かります。
参考:M&Aのバリュエーションとは。目的やタイミング、手法を解説|税理士法人チェスター
3.飲食店をM&Aで事業承継するメリット

M&Aで事業承継すると、売り手は利益を得られます。廃業するのにもコストがかかりますが、売却できれば金銭的な負担がありません。従業員の雇用を守れる点や、事業用の借入の個人保証から解放される可能性があるのもメリットです。
3-1.譲渡・売却益が獲得できる
飲食店のM&Aにより、売り手は売却益を得られます。利益は引退後の暮らしを支える退職金のように活用する選択肢もあれば、新しい事業にチャレンジする資金にすることも可能です。
廃業すればコストがかかりますが、タイミングよく引き継ぎたいという買い手が現れれば、利益を得た上で引退できます。
3-2.従業員の働く場を守れる
飲食店を廃業すれば従業員は仕事を失います。再就職に向けて転職活動をしなければならず、年齢や働き方の条件によっては、再就職が難しい場合もあるでしょう。
M&Aにより事業承継できれば飲食店は消滅しません。従業員を継続して雇用することを契約書へ盛り込めば、従業員の働く場所も守れます。
M&Aを行う上で、飲食店にとって従業員も大切な資産です。店や顧客のことをよく知っている従業員は、買い手にとっても重要な存在のため、継続して雇用することに反対するケースは少ないでしょう。
3-3.個人保証からの解放
事業資金を金融機関から借りている飲食店では、店の利益が出なくなり返済が滞った場合、オーナーの個人資産から返済を行うという個人保証を付けているケースもあります。
この場合、引退したタイミングで借入金が残っていると、オーナーは残債をまとめて返済しなければいけません。
M&Aを実施するにあたり、買い手の合意を得て個人保証も引き継げば、引退時に大きな負債を抱えずに済みます。個人保証の引き継ぎについて合意を得た場合には、必ず契約書にその旨を盛り込み、確実に手続きが実施されるようにしましょう。
また2020年4月から、個人保証を不要とする新たな信用保証制度が始まっています。一定の条件を満たしている法人であれば、事業承継時に個人保証を軽減したり負担をゼロにしたりできる制度です。
個人保証が理由でM&Aが滞っているようであれば、利用できるかどうか検討するとよいでしょう。
参考:2. 事業承継時に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の創設|中小企業庁
4.買い手のメリットは?

スモールM&Aで飲食店を売却すれば、経営者は後継者問題を解決でき、廃業にかかる費用を負担せずに済みます。飲食店の持つ有形・無形の資産を引き継げるM&Aは、買い手にもメリットがある方法です。代表的なメリットを見ていきましょう。
4-1.固定客や優秀な従業員を獲得できる
新しく飲食店を立ち上げた場合、固定客がつくまでが大変です。新しい飲食店があると気付いてもらえるまでに時間がかかる可能性もあるでしょう。
M&Aで既に営業している飲食店を買収すれば、買い手はすぐに固定客を獲得できます。認知されるまでの期間を省略でき、すぐに収益を上げられるのはメリットです。
買収した時点で既に従業員がいる点もポイントといえます。飲食店の仕事について知り、顧客についても把握している従業員を育てるには、採用にも教育にも費用と手間がかかります。この費用と手間を抑えられるのもM&Aの魅力です。
4-2.資金力や既存事業を活用できる
買い手が持つ資金の有効活用にも、M&Aが役立ちます。例えば飲食店が持つもともとの魅力をブランドとして打ち出し、複数店舗による展開も可能です。
また買い手の既存事業との相乗効果も期待できます。買い手が既に他の地域で飲食店を経営しているなら、規模の拡大に役立てられるでしょう。
食材の調達や加工ができる買い手であれば、自社で調達した材料を飲食店で利用し効率的な経営ができるかもしれません。
参考:M&Aのメリットを細かく紹介。M&Aによる相乗効果や節税効果とは|税理士法人チェスター
5.飲食店M&Aの流れ

M&Aによる事業承継を実施するなら、まずは買い手を探さなければいけません。条件の合う買い手が見つかれば、売買の手続きを経て後継者へ引き継ぎます。
5-1.買い手とのマッチング
買い手を探すには『マッチングサイト』が便利です。マッチングにはM&A仲介会社も利用できます。
ただし仲介会社は手厚いサポートを提供する性質上、報酬がコストに見合わないため、スモールM&Aを取り扱っていないケースがほとんどです。そのため小規模な飲食店であれば、マッチングサイトが向いているでしょう。
業種・売上高・希望譲渡金額など必要な情報を入力し登録すれば、すぐに使い始められる手軽さもポイントです。小さな飲食店1店舗のみでも、手軽に買い手とマッチングできます。
参考:M&A仲介サイトで小規模な事業の売買も可能。六つのサイトを紹介|税理士法人チェスター
5-2.売買の手続き
条件の合う買い手が見つかったら、売買の手続きに移ります。M&Aで飲食店を売却するときには、株式譲渡や事業譲渡など複数の手法の中から、適切なものを選ばなければいけません。
手法ごとに必要な手続きが異なり、利益に課される税率も異なります。そのため手法によっては手取り額が低くなる場合もあるでしょう。あらかじめ試算した上で、適切な手法を選ぶ必要があります。
参考:M&Aの際に行われる税金対策。株式譲渡、事業譲渡、会社分割を解説|税理士法人チェスター
5-3.後継者への引き継ぎ
選んだ手法に則って手続きを行った後は、買い手への引き継ぎを実施しましょう。飲食店の事業承継では、調理・接客・メニューなどの引き継ぎが欠かせません。全てを引き継ぐには数年かかるケースもあります。
通常業務・経営・メニュー開発というように、段階を踏んで伝えていくとよいでしょう。また引き継ぎ時には、事業承継後の経営方針についても相談しておきます。
方針に合わせて、引き継ぐ点・変化させる点をはっきりさせておくと、スムーズに引き継げるでしょう。
参考:事業承継に必要な準備や引き継ぎ内容は?親族内承継、M&Aの違い|税理士法人チェスター
5-3-1.飲食店のM&Aを成功させるポイント
飲食店のM&Aを成功させるためには、早めに取り掛かるのがポイントです。M&Aを希望したからといって、すぐに買い手が見つかるとは限りません。
買い手が見つかっても、契約までに時間がかかるケースも多々あります。予定していた時期に引退するためには、計画的に進めなくてはなりません。
そのためには情報収集も重要です。状況に合ったサポートを受けられる仲介会社やマッチングサイトを利用すると、スムーズに進めやすくなります。
ただし仲介会社やマッチングサイトの利用には手数料がかかるため、予算内で利用できるか確認した上で利用しましょう。
6.飲食店を株式譲渡で承継する方法

株式会社を立ち上げ飲食店を経営しているなら、株式譲渡でM&Aを実施できます。会社を丸ごと引き継ぐ手法のため、買い手は飲食店の経営に必要なものをまとめて獲得可能です。許認可を取得し直す必要もないため、買い手はすぐに飲食店を営業できます。
6-1.後継者にそのまま引き継げる
会社ごと飲食店を売却する株式譲渡なら、M&Aの手続きは比較的シンプルです。株式を買い手に売却し、会社の所有権を移行することで、飲食店も含め会社が保有する全ての資産・負債を承継します。
飲食店の設備はもちろん、メニューや顧客リストなど、有形無形のあらゆるものを引き継ぐ株式譲渡は、売却価格が高くなりがちです。
しかし従業員との雇用契約や設備のリース契約など、各種の契約をそのまま使えます。また許認可も取得し直す必要がありません。そのため手続きの手間を省ける手法です。
6-2.株式譲渡の流れ
株式譲渡は契約を締結しただけでは完了しません。その後『株主名義』の書き換えが必要です。名義変更は株主名簿の書き換えによって完了します。
名義の書き換えは、会社によって手順が異なります。例えば株券を発行していない会社では、株主名義の書き換えは、売り手・買い手が共同で請求しなければいけません。
そのため確実に手続きできるよう、株式譲渡契約書に、代金と引き換えに押印済みの『株主名簿名義書換請求書』を交付するという内容を記載します。
また譲渡制限株式は、『譲渡承認請求書』を会社へ提出し、取締役会もしくは株主総会の決議により承認を受けなければいけません。
参考:株式譲渡にはどんな手続きが必要?契約や税金に関する基礎知識|税理士法人チェスター
7.飲食店を事業譲渡で承継する方法

事業譲渡で飲食店を売却するときの特徴は、引き継ぐ範囲を決められる点です。必要な資産のみを選択し承継できるのは、買い手にとってメリットといえます。ただし個別の手続きが必要なため、その分手間がかかる点に要注意です。
7-1.承継する範囲を決められる
売り手の持つ事業の一部もしくは全部を売却するときには、事業譲渡を活用するとよいでしょう。例えば経営している複数の飲食店のうち、1店舗のみを売却したいという場合には、事業譲渡で手続きできます。
引き継ぐ資産や負債を一つずつ決められるため、買い手にとっては不要なものを引き継がずに済む点がメリットです。反面、許認可を引き継げないのはデメリットといえます。
飲食店を経営するには飲食店営業許可が必要です。事業譲渡の場合、買い手は許可を取り直さなければいけません。手続きにかかる期間も考慮した上で、M&Aのスケジュールを組む必要があります。
7-2.事業譲渡の流れ
売り手・買い手で条件を決定し合意したら、事業譲渡契約を締結します。契約書に記載する内容は法律で決められていませんが、誰が見ても明らかなように譲渡財産の内容まで細かく記載するとよいでしょう。
契約の締結後は、譲渡対象の資産を買い手へ引き渡したり、契約を買い手名義へ変更したり、取引先とスムーズなやり取りができるよう取り決めたりします。
契約書で取り決めた手続きが完了すると、買い手から売り手へ対価が支払われる流れです。
参考:事業譲渡の目的、主な特徴とは。専門家の知識が欠かせない理由|税理士法人チェスター
8.飲食店を居抜き譲渡する方法

M&Aよりもよく知られているのが『居抜き譲渡』です。通常飲食店を廃業するときには、設備などを処分し賃貸を開始したときの状態に戻す原状回復をしてから明け渡します。
しかし居抜き譲渡であれば、原状回復の手間と費用がかからない上、対価も受け取れるでしょう。
8-1.内装や設備を残して売却すること
内装や設備を原状回復することなく、そのまま引き渡すことを『居抜き』といいます。所有している店舗であれば、土地や建物と一緒に設備や内装なども売却もしくは賃貸する方法です。
居抜き譲渡は賃貸物件でも可能です。賃貸の場合は貸主の承諾を得た上で、次の借主へ設備や内装を譲渡し、退去します。
居抜き譲渡であれば設備をそのままにしておけるため、原状回復費用の節約が可能です。また店舗資産の現金化も期待できます。
8-2.いくらで売れるのか
居抜き譲渡の対価は店舗ごとに異なります。価格を左右するのは『立地』『店舗面積』『業態』などの条件です。同じ店舗面積でも、人通りの多い道に面している店舗の方が、裏通りの店舗よりも高い値段で譲渡できます。
ただしM&Aで考慮されるブランドや顧客・従業員などは価格に反映されません。そのためM&Aと比較すると売却価格は低く抑えられがちですが、小規模な事業者の中では、M&Aよりよく知られています。
8-3.居抜き譲渡の流れ
賃貸の店舗を居抜き譲渡するなら、貸主の承諾を得ておくと安心です。貸主との賃貸借契約で、居抜き譲渡が禁止されているにもかかわらず無許可で行うと、居抜き譲渡が成立しても賃貸借契約がスムーズに進まない可能性があります。
また居抜き譲渡を行う際には契約書の作成も必要です。内容については定められていませんが、以下を含めておくとよいでしょう。
- 引き渡し日
- 引き渡し物品
- 引き渡し状態
- 引き渡し後の取り決め
- トラブル発生時の解決方法
居抜き譲渡は専門の仲介業者を利用する方法もあります。サポートを受けながら居抜き譲渡できるため、個人で行うよりトラブルを避けやすいでしょう。
9.閉店を決める前に売却を検討しよう
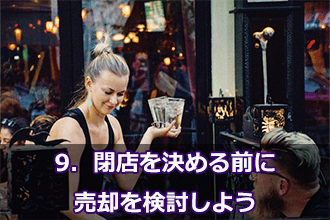
子どもや従業員への事業承継が難しいからといって、すぐに閉店する必要はありません。まずはM&Aによる第三者への売却を検討しましょう。売り手は後継者問題を解決でき、買い手はすぐに利益を得られる店舗を獲得できます。
M&Aを行うにあたり、まずは手法を選びましょう。会社を丸ごと売却する株式譲渡や、事業の一部もしくは全部を選び売却する事業譲渡が代表的です。
飲食店では居抜き譲渡もよく行われます。賃貸の店舗であっても、退去時に原状回復費用が不要のため、廃業にかかるコストを抑えられる方法です。
ただしM&Aは、法務や財務など幅広い領域にまたがる知識が必要なため、信頼できる専門家に相談しましょう。
税金対策をはじめ、後継者問題やM&A全般についての相談対応実績が豊富で、税理士・会計士・弁護士が多数在籍する『税理士法人チェスター』にご相談ください。
税理士法人チェスターでは相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士がお客様にとって最適な方法をご提案を致します。
事業承継に関する基礎知識をチェックするには、以下もご覧ください。
事業承継とは|経営者が知っておきたい事業承継の基礎知識 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。