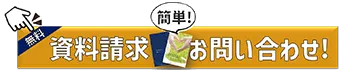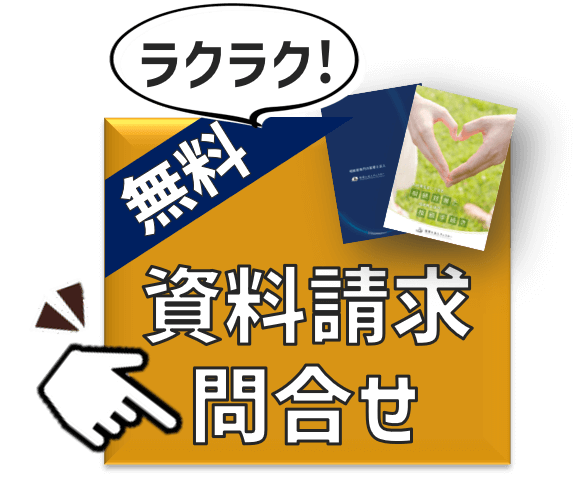親の会社を継ぐべき?メリット・デメリットや相続対策を解説

親が会社を経営している場合、昔であれば、子が会社を継ぐことは当たり前のことでした。今では、そういった意識は薄れています。それでも、経営者の子であれば、親の会社を継ぐか、継がないか、一度ならずと真剣に考えるでしょうし、悩んだり、迷ったりすることも多いはずです。
会社を継ぐということは、単に事業を引き継ぐというだけではなく、大きな責任も負うことになるため、簡単に決められないのも当然です。
そこで本記事では、親の会社を継ぐかどうかで悩んでいる人を対象に、そのメリット・デメリットや求められる能力、円滑に引き継ぐためのポイント、注意すべき点など、さまざまな角度から親の会社の引き継ぎについて検討します。
この記事の目次 [表示]
1.どれくらいの人が親の会社を継いでいる?
現在では、どれくらいの人が親の会社を継いでいるのでしょうか?
1-1.中小企業の事業承継の現状
はじめに、中小企業の後継者の決定状況を確認してみましょう。下図をご覧ください。
(出典)中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」10ページに掲載の「(3)中小企業における事業承継の現状①後継者確保の困難化」より)
中小企業庁が作成した「事業承継ガイドライン(第3版)」によると、調査対象となった中小企業のうち、約半数が廃業を予定しています。
残りの半数のうち、つまり廃業せずに事業を承継したいという意向がある企業のうち、約22%が後継者未定となっています。
また、約半数を占める廃業を考えている企業のうち、約3割は後継者難による廃業となっています。
(出典)中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」10ページに掲載の「(3)中小企業における事業承継の現状①後継者確保の困難化」より)
1-2.親族内承継の状況
次に、事業承継を終えた会社のうち、親族内で会社が継がれた割合がどれだけあるのかを確認してみます。
(出典)中小企業庁『2023年版中小企業白書』
(第2部第2章128ページに掲載の「近年事業承継をした経営者の就任経緯」より)
『2023年版中小企業白書』に掲載の「近年事業承継をした経営者の就任経緯」データによると、「親族内承継」「従業員承継」「社外への引き継ぎ」(M&A等)のうち、親族内承継の割合は2021年までトップであり、横ばいで推移してきましたが2022年には急減しています。反面、「従業員承継」は増加して、「親族内承継」とほぼ同じ割合になりました。
また、「社外への引き継ぎ」(M&A等)も、年々増加傾向にあることがわかります。
この流れからも、親の会社を子が引き継ぐことは、もはや「当たり前」ではなくなっているといえます。
2.親の会社を継ぐメリット
次に、親の会社を継ぐメリットについて確認します。親の会社を継ぐメリットには、さまざまなものがあり、人によっても異なりますが、代表的なものは以下の5つでしょう。
- 自分らしい働き方ができる
- リストラや定年退職がない
- 多くの資産を受け継げる
- 従業員や取引先・金融機関などから受け入れられやすい
- 売却によって多額の利益が得られる可能性がある
2-1.自分らしい働き方ができる
親の会社を引き継ぎ、経営者の立場となれば、雇用される従業員と違って、働き方などの自由度が格段に高くなります。
従業員のように決まった勤務時間もなく、仕事のスケジュール管理などもすべて自分で決められます。また、事業展開の方向性や社内の組織変更も、すべて自分の考えた通りにおこなうことができます。
2-2.配置転換も定年退職がない
従業員であれば、会社から命令されれば、配置転換などもあり、必ず自分が望んだ内容の仕事ができるとは限りません。場合によっては、業績悪化によってリストラされることもあります。また、どれだけ技術やモチベーションが高くても、定年を迎えれば退職せざるを得ません。
しかし、親の会社を継いで経営者となれば、どんな業務をするかは自分で決められます。もちろん、リストラや定年退職もありません。本人のやる気次第でいつまでも好きなだけ働くことができます。
2-3.多くの経営資源を受け継げる
親の会社を引き継げば、会社が持つ経営資源、つまり、資産や技術、また人材、ブランドなどを用いて事業活動ができます。
一方、自分で起業した場合は、自己資金を用意し、資産も信用もすべてゼロから築き上げなければなりません。そのため、一般的には失敗のリスクも高くなります。すでに軌道に乗っている親の会社を引き継げば、順調な経営を維持していくことは、比較的やりやすいでしょう。
2-4.従業員や取引先、金融機関などから受け入れられやすい
社員や外部人材など、前経営者の親族ではない人が経営者として登用されると、社内外から「どうしてあの人なのか」と、正統性に疑問が生じやすくなります。社内登用の場合、会社に派閥のようなものがあれば、派閥争いのようなものが生じかねません。また、外部登用だと、信用を得るまでに時間がかかったり、反発を生みやすくなったりすることがあります。
一方、多くの中小企業では、昔から親族内承継が事業承継の第一選択肢として選ばれています。そのため、子が会社を継ぐ場合は、従業員や取引先、金融機関などから正統な後継者として受け入れられやすく、承継がスムーズに進みます。
2-5.売却によって多額の利益が得られる可能性がある
親から会社を引き継いだ後、必ずしも、一生経営を続けなければならないわけではありません。状況によっては将来売却(M&Aによる譲渡)をすることもできます。M&Aが一般化している昨今、買い手も以前よりは見つかりやすくなっています。
会社の業績が良かったり、優れた技術やブランドなどの無形資産を保有したりしている場合は、多額の譲渡利益も期待できます。
その利益によって、受け継いだ会社とは別のビジネスを始めることもできますし、リタイアを選択することもできます。
3.親の会社を継ぐデメリット
一方、親の会社を継ぐことにはデメリットもあります。デメリットにもさまざまなものがありますが、特に知っておくべきなのが以下の3つです。
- 経営者としての重責を背負うことになる
- 保証債務があれば、それも引き継ぐことが一般的
- 従業員との関係に悩むことがある
3-1.経営者としての重責を背負うことになる
経営者になれば、会社に対する責任をすべて背負うことになります。従業員はもちろん、その家族の生活も、経営者の手腕にかかっているのですから、責任は重大です。そして、その責任をだれにも転嫁できません。
経営者は、会社にかかわることは、すべて自分で決断して自分で責任を負わなければならないのです。
3-2.保証債務があれば、それも引き継ぐことが一般的
会社が金融機関等から融資を受ける際、経営者個人は連帯保証人となり、保証債務を負うことが普通です。
このような債務がある状況で会社を引き継ぐと、承継した経営者にも保証債務をそのまま引き継ぐことが、金融機関から求められます。
会社の債務に連帯保証をしていれば、万が一、会社が経営破綻した場合、経営者の個人資産も差し押さえられてしまうことを、よく理解しておかなければなりません。
なお、この保証債務の引き継ぎ問題は、かねてより中小企業の円滑な事業承継を妨げる一因であると指摘されていました。
そこで、中小企業庁では、「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」を実施しており、「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の制定などが実施されています。
現在では、事業承継時の金融機関との話し合いによっては、親の会社の保証債務を後継者の子が引き継がなくてもよいケースもあります。ただし、保証債務も承継することが一般的ではあるのは事実です。
3-3.従業員との関係に悩むことがある
会社経営の成功には、従業員との良好な関係が前提になります。しかし、こうした関係を築くのは、決して簡単ではありません。
例えば、先代の古い業務のやり方を変えて、IT化により、効率的な業務遂行をするなどの改革をしようとすれば、従業員からの反発が起こるかもしれません。
また、自分よりも年上の古参従業員との間で、感情的な対立が起こることも考えられます。
社内での対立や反発を乗り越えて人心掌握をする苦労が、経営者にはつきものなのです。後継者がそういったことに向いていなければ、苦労することになります。
4.親の会社を継ぐための準備
親の会社を継ぐタイミングには、一般的に以下の3つが挙げられます。
- 親が引退する時
- あらかじめ設定したタイミング
- 親が亡くなった時
4-1.親が引退する時
ひとつ目のタイミングが、親が引退する時です。親の年齢や体調などに合わせて、子が会社を引き継ぐことになります。
このケースでは、事前にある程度の準備が出来るため、余裕をもって計画的に進めれば、無理のない事業承継が可能です。
4-2.あらかじめ設定したタイミング
例えば、「子が親の会社に入社して、役員として10年働いたら事業承継する」など、親との間で事業承継の時期の約束があれば、その時期が会社を継ぐタイミングとなります。
この場合も、実務経験や年齢などから逆算して、ちょうど良い時期を設定しておけば、スムーズな承継がしやすいでしょう。
4-3.親が亡くなった時
最後は、親が亡くなった後です。人がいつ死亡するかは、事前に予測できないため、子が承継するつもりであったものの、事業承継の準備が整わないうちに、親が亡くなることもあり得ます。
すると、会社の承継と、相続の手続きなどを同時並行でおこなわなければなりません。限られた時間の中で、正しい判断・選択を行う必要があります。遺言の文書で、事業承継に対する親の考え方が明確に残されていればよいのですが、そういうものがないと、親族間でのトラブルにもなりかねません。
そうならないように、子が後継者になると決まっているのなら、事業承継の準備は早めに進めておくことが肝要です。また、万一に備えて、会社をどのように承継させたいのかを文書で残しておくことも、親には求められます。
5.親の会社を継ぐために必要な3つの能力
経営者の子だからといって、誰もが企業経営者としての資質を備えているわけではありません。経営者として会社を運営していくためには、以下のような能力が必要です。承継を考える際には、果たして自分にこのような能力があるか、また、今はなくてもそれを身に付けるための努力をすることができるかを考えることもポイントです。
- 優れた経営能力
- 卓越した実務能力
- リーダーシップ
5-1.優れた経営能力
優れた経営能力とは、将来のビジョンを持ち、それを達成するための戦略を立案・実行する能力のことです。
こうした能力の多くは、実際の経営経験を積むことで身に付けられるものであり、まだ経営をしたことがない段階では備わっていません。
そのため、親の経営をよく見て、よく聞いて学ぶとともに、例えば、セミナーや書籍から学んだり、多くの経営者に会って話を聞いたりする機会を積極的に設けることが必要です。
5-2.卓越した実務能力
親の会社を継ぐためには、その会社の仕事内容を十分に理解し、ある程度の技術も身に付けておくこと、つまり実務能力も大切です。
そのため、通常は、会社を継ぐ前に、ある程度の期間は、一社員として働き、現場感覚を身に付けておくべきです。
実務能力が得られるだけでなく、会社を継いだ後で、従業員から「現場のことも知らないくせに」といった反発を受けることなく、コミュニケーションがスムーズになるでしょう。
5-3.リーダーシップ
経営者に必要な資質としては、リーダーシップも大切です。どれだけ優れた経営計画を策定できたとしても、周囲の人から信頼を得て、働いてもらえなければ、目標を達成することはできません。
「人に働いてもらうために、働く」というのが、経営者の仕事であり、それをなしえるのが、リーダーシップです。
リーダーシップは、天賦の才能ではありませんし、社長という立場であれば自然に身につくものでもありません。やはり、リーダーとしてどう考え、なにをすべきかを、学習によって身に付けなければならないのです。
6.親の会社を継ぐ際の注意点
親の会社を継ぐにあたり、注意すべき点もいくつかあります。その中でも特に重要なのが、以下の3点です。
- 一度継いだら簡単に辞められない
- 新しいビジネスモデルを構築しなければならない
- パートナーや家族の理解が必要となる
6-1.一度継いだら簡単に辞められない
会社員という立場であれば、業務内容や職場が自分にあっていないと感じれば転職することもできますが、経営者はそういうわけにはいきません。
従業員やその家族の生活を守る責任がありますし、金融機関から融資を受けていれば、その返済の責任も負います。
良くも悪くも経営者は会社と一蓮托生の関係であることが多いだけに、「とりあえず会社を継いでみて、ダメだったら会社員に戻ろう」という考えなら、経営は止めておいた方がよいでしょう。
6-2.新しいビジネスモデルを構築しなければならない
技術革新や顧客ニーズの変化が進めば、既存のビジネスモデルでは収益をあげ続けることが難しくなります。そのため、どの企業も存続をかけて常に新しい収益の柱を作り上げる努力をしています。
環境変化の激しい現代では、1つのビジネスモデルが通用する年数も段々短くなっているだけに、常に新しいビジネスモデルを模索して、構築する努力を続けなければなりません。
6-3.パートナーや家族の理解が必要となる
経営者は従業員とは立場が違うため、365日経営者であることが求められます。また、すでに述べたように、会社の資金調達の際には、通常は連帯保証人にもなる必要があります。
こうした状況は、パートナーや家族にも少なからぬ負担をかけることになります。
したがって、親の会社を継ぐ前に、パートナーや家族に対して十分な説明をした上で理解を得ておくことは、とても大切です。
7.円滑に会社を継ぐためのポイント
親の会社を円滑に継ぐためには、以下のポイントに注意しておく必要があります。
- 会社を継ぐタイミングをあらかじめ決めておく
- 後継者教育に十分な時間をかける
- 親族や関係者の理解を得る
- 専門家や公的支援を積極的に活用する
7-1.会社を継ぐタイミングをあらかじめ決めておく
会社を継ぐのはいつが良いかですが、当然ながらいつでも良いわけではありません。
事業環境の変化が激しい場合や会社の財務状況が悪い場合のように、経営経験に基づいたシビアな経営判断が求められる時期は避けた方がよいでしょう。
また、親の年齢や健康状態なども考慮しなければなりません。もちろん、本人のモチベーションや周囲の理解なども大切です。
こうしたさまざまな状況から、会社を継ぐのに最適なタイミングをあらかじめ決めておき、それに向かって準備を進めておくことが、スムーズな事業承継のポイントです。
7-2.承継準備、後継者教育に十分な時間をかける
承継準備や後継者教育には、一般的に5~10年程度の時間がかかるといわれています。中小企業の経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを考えると、60~65歳までには後継者教育をスタートした方がよいでしょう。
後継者教育は、自社業務を通じたOJTによるものが中心となりますが、それ以外にも同業他社への出向や経営者セミナーなどの受講、他の経営者とのコネクション作りなどさまざまな方法があります。
ここで十分な知識や経験を身に付けておけば、経営者となった後でも慌てることなく正しい判断が下せるようになるでしょう。
7-3.親族や関係者の理解を得る
親の会社を継ぐのであれば、親族や関係者の理解を得ることが大切です。
特に、後継者以外の親族が株式を持っていたり役員になっていたりする場合は、事前に十分なコミュニケーションを取った上で、内諾を得ておかなければなりません。
ここは、事業承継のみならず、相続における遺産分割などとも関連するため、税理士などに相談しながら検討することが必要です。
さらに、承継が近くなった時期には、取引先や得意先、金融機関などの関係者にも事前に根回しをしておくことも大切です。
7-4.専門家や公的支援を積極的に活用する
親の会社を継ぐためには、さまざまな法的手続きが必要です。
契約書類であれば弁護士によるリーガルチェックを受けた方が良いでしょうし、株式の移転(贈与、相続または譲渡)にともなう課税関係については事前に税理士に相談しておくことが必要です。
また、事業承継にあたっては、公的な補助制度や、課税関係の特例制度などもあります。これらも、事業承継に詳しい専門家に相談して、状況に応じて活用できるとよいでしょう。
8.会社の引き継ぎと相続とは、一体で考える必要がある
「親の会社を継ぐこと」には、事業(経営)の引き継ぎと、財産の引き継ぎという2つの側面があります。
後者については、相続人(親の遺産を受け継ぐ権利を持つ人)が、後継者となる子以外にもいる場合は、慎重に検討しなければなりません。
8-1.株主と経営者の関係
株式会社の最高意思決定機関は株主総会であり、会社の所有権は株主にあります。社長(代表取締役)も含めた取締役は、あくまで株主から委任を受けて経営を執務するというのが、株式会社の建て付けになっています。
もし、株主と経営者(代表取締役)とが別の人物だとすれば、両者の経営意思が分かれた場合、株主の意思のほうが優先されます。そうなれば、経営者の考える通りの経営ができなくなり、経営は不安定化します。
そこで、経営意思の安定という観点からは、株主=経営者(代表取締役)となっている状態がもっとも安定します。
株主=経営者(代表取締役)であるとは、経営者が、最低でも株主総会議決権の過半数の株式を所有していることです。
詳しい解説は省きますが、株主総会の「特別決議」が可能になる3分の2以上の議決権を経営者が保有していれば、ベストです。
8-2.自社株式を集中して承継させれば、相続トラブルにつながりかねない
事業承継に際して、経営を安定化させるためには、株主=経営者となるように、自社株式のすべてを、後継者経営者となる子ひとりに、集中して承継させることがベストです。
株式を承継させるには、贈与、相続、または譲渡(子が買い取る)の方法がありますが、譲渡は子に多額の現金が必要であるため、贈与または相続による移転が一般的です。
つまり、事業承継には、自社株式のすべて、または大半を、後継者に集中して、贈与または相続させる必要があるということです。ここで、問題になるのが、相続人が複数いた場合の遺産分割の公平性です。
例えば、子が3人いて、長男を後継者と決めて、長男に自社株式のすべてを相続させたとします。
このとき、他の2人の子にも長男が承継した株式の価値と同じ程度の価値の財産を相続させることができれば、特に問題は生じないでしょう。
しかし、親に自社株式以外の財産が少なければ、それができません。すると、他の2人の子が不公平を感じてトラブルが生じる場合があります。
8-3.早めの相続対策がポイント
こうした事態を防ぐためには、親の生前に自社株式以外の資産を十分に用意しておくことや、生命保険を適切に活用する方法などがあります。
いずれにしても、事業承継は相続とは切り離せず、一体化して考える必要があるということです。
相続対策には時間がかかる場合もあるので、早期に、相続にくわしい税理士に相談しておくことをおすすめします。
9.会社を継ぐ際のよくある悩みと対策
親の会社を継ぐ際には、多くの人が様々なことで悩みます。記事の最後に、中でも多くの人に共通する悩みと、その対策について簡単に触れておきます。
- ベテラン社員との軋轢が生まれる
- 先代の父親と比較される
- 資金繰りのノウハウがない
9-1.ベテラン社員との軋轢が生まれる
親の会社を継いで新たな経営者となった際に、生え抜きのベテラン社員との間で軋轢が生まれることがあります。特に、社員への説明もないまま急に現れて会社を継ぐようなケースでは、こうした事態がよく起こります。
それを避けるためには、いきなり会社を継ぐよりも、従業員として入社してベテラン社員の下で働きながら積極的にコミュニケーションをとっておくとよいでしょう。経営者になった後も円滑な業務進行が可能になります。
9-2.先代の父親と比較される
会社を継いだ子が、先代の社長である父親と比較されるのはどの会社でも同じです。特に経営者になりたての段階では、経験も知識も先代に劣るのは仕方ありません。
これを解決するための、安直な近道はありません。遠回りのように見えても、今の自分に出来ることを少しずつ積み上げ、周囲の人々からの信頼を集めていくことが、唯一の方法です。
9-3.資金繰りのノウハウがない
経営者の仕事の中で、最も大切なもののひとつが会社の資金繰りです。しかし、資金繰りにもノウハウがあり、経験を積み重ねなければなかなか身につきません。
自分に知識がないのであれば、税理士や、会計にくわしいコンサルタントなどの専門家を上手に活用することをお勧めします。専門家に相談しながら経験を積むうちに、やがて少しずつノウハウも蓄積されていくはずです。
10.まとめ:決めるのは自分だが、専門家にアドバイスを求めるのもよい方法
親の会社を引き継ぐことには、メリットだけではなく、デメリットもあります。また、本人の資質に、経営者への向き不向きもあるでしょう。
かつてのように、経営者の子だから親の会社を引き継ぐことが当たり前という時代ではありません。
本人が、経営をするとはどういうことか、会社を引き継いだら、何をしなければならないのかということを十分に理解した上で、主体的な判断をすることが大切です。
そのような判断の上での引き継ぎでなければ、経営者の重責をまっとうすることは難しいでしょう。
事業承継について、プロの専門税理士に相談したい方は、ぜひチェスターまでご連絡ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は76名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編