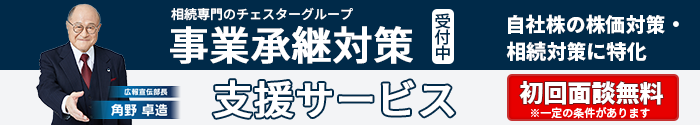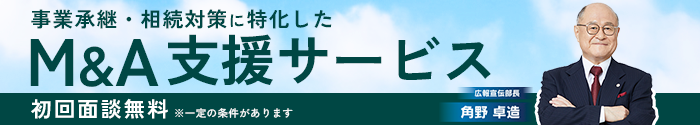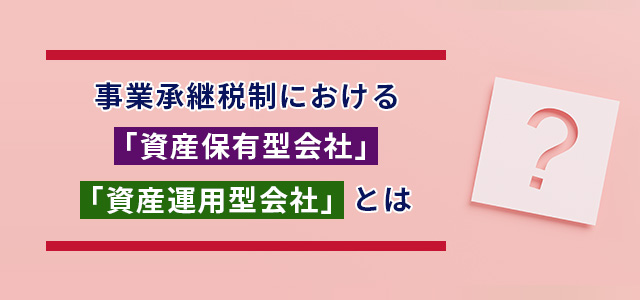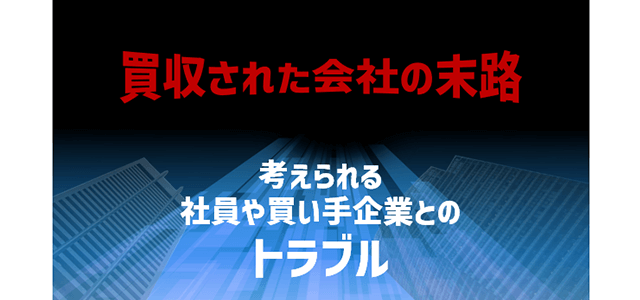特定目的会社(TMK)とは? その意味や活用方法、設立の流れを解説
タグ: #M&A
不動産投資のことを調べている中で、「特定目的会社」や「TMKスキーム」といった言葉を目にしたことはないでしょうか。
また、特定目的会社と似た言葉に、「特別目的会社」(SPC)というものもあり、こちらは、M&Aや投資ファンドをテーマにした話の中でよく出てきます。
両者の違いはどこにあるのでしょうか。
また、これらの会社は、一般的な株式会社などによる事業会社とはどう違い、どんな場面で利用されているのでしょうか。
本記事では、特定目的会社の基本や利用のメリット、デメリット、また、設立方法などについてくわしく説明します。
目次 [閉じる]
1.特定目的会社(TMK)と、株式会社との違い
特定目的会社とは、「資産の流動化に関する法律(以下、資産流動化法)」で規定されている、法人の一類型です。
株式会社などの一般の事業会社と比較することで、特定目的会社の基本的な性格が見えてきます。
なお、特定目的会社は、「特定」「目的」「会社」それぞれの頭文字をとって「TMK」と呼ばれることもあります。
また、資産流動化などの目的を実現するために、特定目的会社を用いることを「TMKスキーム」と呼ぶこともあります(後でまた触れます)。
1-1.特定目的会社が規定されている根拠法は、「資産流動化法」
特定目的会社と株式会社との違いの1点目は、それぞれが規定されている根拠法の違いです。
株式会社、合同会社などの事業会社は、「会社法」において規定されている法人です。
一方、特定目的会社は「資産の流動化に関する法律」(資産流動化法)に規定されている法人です(法人とは、法律上の権利・義務の主体となることができる組織です)。
両者は根拠となる法律が異なることから、設立や運営など、多くの面で違いがあります。
1-2.特定目的会社は、扱える業務が限定されている
2点目として、会社で扱える業務内容の違いがあります。
株式会社は定款に記載することで、モノやサービスの販売など、どのような事業でもおこなうことができます。
一方、特定目的会社は、文字通り「特定の目的」のための業務しかおこなうことができません。
その特定の目的とは、要約すれば「『資産流動化計画』に基づいた、資産の流動化及び資産の流動化に附帯する業務」です。
資産の流動化とは、簡単にいえば、不動産のような高額な資産を証券化(小口化)して、売買しやすくすることです。特定目的会社は、資産流動化とそれに附帯する資金調達など以外の事業活動をおこなうことは、認められていません。
1-3.特定目的会社には、税務上の優遇措置がある
特定目的会社は、扱える業務が限定されている代わりに、いくつかの税務上の優遇措置が定められています。
中でもポイントとなるのは、利益配当の損金算入です。簡単にいえば配当を法人の損金にできるというもので、株式会社等の事業会社では認められていません。
| 種類 | 根拠法 | 事業内容 | 配当の損金算入 |
|---|---|---|---|
| 株式会社、合同会社、合資会社 | 会社法 | 限定なし | 不可 |
| 特定目的会社 | 資産流動化法 | 資産の証券化、運用などに限定 | 可 |
2.特定目的会社と、特別目的会社との違い
特定目的会社と似ているものに、「特別目的会社」があります。混同して使われることも多いのですが、両者は明確に異なりますので、区別をしっかり理解しておきましょう。
2-1.「特別目的会社」は、法律上に規定されていない
実は、株式会社や特定目的会社と異なり、「特別目的会社」には法律上の規定がありません。
それは以下のような背景によります。
欧米では以前から、資産の流動化や証券化による資金調達に限定して業務をおこなう「Special Purpose Company:SPC」がありました。このSpecial Purpose Companyを和訳したのが「特別目的会社」ですが、日本には1997年以前は、そのような法人類型はありませんでした。
SPCの仕組みが日本に輸入されたのは、1998年にSPC法(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」)が成立して以降です。このSPC法が、2000年に改正され、現在の資産の流動化に関する法律になっています。
ここで注目してほしいのは、1998年に成立したSPC法は、「『特定目的会社』による特定資産の流動化に関する法律」という名前であり、使われている言葉が「特別目的会社」ではなく「特定目的会社」だという点です。
SPCの一般的な訳語は「特別目的会社」であるのに、SPC法で規定されたのは「特定目的会社」という名称だったのです。
ここから、特別目的会社と特定目的会社を同一のものとして混同されてしまうケースも生じているのですが、法律上規定されている名称は、あくまで「特定目的会社」だけです。
現在では、日本における特別目的会社とは、「株式会社や合同会社、特定目的会社などを総じて、特別の目的のために運営され、通常の事業活動をおこなわない会社を指す一般用語」だと理解するといいでしょう。
現実的にも、特定目的会社以外の合同会社などが、特別目的会社として用いられることは、珍しくありません。特に、資産の流動化や資金調達、M&Aなどの場面では、頻繁に用いられています。
2-2.特別目的事業体、特別目的会社、特定目的会社は、含む対象の広さが異なる
ややこしい話ですが、ここでもう1つ、「特別目的事業体」(Special Purpose Vehicle:SPV)という概念もあります。
事業体というのは、事業運営の主体となる組織や仕組みのことですが、法人だけではなく、法人以外の、民法上の組合や信託などもすべて含めて、特別の目的のために運営される組織を指す言葉が、「特別目的事業体」です。
これらの関係をまとめると以下のようになります。
| 特別目的事業体 (SPV) | 資産の証券化やファイナンス(資金調達)のみを目的として、営利事業の運営をしない事業体の総称。法人格を持たない民法上の任意組合や信託、法人格を持つ株式会社、合同会社、特定目的会社などをすべて含む概念。 |
|---|---|
| 特別目的会社 (SPC) | 特別目的事業体のうち、法人格をもつ組織の総称。株式会社、合同会社、特定目的会社など。 |
| 特定目的会社 (TMK) | 資産の流動化に関する法律に規定された方法で設立、運営されている法人。 |

3.特定目的会社を活用した資産流動化=TMKスキームとは?
特定目的会社は、主に企業が保有している不動産などの高額な資産を証券化・流動化する場合に用いられます。
このスキーム(仕組み)は、「TMKスキーム」とも呼ばれます。TMKスキームの活用場面はさまざまですが、ここでは一例を挙げます。
3-1.TMKスキームの活用
ある株式会社(X社)が100億円のビルを保有しているとします。
X社の業績が悪く財務状況が悪化したので、このビルを売りたいのですが、簡単には売れません。業績が悪いので、足元を見られて「買い叩かれる」可能性もあります。
そこで、特定目的会社を利用した「資産流動化」をおこないます。
まず、特定目的会社(Y社)を設立します。Y社が、「資産流動化計画」を作成して、TMKスキームの全体像を計画します。
そして、融資や出資を受けながら、ビルを運営(第三者に運営実務を委託)し、得られる賃料で、債権者への返済・利払いや、出資への配当をおこなっていきます。このようなY社の運営自体は、実質的にはX社がおこないます。
一方、X社は、特定資産のY社への売却で得られた資金により負債を返済すれば、悪化していた財務状況が改善でき、信用力の向上や業績の回復につなげることができます。
このように、特定社債や特定出資などの資産対応証券により資金を調達することから、「証券化」と呼ばれます。
| オリジネーター | 流動化の対象となる不動産などの原資産を保有しており、譲渡する法人や個人です。ここではX社。 |
|---|---|
| 特定資産 | 特定目的会社とオリジネーターとの間で売買の対象となる資産です。現物不動産のことが多いのですが、不動産を信託化して信託受益権を特定資産とすることもあります。 |
| 特定借入 | 特定目的会社が特定資産を取得するために金融機関などから受ける借入れです。 |
| 特定社債 | 特定目的会社が発行する社債です。 |
| 優先出資 | 特定目的会社の利益配当や残余財産の分配を特定出資者に先立って受ける権利を持つ出資のことです。 |
| 特定出資 | 特定目的会社の設立発起人の出資です。 |
| 特定資産管理処分受託者 | 特定資産の運営、管理、処分などをおこなう外部企業です。特定資産を信託財産として信託、もしくは特定資産の管理および処分に係る業務を他に委託していることは、後で出てくる「導管性要件」の一部となっています。 |
(参考)国土交通省ホームページ「不動産の証券化に関する基礎識」
3-1-2.TMKスキームは、ある程度大きな事業で用いられている
特定目的会社の設立やTMKスキームの設計、また、運営にはある程度の手間や費用がかかるため、一般的には、ある程度大きな事業において活用されるスキームだといえます。
なお、これまでに届け出があった特定目的会社の一覧は、金融庁のWebサイトで公開されています。
(参考)特定目的会社届出一覧
3-2.(参考)特別目的会社として合同会社を用いる「GK-TKスキーム」やLBOスキーム
資産流動化を目的とした特別目的会社として、特定目的会社を用いるのが「TMKスキーム」ですが、先に述べたように、特別目的会社は、必ずしも特定目的会社である必要はありません。
特別目的会社として、合同会社と匿名組合を用いる、「GK-TKスキーム」も実務上はよく利用されています。(GKは「合同」「会社」、TKは「匿名」「組合」の、それぞれの頭文字からとられています。)
ここではくわしい説明は省きますが、「TMKスキーム」と「GK-TKスキーム」とでは、設立の手間や課税面での違いなどがあるため、必要に応じて使い分けられています。
また、ファンドが買い手となるM&Aにおいては、通常、特別目的会社を利用してM&A資金の融資を受けるLBO(レバレッジドバイアウト)と呼ばれるスキームが用いられます。
4.特定目的会社の6つのメリット
資産を保有している企業が、特定目的会社を利用して資産の流動化を図ることには、以下のようなメリットがあります。
4-1.メリット1:資産を簿外化(オフバランス)することで、財務の改善が図れる
不動産などの資産を特定目的会社に売却すれば、オリジネーターは、その資産と、資産に紐付いた負債を会社の貸借対照表から切り離す(オフバランス化する)ことができます。
これにより、財務状況の改善が図れます。
具体的には、上の例で見たように、特定目的会社に資産を譲渡し、対価として得られた資金で負債を返済するといったことをします。
このオフバランス化により、自己資本比率やROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)といった経営指標が改善する、あるいは、オリジネーターのキャッシュフローが改善するといった効果が見込めます。
4-1-1.連結決算が必要な場合もあるので注意
ただし、この際には、本当にオリジネーターから資産が切り離されたといえるかどうかをしっかり確認する必要があります。
形式的にオフバランス化したと考えていても、親会社による実質支配があると認められる場合は、連結決算が義務付けられることがあるためです。
具体的には、日本公認会計士協会による「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の規定などを参照し、オフバランス化の可否を判断することになります。
(参考)特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針
4-2.メリット2:スムーズな事業承継の実現につながる
これは、上のメリット1の結果として生じるものですが、近い将来に会社の親族承継や第三者承継(M&A)を検討・予定しているのであれば、財務が健全化することによってそれがスムーズに遂行しやすくなるという効果もあります。
4-3.メリット3:流動化により資金調達の可能性が広がる
TMKスキームでは、資産がオリジネーターから切り離されます。そのため、仮にオリジネーターの信用力が大きく低下していたとしても、それと関係なく純粋に特定資産の価値や、将来得られると見込まれるキャッシュフローなどを裏付けとして、資金調達が可能になるということです。
また、一般的に高額な資産は、購入相手を探すことが難しくなりますが、証券化により小口化(=低額化)することで、より多くの投資家が投資に参加できるようになります。いいかえると、流動性が高くなります。
これにより、資金調達の間口が広がり、より大きな資金を調達できる可能性が高まるのです。
4-4.メリット4:倒産隔離機能により不動産を守れる
特定目的会社は独立した法人であるため、オリジネーターが倒産した場合でも、特定目的会社が保有する資産はその影響を受けません。これを「倒産隔離機能」と呼びます。
この仕組みがあることにより、投資家や金融機関は、対象不動産の収益性を見極めたうえで、安心して特定目的会社に資金を拠出することができます。
4-5.メリット5:法人税の特例措置(利益配当の損金算入)がある
特定目的会社は、法人税の特例措置により、一定の要件のもとで利益配当の損金算入が認められています。
これは重要なメリットなので、「5.特定目的会社の導管性と利益配当の損金不算入」でくわしく解説します。
4-6.メリット6:不動産取得税および不動産登録免許税の軽減措置がある
上記の法人税の軽減措置に加えて、特定目的会社が不動産を取得する場合、一定の要件を満たすと不動産取得に伴う不動産取得税、不動産登録免許税の軽減措置を受けることができます。
具体的には、不動産の取得に対して課税される不動産取得税の、課税標準の算定において不動産価格の5分の3が控除されます。
また、不動産の所有権の移転登記にかかる登録免許税が、1000分の13(通常は1000分の20)に軽減されます。
5.特定目的会社の導管性と利益配当の損金不算入
メリットの項目で述べた、特定目的会社が利益配当の損金算入が認められる要件などについて説明します。
5-1.一般の事業会社から受け取る配当は二重課税になっている
株式会社などの事業会社においては、法人が得た利益(所得)に対して法人税が課されます。
一方で、その会社から投資家が受け取る(税引き後の法人利益を原資とした)配当に対しても、所得税(投資家が個人の場合)や法人税(投資家が法人の場合)が課されます。つまり、課税後の利益から得られた配当にまた課税される二重課税になっているのです。
5-2.特定目的会社における利益配当の損金算入(ペイスルー課税)
特定目的会社も法人であるため、原則的に、利益に対して法人税が課されます。しかし、特定目的会社は、資産の証券化による利益の配分を目的とした法人であり他の事業をおこなうことができません。
そのような性格の特定目的会社において、二重課税があるのでは、特定目的会社を利用する意義が大きく損なわれます。
そこで、特定目的会社においては、二重課税を避けるため、一定の要件を満たす配当の全額を、法人の損金(経費)に算入して、法人段階では非課税とできる特例措置が設けられています。
投資家が配当を得た段階で、投資家への所得税、法人税などが課税されます。
このように、法人が獲得した利益に対し、法人段階では課税されず、利益の分配を受けた投資家の段階で課税される性質のことを「導管性」(どうかんせい)と呼びます。
導管性を担保する方法にも種類がありますが、特定目的会社のように法人段階で損金に参入される方法は、「ペイスルー課税」と呼ばれます。
なお、特定目的会社から投資家が受けた配当について、投資家は法人税の「受取配当等の益金不算入」や所得税の「配当控除」の適用を受けることはできません。
5-3.ペイスルー課税のための導管性要件とは
特定目的会社で、ペイスルー課税が適用されるためには、「導管性要件」と呼ばれる要件を満たしていなければなりません(租税特別措置法第67条の14)。
導管性(どうかんせい)とは、利子や配当の課税において、法人税課税との二重課税を回避する仕組みのことです。
具体的には、以下の要件が求められます(抜粋)。
このうち特徴的なのが、「利益配当が配当可能利益の90%を超えている」という項目でしょう。
この項目があるため、特定目的会社は、利益を会社にほとんど残すことができず、ペイスルー課税の名前の通り、利益が投資家にスルーしていくものであることがわかります。
・特定目的会社名簿への登載
・特定出資、優先出資の50%超が国内募集である旨が資産流動化計画に記載されている
・会計期間が1年を超えないもの
(後略)
▼要件2(対象事業年度について)
・資産流動化業務およびその附帯業務を資産流動化計画に従い行っている
・他の業務を営んでいない
・特定資産を信託財産として信託、もしくは特定資産の管理および処分に係る業務を他に委託している
・事業年度末において同族会社に該当しない
・利益配当が配当可能利益の90%を超えている
(後略)
6.特定目的会社の4つのデメリット
特定目的会社を用いることには、デメリットもあります。
6-1.デメリット1:法人設立に専門知識が必要であり、事務負担が重い
特定目的会社の設立は、資産流動化計画の作成が必須となるなど、設立までの事務負担が重く、また相応に時間もかかります。
例えば、同じ特別目的会社のGK-TKスキームで用いられる合同会社の設立と比べても、特定目的会社設立のほうが手間も時間もかかります。
6-2.デメリット2:法人の維持費用がかかる
特定目的会社は、株式会社などとは異なり、資産流動化法に基づいて設立されます。同法による法人設立には、10万円以上の資本金を用意する必要があります(会社法上の会社は1円以上)。
また、特定目的会社の設立、登記には専門家への依頼が必要であり、その報酬も必要です。
特定目的会社の運営にあたっても、一般的な株式会社とは異なる利益配分の仕組みなどがあるため、知識を持つ専門家のサポートが必要です。
6-3.デメリット3:取得できる資産に制限がある
特定目的会社は、オリジネーターの持つどんな資産でも取得できるわけではありません。
一般的には、不動産や不動産に関する信託受益権を取得する場合に、特定目的会社が用いられます。
6-4.デメリット4:資産流動化計画に定められた特定業務しかおこなえない
これはデメリットというより、特徴というべきかもしれませんが、特定目的会社は、設立時に提出する資産流動化計画に定められた特定資産に関する業務しかおこなうことができません。
資産流動化計画は後から変更することも可能ですが、取得できる資産などには一定の制限があり、無制限に資産を取得できるわけではありません。
7.特定目的会社設立の流れ
特定目的会社設立までの概要を説明します。
なお、特定目的会社の設立手続きには専門知識が必要となりますので、実行する際は専門家への相談が必須です。
7-1.(1)定款作成・認証
特定目的会社の設立には、定款の作成が必要です。
定款は、特定目的会社の基本的な事項を定めた文書で、特定目的会社の目的、出資の内容、運営の方法などを明記します。
定款は公証人による認証により法的効力を持つようになります。
7-2.(2)特定出資の払込み
定款が認証された後、発起人(特定社員)は特定出資の払い込みをします。
特定目的会社の最低資本金は10万円です。
7-3.(3)設立登記
特定出資が払い込まれたら、法務局で特定目的会社の設立登記をおこないます。
7-4.(4)資産流動化計画の作成
株式会社の設立と大きく異なるのがこの点です。
特定目的会社で、特定資産の運用事業を始めるには、「資産流動化計画」という計画書の作成・届け出が必須とされています。
資産流動化計画とは、特定目的会社がどのように特定資産を運用し、どのように資金を調達、利益配分をするのかなどを詳細に記述した計画のことです。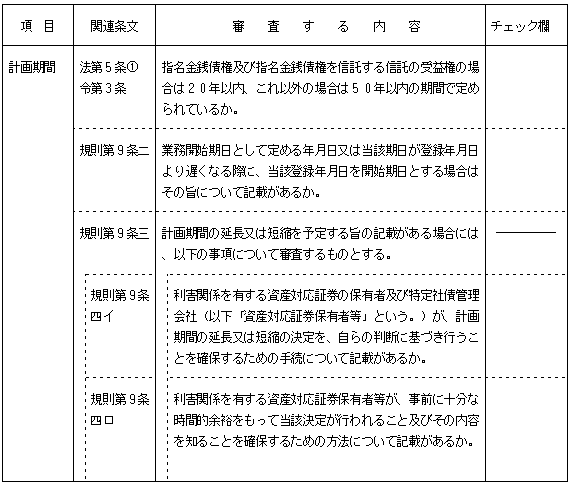
(出所:金融庁「II .資産流動化計画の記載内容」 )(一部)
7-5.(5)業務開始届出
資産流動化計画を作成後、内閣総理大臣(受付窓口は所轄財務局)に対して業務開始の届出をします。
業務開始届出には、定款や資産流動化計画の添付が必要です。この届出により、特定目的会社は正式に業務を開始することができます。
7-6.(6)資金調達
業務開始後に、資金を調達します。
具体的には、不動産などの特定資産から得られるキャッシュフローや資産価値を裏付けとして、投資家からの出資や金融機関からの借入れなど、さまざまな方法で資金調達をします。
7-7.(7)特定資産の取得
最後に、特定目的会社は資金調達により得た資金を用いてオリジネーターから不動産などの特定資産を取得します。
8.まとめ:特定目的会社を活用するには経験豊富な専門家のサポートが必須
高額な資産を保有している企業や個人は、特定目的会社を活用して資産を流動化すれば、資金調達の間口が広がり、調達可能性を高めることができるでしょう。
一方、資産流動化法に基づいて設立・運営される特定目的会社は、会社法に基づいて運営される一般的な株式会社などとは、異なる面がたくさんあり、専門知識がなければ、設立、運営は困難です。
また、GK-TKスキームなど、類似の特別目的会社スキームもあるため、どのようなスキームを用いるのがよいか、得失の比較も必要です。
いずれにしても、高度な専門知識が求められるので、特別目的会社の運営経験の豊富な専門家に相談しながら進めていくことが大切です。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。