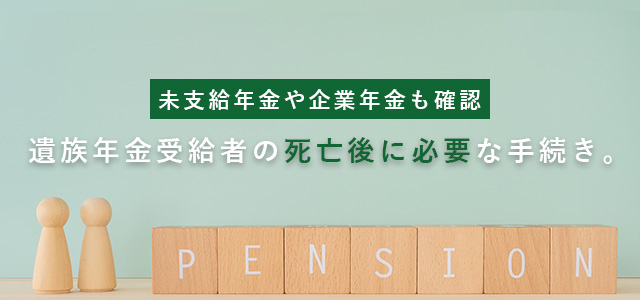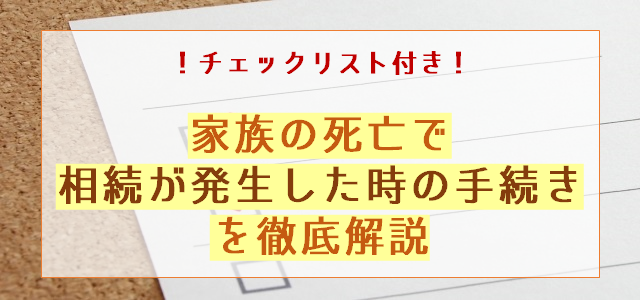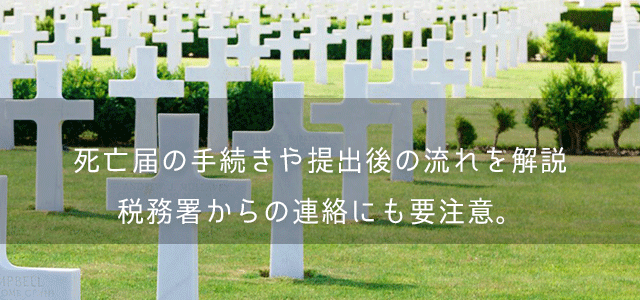相続手続きは何から手をつける?手続きの流れや放棄する方法を解説
タグ: #相続手続き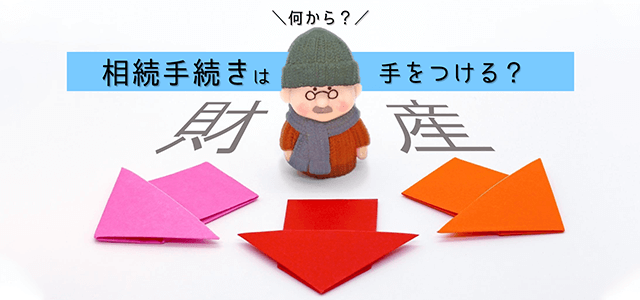
相続を完了するにはさまざまな手続きが必要です。それぞれ異なる期限が設けられているため、期限内に済ませられるよう、手際よく進めましょう。相続放棄の方法や、相続について相談できる専門家についても紹介します。
目次 [閉じる]
1.相続手続きの基本知識
相続手続きはなぜ必要なのでしょうか?具体的な手続きの進め方をチェックする前に、まずは相続に関する基本知識について見ていきましょう。
1-1.遺産相続のための手続きのこと
相続手続きは遺産を次の世代が受け継ぐために必要な手続きのことです。相続において、亡くなった人を『被相続人』、遺産を引き継ぐ人を『相続人』といいます。
遺産というと土地や預貯金といったプラスの財産をイメージする人が多いかもしれません。しかし借金や借金の連帯保証、所得税や住民税の未払い分など、マイナスの財産も遺産として扱われます。
これらの私有財産は所有者が亡くなると、相続人の全員で共有している状態になります。
1-2.なぜ相続手続きが必要なのか
正しい手順を踏み相続手続きを実施することは、相続人同士のトラブルを避けることにつながります。相続人は1人とは限りません。配偶者・子ども・親など複数人が法的な相続の権利を持つことも多いものです。
例えば相続財産として代表的な不動産は、立地を含むさまざまな条件により、価値が決まります。そのため誰がどの不動産をどのような割合で引き継ぐかを、遺産分割協議で詳細まで決めることが大切です。
また相続手続きを実施せずにいると、次の世代の相続が複雑になるというデメリットが発生します。被相続人から子世代が相続したときに手続きをしないままにもできますが、そのままでは孫世代でトラブルが起きる可能性があるのです。
2.死亡から10日以内に行う相続手続き

相続には、さまざまな手続きが必要です。それぞれ期限が異なるため、まずは死亡日から10日以内に行うものをチェックしましょう。
2-1.死亡届の提出
死亡日より7日以内に実施するのが『死亡届』の提出です。記載されている人が死亡したことを届け出る書類のことで、死亡した地域か本籍地、または届出人の所在地(住所地)の市区町村役場で手続きします。
用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書になっており、死亡診断書は医師に記入してもらいます。届出ができるのは親族のほか、同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人などの関係者です。
2-2.年金受給停止
年金受給者が亡くなった場合『年金受給停止』の手続きを行います。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に手続きしましょう。住民票の住所地を管轄する年金事務所へ年金受給権者死亡届を提出します。提出先は最寄りの年金相談センターでもかまいません。
手続きを忘れると受給者の死亡後も年金が振り込まれ続けます。後から返還しなければいけませんし、故意でなくても問題に発展することがあるため注意を要します。手続きには以下の書類を用意します。
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書・戸籍抄本・死亡届の記載事項証明書など)
故人の年金手帳が見つからない場合には、紛失届も必要です。また、死亡時期によっては未支給年金がある場合があります。その際は、給付の申請を行います。
3.死亡から2週間以内に行う相続手続き

亡くなってから2週間以内が期限の手続きもあります。死亡届と同時に済むものもありますが、個別に連絡しなければいけないものもあるため忘れないようチェックしましょう。
3-1.住民票の抹消・除票
死亡届を提出すると自動的に故人の住民登録が抹消されます。これが『住民票の抹消』の手続きです。そのため別個に提出しなければいけない書類はありません。
手続きをしたら住民票の除票を取得しておくと、不動産登記や相続税申告の際にスムーズです。除票とは、抹消された住民票のことをいいます。取得の際は、故人と届出人の関係がわかる戸籍謄本と届出人の身分証明書を持参しましょう。
3-2.健康保険の資格喪失の届け出
故人が加入していた『健康保険の資格喪失』の届け出も忘れずに実施しましょう。加入している健康保険によって、手続きの期限や届け出先が異なります。
国民健康保険は亡くなってから14日以内が届け出の期限です。市区町村役場へ健康保険証の返却とともに届け出ます。故人が75歳以上の後期高齢者なら、後期高齢者医療資格喪失届の提出が必要です。
勤め先企業で健康保険に加入している場合、届け出の期限は亡くなってから5日以内です。会社経由で年金事務所へ届け出するため、勤務先の指示に従い必要書類を用意します。
3-3.世帯主変更届の届け出
世帯主が亡くなった場合、世帯主が不在になってしまうため『世帯主変更届』も提出しましょう。特別な理由がなく届け出を怠ると、5万円以下の過料を科されます。
ただし残された世帯員が1人のみか、15歳未満の子どもと親権者のみの場合には、特別変更の届け出は必要ありません。二つのケースに該当しないときには、亡くなってから14日以内に手続きを済ませます。
世帯主変更届は故人の住所地が属する市区町村で行う手続きです。身分証明書を持参することで実施できます。
新たな世帯主はもちろん、他の世帯員や知人などの代理人による手続きも可能です。同じ世帯ではなく代理人の場合は委任状も持参します。
3-4.介護保険資格の喪失届
故人が介護保険の被保険者の場合『介護保険資格の喪失届』を、死亡してから14日以内に市区町村役場へ提出しましょう。65歳以上で介護保険被保険者証があるなら返還が必要です。
その時点で保険料の未納分がある場合は、相続人に請求されます。納め過ぎの状態になっていれば、保険料過誤状況届出書を提出することで相続人に還付される仕組みです。
4.死亡から3カ月以内に行う相続手続き

2週間以内に行う手続きは、故人が加入していた健康保険や年金、行政機関で行う戸籍に関する手続きなどが中心でした。3カ月以内に実施する相続手続きは、実際に遺産をどのように扱うか決定する内容です。
4-1.遺言書の調査と検認手続き
相続手続きをする前に、まず遺言書があるかどうか調査をします。見つかった遺言書の種類によっては、『検認』の手続きをしなければなりません。
遺言書の調査と検認手続きに期限は定められていませんが、これらを行わなければ遺産の相続手続きを進められないため、必ず最初に行いましょう。
検認とは客観的に遺言書の存在を明確にし、偽造を防止するための手続きのことです。自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合に実施する必要があります。公正証書遺言の場合は、遺言書自体を公証人が作成しているため検認の必要はありません。また、自筆証書遺言であっても法務局で保管されていた場合は、検認の必要はありません。
検認を行うには、まず関係書類を集めて申立人が家庭裁判所へ提出します。その後1カ月~1カ月半後を目安に、家庭裁判所から全ての相続人へ遺言書検認日の案内が郵送されます。
通知された遺言書検認日に、遺言書を開封し内容を確認すると手続きは完了です。検認が行われたことを証明する検認済証明書は、不動産の名義変更や預貯金の解約時に必要になります。
4-1-1.検認に必要な書類
検認に必要な書類のうち、全てのケースで共通して用意する書類は下記のとおりです。
- 検認申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子どもが死亡している場合はその子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 遺言書のコピー(遺言書が封印されていない場合)
加えて相続人の続柄に応じて、戸籍謄本を用意します。例えば兄弟姉妹が相続人となる場合は、父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本や、祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
4-2.相続放棄または限定承認の手続き
相続には不動産や預貯金と同時に負債も受け継ぐ『単純承認』の他に、プラスの資産の額を限度に負債を受け継ぐ『限定承認』や、一切を相続しない『相続放棄』があります。
単純承認の意思表示をしたとき、相続財産の全部または一部を処分したとき、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったときに、適用されるのは単純承認です。もしも遺産に多額の借金が含まれていても、3カ月以内に限定承認または相続放棄を行わないときは、全て相続しなければいけません。
そのような事態に陥らないよう3カ月以内に相続の方針を決定し、限定承認や相続放棄をする場合は家庭裁判所で手続きを実施します。
相続放棄に必要な書類は、「8.相続放棄を行う場合に必要な書類」で解説します。
4-3.相続の承認又は放棄の期間を伸長する
限定承認や相続放棄のためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内の手続きが必要です。この3カ月を『熟慮期間』といいます。しかし場合によっては3カ月の間に遺産の調査が完了しないこともあるでしょう。
そのようなときに家庭裁判所へ申し立てるのが『相続の承認又は放棄の期間の伸長』です。当初定められている3カ月の熟慮期間中に申し立てすることにより、熟慮期間を3カ月延長できます。
5.死亡から4カ月以内に行う相続手続き

被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの間に一定の収入がある場合、相続人は、相続の開始を知ってから4カ月以内に必要な手続きが発生することがあります。
5-1.所得税の準確定申告を行う
生前に一定の収入がある場合、相続の開始を知ってから4カ月以内に『準確定申告』を行うとともに、納税しなければいけません。故人が以下に該当するようであれば、速やかに手続きしましょう。
- 個人事業主で収入を得ていた
- 給与を2カ所以上から受けていた
- その年の1月1日から亡くなるまでの間の給与収入が2000万円を超えていた
- 不動産運用で家賃収入を得ていた
- 株の配当金といった給与や退職金以外の所得があった
- 多額の医療費を支払っていた
収入が年金のみの場合、400万円以下であれば準確定申告は必要ありません。ただし手続きすることで所得税が還付されることもあります。
準確定申告で使う付表は、通常の確定申告とは異なるものです。国税庁のWebサイトや税務署で入手しましょう。
6.死亡から10カ月以内に行う相続手続き

10カ月以内に行うのは相続の実施に伴う各種手続きです。法的には期限が決まっていませんが、10カ月以内に行うことでスムーズに相続を進められる手続きも含みます。
6-1.遺産分割協議書を作成する
まず挙げられるのは『遺産分割協議書』の作成です。相続の内容が決定したら、それを第三者にも証明できるように作成します。相続人全員が分割内容について合意し、その内容を確認し実印を押して保有することで、トラブル回避にもつながります。
法的に作成の期限を設けられているわけではありませんが、他の手続きに間に合うよう、できるだけ早い段階で作成し始めるとよいでしょう。必要な項目も厳密に決められていませんが、下記について詳しく記載します。
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍・死亡時の住所
- 各相続人の氏名・相続内容
- 各相続人の氏名・住所・押印
法律で定められている法定相続割合や遺言書通りに相続を実施するときには不要ですが、割合を変更する場合に作成が必要です。
6-2.相続税の申告
死亡を知った翌日から10カ月以内に手続きが必要なのは『相続税の申告』です。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し納付します。
遺産分割協議が長引き終わっていない場合でも、手続きが遅れると税務署による調査が行われ延滞税や加算税が課税されます。この状態を避けるには、法定相続人が法定相続分で引き継いだと仮定し、申告と納税をしなければいけません。
そして正式に協議がまとまった段階で相続税を計算し直し、税務署で手続きします。このとき過払い分は還付され、不足分は追加で支払う流れです。
また遺産の総額が『3000万円+(法定相続人の数×600万円)』で計算できる基礎控除額の範囲内におさまっていれば、相続税は発生しないため申告は必要ありません。
6-3.預貯金や有価証券などの名義変更
遺産分割協議終了後には、財産の名義変更を行います。
預貯金や有価証券であれば銀行や証券会社へ連絡し、所定の方法に従って手続きします。一般的には連絡後に残高証明を請求し、所定の用紙を提出する流れです。相続届や名義変更届・相続人全員の署名押印・戸籍謄本・印鑑証明などを用意します。
6-4.不動産の相続登記(名義変更)
不動産を相続するときには『相続登記』をして法務局で名義変更を行いましょう。登記申請書と合わせ、故人の戸籍謄本・故人の住民票除票もしくは戸籍附票・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明・遺言書などを用意します。
このとき不動産固定資産評価額の0.4%の登録免許税が必要です。
不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続したことを知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。
ただし、3年以内であってもできるだけ早く相続登記をしましょう。被相続人の名義のままになっている不動産は相続人の共有財産になるため、例えば他の相続人が借金を支払えなくなったとき、共有持ち分の不動産を差し押さえられてしまう可能性があるのです。
売買やビジネスのチャンスがあっても、すぐに取引できずチャンスを逃してしまうかもしれません。財産として存分に生かすためにも、相続登記は必要な手続きです。
6-5.各種財産の名義変更
財産は預貯金や不動産だけではありません。例えば自動車の名義変更は相続開始から15日以内の実施が義務付けられています。保険や自動車税のトラブル回避のためにも早めに手続きしましょう。
管轄の運輸局か自動車検査登録事務所で実施可能です。その際以下の書類等を用意します。
- 移転登録申請書
- 自動車税申告書
- 自動車検査証
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 手数料納付書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 手数料500円
バイクの相続は1度廃車手続きをした後に再登録して名義変更が可能です。125cc以下は市町村役場、126cc以上は運輸局で行います。
またゴルフ会員権や損害保険は名義変更か売却・解約の方針を決定後、それぞれの企業の方法に従い手続きします。
7.死亡から1年~5年以内に行う相続手続き

相続が一通り完了した後にも、見直しの結果税金の支払い過ぎが判明したり、受けられる給付制度が判明したりすることがあります。その中でも1年~5年以内に行うものを確認しましょう。
7-1.遺留分侵害額請求の手続き
被相続人の配偶者・子ども及びその代襲者・父母や祖父母などで相続人である人は、法律上、最低限の取り分が保障されています。これを「遺留分」といいます。
被相続人が遺言で他人に多くの財産を与えると、相続人は財産を十分に相続できず遺留分を侵害されることがあります。遺留分を侵害された人は、その侵害された金額を、財産をもらった人に請求することができます。これを『遺留分侵害額請求』といいます。
この請求ができるのは、遺留分侵害を知ってから1年以内か、相続の発生から10年以内です。そのためこの期間内にできるだけ早いタイミングで手続きを行いましょう。
ただし、遺産分割協議で遺留分未満の財産取得に同意している場合、遺留分侵害にはあたらず請求もできません。
7-2.葬祭費、埋葬料の請求手続き
喪主は故人の健康保険から葬祭費や埋葬費を受け取ることができます。国民健康保険であれば2年以内に請求することで『葬祭費』の給付を受けられます。国民健康保険なら5~7万円、後期高齢者医療制度なら3~7万円です。
ただし給付されるのは葬祭費のため、告別式といった葬祭を行った場合にのみ受け取れます。手続きは市区町村の保険年金課へ問い合わせましょう。
会社員として組合健保や協会けんぽに加入していた場合、健康保険から一律5万円の『埋葬料』か、5万円の範囲内で実費として『埋葬費』が給付されます。2年以内に健保組合や全国健康保険協会での手続きが必要です。埋葬料(埋葬費)として給付されるため、葬祭を行わない場合も受け取れます。
7-3.生命保険金の請求(保険会社により異なる)
生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている人は保険金受取の手続きをしましょう。手続きの期限は保険会社ごとに異なるため、できる限り早い段階で行うのがおすすめです。
契約している生命保険会社へ連絡し、請求書・被保険者の住民票・受取人の戸籍抄本・印鑑証明・死亡診断書・保険証券などをそろえて手続きします。
また保険金は受取人固有の財産になるため、他の相続人への相談や許可は必要ありません。
7-4.相続税軽減・還付の手続き
遺産分割協議の終了前に申告と納税を行った場合『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出していれば、遺産分割協議が終了した段階で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受け、相続税が軽減される可能性があります。
そのためには死亡してから3年10カ月以内に遺産分割協議を終わらせ、その4カ月以内に更正の請求を行わなければいけません。
また納税後に相続税額の減額が可能と分かるケースもあります。特に不動産は評価額の算定が難しく、税理士によって大きく差が出る部分です。当初と異なる相続税額となった場合、亡くなってから5年10カ月以内であれば、相続税還付の手続きができます。
7-5.遺族年金の請求
国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときには『遺族年金』の請求ができます。ただし請求できるのは死亡日から5年以内です。やむを得ない事情を除いては、期限が過ぎると請求できなくなってしまいます。
遺族年金の請求には、以下の書類が必要です。書類をそろえた上で、国民年金なら市区町村や年金事務所へ提出、厚生年金なら年金事務所または会社経由で手続きします。
- 年金請求書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 故人の住民票の除票
- 請求者の所得証明書
- 死亡診断書
8.相続放棄を行う場合に必要な書類

ここまで、遺産相続の手続きの流れを見てきました。続いて、相続放棄を行う場合に必要な書類をご紹介します。
遺産の内容によっては相続放棄を選択した方がよいケースもあります。相続放棄にも複数の書類が必要です。原則として3カ月以内に手続きするため、相続放棄が決まったら速やかにそろえましょう。
8-1.相続放棄申述書
まず用意するのは『相続放棄申述書』です。フォーマットを裁判所のホームページから取得し作成します。
記入する項目が少なくそれほど複雑でもないため、比較的簡単に作成できるでしょう。ただし『申述の理由』の内容が重要な意味を持つ点に注意が必要です。
申述の理由によっては、詳しい事情説明や資料をプラスしなければいけないこともあります。
8-2.被相続人の住民票除票・戸籍謄本
被相続人の『住民票除票』と『死亡の記載のある戸籍謄本』も必要です。相続放棄する人の続柄によっては、被相続人の『出生から死亡までの全ての戸籍謄本』が必要になる場合があります。
住民票除票は、被相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。死亡の記載のある戸籍謄本と、出生から死亡までの全ての戸籍謄本は、本籍地のほか最寄りの市区町村役場で取得できます。
ただし、戸籍謄本は本籍地でしか取得できない場合があり、その場合は全ての戸籍謄本が1か所でそろうとは限りません。不足している場合には以前の本籍地へ請求し、出生までさかのぼる戸籍謄本をそろえましょう。
8-3.申述人の戸籍謄本
相続放棄をする申述人の『戸籍謄本』も取得します。戸籍謄本は本籍地のほか最寄りの市区町村役場で取得できます。
本籍地に請求する場合、郵送で申請することもできます。本籍地がコンビニ交付を導入していれば、マイナンバーカードを用いコンビニでも取得可能です。
8-4.収入印紙と切手
相続放棄には、申述人1人につき800円が必要です。『収入印紙800円分』を相続放棄申述書に貼って家庭裁判所に提出します。
『連絡用の郵便切手』も必要です。郵便切手の金額は各家庭裁判所で異なるため、管轄の家庭裁判所のホームページを参考にします。
9.専門家に相談する場合の注意点

法律上相続手続きは全て自分で行えます。しかし期限内に必要書類を集め全ての手続きを行うのは、手間がかかることです。紹介する注意点を参考にしながら専門家へ依頼しましょう。
9-1.内容により相談先が異なる
まず注意しなければいけないのは、専門家によって対応できる分野が異なる点です。不動産の登記について相談するには『司法書士』が向いていますが、相続税対策であれば『税理士』が適しています。
また相続人間のトラブルや遺留分請求など、相続に関する幅広い問題を相談するのは『弁護士』がよいでしょう。手続きの一部だけを任せて費用を抑えたいなら『行政書士』が向いています。
どの専門家に相談すればよいか判断が難しい場合『銀行』や『信託銀行』に相談するのも有効です。窓口となって適した専門家へ依頼してもらえるため、相談先を探す手間を最小限にできます。
9-2.迷ったらすぐに相談を
相続手続きには期限があるものも多く、放っておくと税金や延滞金の督促を受けることもあります。当初は自分で行い費用を抑えようと考えていても、専門的な内容につまずくこともあるでしょう。
できるだけ早期に専門家へ相談することで、法的に正しく短期間のうちに手続きができます。期限が迫ってからの相談では、不本意な条件で相続することになりかねません。
相続にお悩みなら、余裕を持って対応できる時期に『税理士法人チェスター』へご相談ください。
10.相続手続きは計画的に行うことが重要
専門的な知識が必要な相続手続きは、計画的な実施が欠かせません。期限が決まっている手続きがたくさんあるため、途中でつまずくとスムーズに実行できなくなってしまいます。
そこで信頼できる専門家へ相談するとよいでしょう。ただし相談内容によって適切な相談先は変わります。例えば相続税の申告や軽減・還付についての相談であれば、税理士法人チェスターを始めとする税理士が適切です。
専門家を活用し複雑な相続手続きを早期に実施しましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。