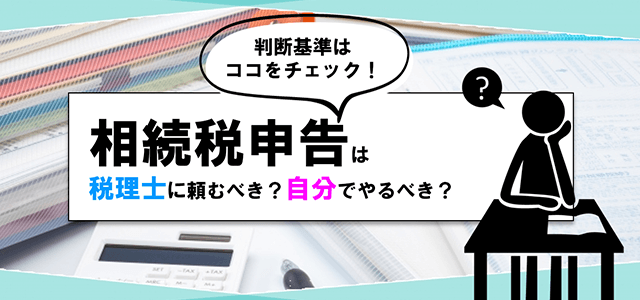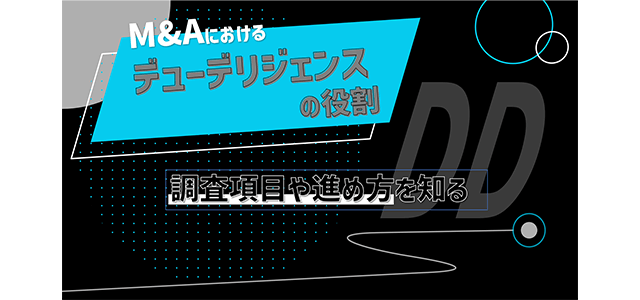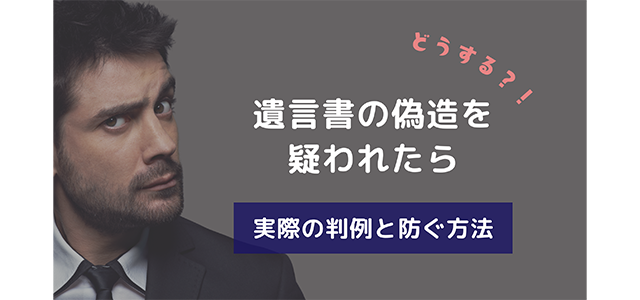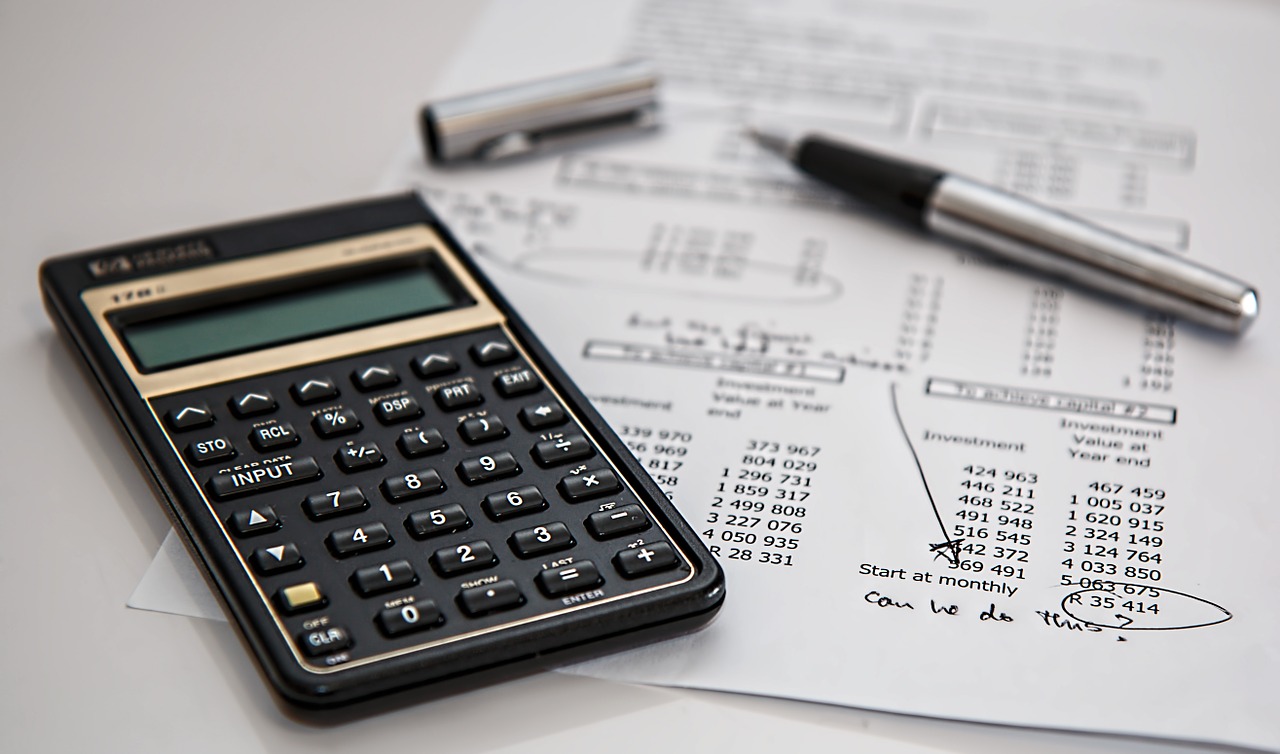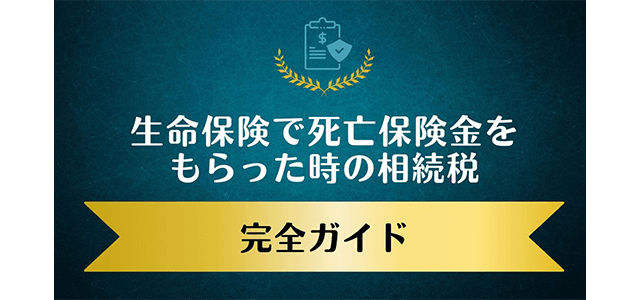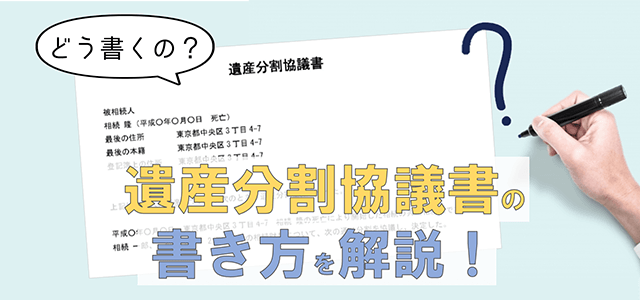終活ノートの意味と活用のコツ。記載しておきたい項目を解説
タグ: #終活・葬儀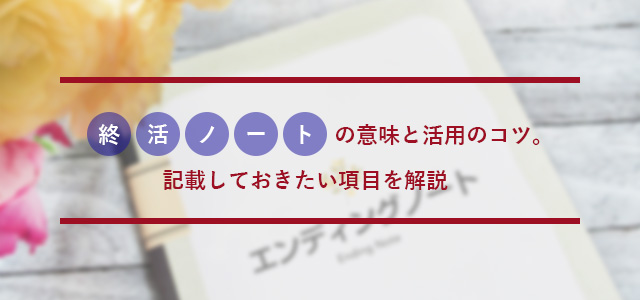
『エンディングノート』とも呼ばれている終活ノートは、どのように作ればよいのでしょうか?記載すべき内容が分かるよう代表的な項目を紹介します。また終活ノートの目的や作り方、書く際の手順、活用方法なども見ていきましょう。
目次 [閉じる]
1.エンディングノートを作成しよう

エンディングノートの作成にあたり、まずは目的や役割を解説します。どのような意義のあるノートなのか把握した上で作成を始めれば、自分にも家族にとっても役立つエンディングノートができるはずです。
1-1.目的は家族が困らないため、自分のため
自分の死後、何をどのようにしてほしいかが記載されたノートがあれば、家族はその内容に従って供養や片付けを進められます。意思表示をせずに全て家族任せにしてしまうと、想像以上の負担となってしまう場合もあるでしょう。
また緊急連絡先や所有している銀行口座などについて記載されていれば、誰に連絡すればよいか、どこで手続きが必要かなどが一目瞭然です。家族の手間を減らすのに役立ちます。
同時に、元気な間は自分の備忘録として活用することも可能です。書き進めることで人生を振り返る機会も得られるでしょう。
1-2.遺言を残す場合は正式な遺言書が必要
財産を誰にどのような割合で分配するかも、エンディングノートに記載できます。ただしエンディングノートへ書いただけでは法的な意味はなく、希望を書いただけにすぎません。
遺産相続についての希望があるなら、エンディングノートとは別に『遺言書』の作成が必要です。正式な遺言書を作成しておけば、自分の希望に添った遺産相続を実施してもらえます。
ただし効力を発揮する遺言書を作成するには、ルールにのっとって決められた内容や形式で作成しなければいけません。エンディングノートのように自由に記述できない点に注意しましょう。
2.エンディングノートの作り方
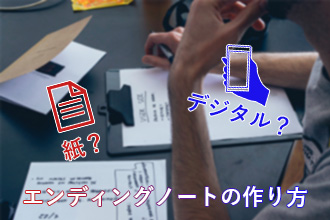
では具体的にエンディングノートはどのように作ればよいのでしょうか?手書きする方法に加え、パソコンやスマホを使う方法もチェックしましょう。
2-1.専用ノートを使う、参考にして自作する
エンディングノートは、専用のものを1,000~2,000円程度で文具店や書店で購入できます。どのような項目を作成すればよいか分からないなら、まずは市販のエンディングノートを購入し記載していきましょう。
あらかじめ項目が記されているため、空欄部分を埋めるように書いていくだけで完成します。中には暗証番号といった個人情報を記載する箇所もあるため、保護シール付きを選ぶと安心です。
専用ノートを購入する前にどのようなものか知ってみたい場合には、インターネットを利用し無料で取得できるタイプを使ってみるのもよいでしょう。項目を参考にしながら、自分で用意したノートに書いていく方法もあります。
2-2.デジタル時代に合った情報の残し方
手書きでエンディングノートを作成するのもよいですが、デジタルの資産やサービスについてはパソコンやスマホを使い記録した方がよいでしょう。デジタル資産はサービスの追加や変更が頻繁に行われるからです。
またアカウント名やパスワードなどには、英数字や記号が用いられます。大文字・小文字の区別もあるため、手書きのノートでは見返しても判別しにくい場合もあるでしょう。
記載されている文字の判別が難しく入力を繰り返し間違えた場合、サービスによってはロックされ解除に時間がかかるケースもあります。パソコンやスマホ内に記録されていれば、このような問題は起こりにくいはずです。
2-3.アプリだけへの保存はおすすめできない
専用のアプリを利用してエンディングノートを作成する方法もあります。これならパスワードの誤記や誤読対策も万全です。ただし内容を保存しておくのがアプリだけという状態は避けましょう。
アプリは運営会社がなくなったり経営方針を変更したりすると、サービスを終了する可能性があります。場合によっては書いた内容が読めなくなることもあるのです。
死後に家族がアプリを確認しようとしたら、既にサービスが終了していたというケースも考えられます。そのような事態を避けるため、必要最低限の内容に絞りノートに書いておくと安心です。
ノートを使えば、アプリでは難しい自由な記述がしやすいというメリットもあります。
3.エンディングノート活用のコツ
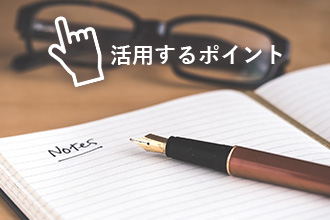
一度書いただけで放置してしまっては、エンディングノートを生かしきれません。活用するにはポイントがあります。
3-1.定期的に書き足して情報を更新していく
作成時には書ける項目からどんどん書きましょう。順番にこだわると途中でつまずき、ノートを完成させられないからです。
また書き終わってからも定期的に見直し、情報の修正や書き足しを行いましょう。常に新しい情報に更新することで、役立つノートになります。誕生日や元日など、日にちを決めて見直すようにすれば忘れません。
3-2.保管場所を決めて信頼できる家族に伝える
エンディングノートを書いても、家族に見つけてもらえなければ、いざというときに活用できません。自分の意思を伝えられない状態になったときや死後に役立てられるよう、保管場所を決めましょう。
自宅の金庫・たんす・仏壇・食器棚などが代表的な保管場所です。どこへ保管するか決めたら、信頼できる家族に伝えます。
4.書きやすい基本項目から埋めていこう
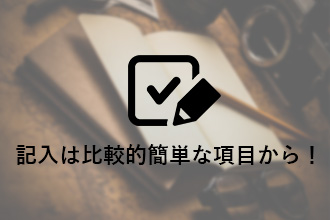
たくさんの項目が用意されているエンディングノートは、いざ書こうとすると難しく感じるかもしれません。そこでまずは比較的簡単に記入できる項目から書き始めましょう。
4-1.まずは自分に関することを書く
自分に関することであれば、資料を用意しなくてもすらすら書ける項目が多いでしょう。生年月日・住所・本籍地などであれば、すぐに埋められるはずです。
加えて趣味や好みについても記載します。好きな食べ物や日々の楽しみについて詳細に書いておくと、介護が必要になったときに好みを把握してもらえるでしょう。
同時に健康状態についても書いていきます。持病・服用している薬・アレルギーの有無・飲酒の習慣などについてです。あわせて『健康保険証』や『おくすり手帳』の保管場所も書いてあると、いざというときに困りません。
また今後の医療や介護に関する希望も書いておくと、自分で判断できない状況に陥った際にも安心です。
4-2.銀行口座、株式などの財産について
財産として銀行預金や株式などがあるなら、その内容を全て記載し明らかにします。家族であっても全ての口座を把握していないケースは多いものです。
存在に気付いていない財産は相続できません。家族に内緒で貯めている預貯金についても、全て書き出しておきましょう。
同時に通帳・証書・印鑑などの保管場所も書いてあると、家族が家中を探し回ることなくスムーズに手続きを進められます。ほかにも現金・不動産・貴金属などがあるなら明記しましょう。
4-3.マイナスの資産も記載する
中にはマイナスの財産を保有している人もいるでしょう。家族の役に立たないマイナスの財産については、書きたくない人もいるかもしれません。しかし記載してあることで、家族は相続放棄を選択できる可能性があります。
預貯金が一定額あったとしてもそれを上回る借金があれば、相続しても家族の負担が増してしまいます。それならば相続せず放棄しようと考えるでしょう。
ただし相続放棄には3カ月までという期限があります。そのため資産はプラスもマイナスも明らかにし、家族が早い段階で決断できるようにすることが大切です。
またマイナスの資産を見られたくない相手がいるなら、ノートを分けるのも手です。見られたくない情報を柔軟に管理できます。
4-4.加入している保険商品について
生命保険や医療保険へ加入している場合には、その内容についてもエンディングノートへ記載しましょう。生命保険へ加入していることが分かれば、死後に家族が請求手続きをスムーズに進められます。
また医療保険があると分かれば、入院による医療費の負担を軽減することが可能です。加入していても適切なタイミングで利用できなければ、無駄になってしまいます。
エンディングノートで保険について家族に知らせられれば、加入した保険を必要なときに役立てられるはずです。
4-5.登録、契約しているサービス
ほかにも利用しているサービスがあるなら、一覧にしておきます。駐車場の契約、サークルや習い事、貸金庫など費用が発生しているものは全て書き出しましょう。
水道・ガス・光熱費・インターネットなどの引き落とし口座といった情報も記載します。SNSを利用しているなら、アカウントをどのように処理するかも決定し書いておきましょう。
このようなサービスは家族が確認しても把握しきれないことが多々あります。解約に必要な情報や死後の処理方法が書いてあれば、手続きを行う家族の負担軽減につながるはずです。
また登録サービスについての項目では、IDやパスワードも記録します。重要な個人情報はノートを分け、別に保管しておくと安心です。
5.家族、周囲の人のことを書く

自分のことを一通り書き終わったら、次は家族や周りの人について書きましょう。日ごろ伝えられない想いも言葉にしておくと、素敵なメッセージになります。
5-1.大切な人の連絡先やコメント
親戚や友人など、大切な人の連絡先を記録しましょう。家族の友人の連絡先は分からないことが多く、葬儀の連絡ができないことも珍しくありません。エンディングノートに記載しておけば、そのような心配は不要です。
また親戚の名前・続柄・連絡先を表にまとめ、関係性が分かるようにしておくのも役立ちます。相続の手続きをする際にもスムーズです。
5-2.ペットを飼っている場合
ペットの扱いについても書いておくと安心です。将来的に施設への入所や病院への入院が決まったとき、自分がいなくなった後は、ペットの世話をほかの誰かにお願いしなければいけません。
そのためペットの面倒を見てもらいたい人を書いておきます。周りに任せられる人がいないなら、ペットを引き取っているNPO法人を記載してもよいでしょう。
ただし、相手に相談せずにエンディングノートに書くのはNGです。事前に許可を取り付けておくようにしましょう。託された人がペットの世話をしやすいよう、名前・種類・年齢・かかりつけの獣医・好きなことなども書いておくのもおすすめです。
6.将来のことを考えて書く

現在の自分や周りのことはもちろん、将来のことも書いておくと、自分で物事の判断ができなくなった際や死後に役立ちます。
6-1.介護の依頼先、介護資金の預け先
年齢を重ねると介護が必要になることもあるでしょう。どこでどのような介護を受けたいのか、希望を書いておくと家族が困りません。
施設での介護を希望するなら、どのような施設に入所したいのか条件を書き出します。具体的に入所したい施設が決まっているなら、その施設の名称や連絡先も記載すると家族の手間を軽減できます。
家族の力を借りて自宅で介護を受けたいと考えているなら、誰にどのように担ってもらいたいかもはっきりさせましょう。単に希望を書くだけでなく、そのための資金についても言及します。
年金でまかないきれない分については、預貯金や資産の売却などが必要になるかもしれません。
6-2.理想の葬儀、納骨の方法
葬儀については家族が決めるのが、かつては一般的でした。しかし昨今はエンディングノートに基づいて、本人の意思を尊重する傾向が強まっています。
例えば葬儀は密葬や家族葬など小規模に開催するのか、できるだけ多くの知人・友人を呼びたいのかを決めておきます。納骨も従来通りに実施するほか、散骨を選べるケースもあるでしょう。
遺影に使う写真や喪主を務めてほしい人の希望も記しておきます。どのような葬儀をしたいかあらかじめ決めておくと、家族が希望に添って準備を整えやすいでしょう。
6-3.遺言書の有無や保管場所
遺言書の有無は遺産分割協議の実施における重要なポイントです。そのため必ず記載しましょう。
遺言書を作成しているのであれば、それが自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれにあたるかも書きます。あわせて作成時に協力してもらった専門家の連絡先も明示しておくと安心です。
7.ノートの活用でよりよいシニアライフを
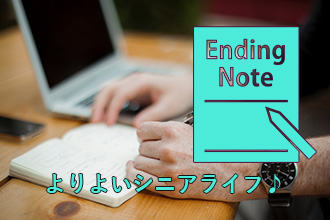
エンディングノートは老後や死後について、自分の希望を示すためのノートです。あらかじめ作成しておくと、家族はノートの内容をもとにさまざまな手続きを進められます。
自分にとっても、これまでを振り返るきっかけになり、改めて自分の希望と向き合うことで、意識が変化する可能性もあるでしょう。ノートへ書く内容は、自分のことや周りの人のこと、将来のことなどさまざまです。
ただし一度書いたからとそのまま放置していると、いざ使いたいときには情報が古過ぎる可能性があります。定期的な見直しと修正で、よりよいエンディングノートを作成できるでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。