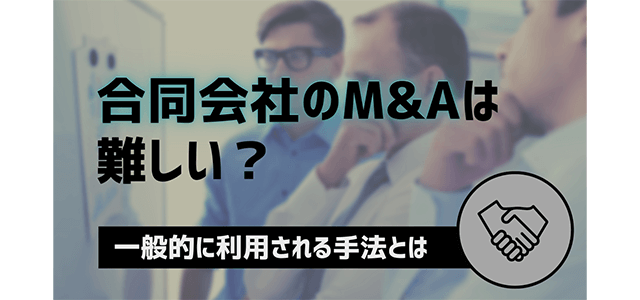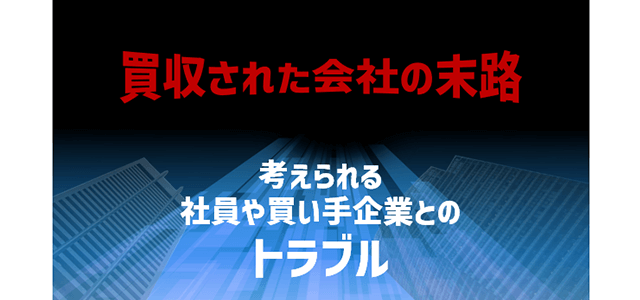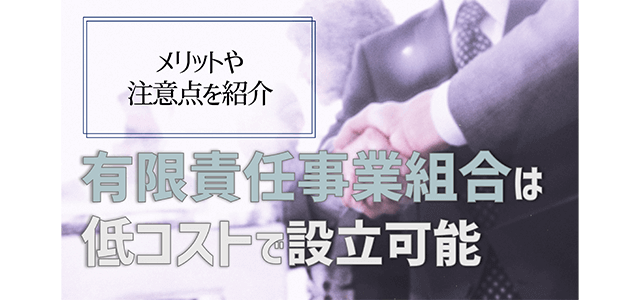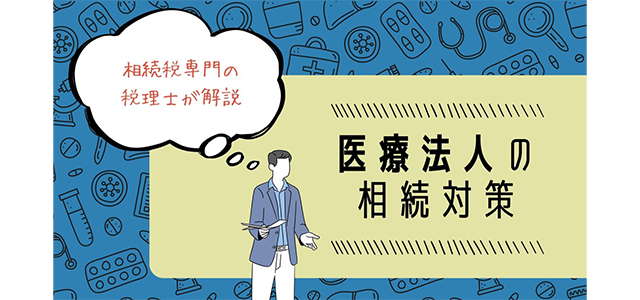相続税対策で合同会社を設立するときに知っておきたい注意点
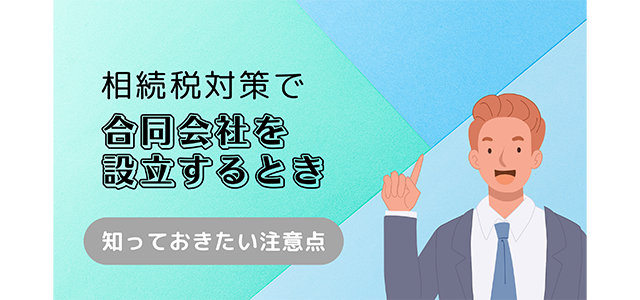
不動産オーナーなど資産家の相続税対策では、資産管理会社を設立するケースがあります。
資産管理会社は、事業で利益を得ることよりも、資産を個人の所有から切り離すことや税務上のメリットを受けることを目的にしています。そのため、会社の設立費用や運営の手間は少なくしたいものです。
合同会社はこれらのコストを抑えられる会社の種類で、資産管理会社として設立する場合に適しています。しかし、出資者が死亡した場合の対応を決めておかなければ、資産管理会社を設立した目的が果たせなくなることもあります。
この記事では、相続税対策で合同会社を設立するときに知っておきたい注意点をご紹介します。
目次 [閉じる]
1.合同会社とは
合同会社とは、平成18年施行の会社法により新たに認められるようになった会社の種類です。
LLC(Limited Liability Company)と呼ばれることもあります。
資産管理会社を設立するときは、会社の種類として「合同会社」と「株式会社」のいずれかから選択します。
会社の種類にはこのほか「合名会社」と「合資会社」がありますが、倒産時の責任の範囲に限度がない無限責任であるため、設立されることはまれです。
1-1.合同会社と株式会社の違い
ここでは、合同会社の特徴を株式会社と対比しながらご紹介します。
合同会社と株式会社には以下のような違いがあります。
| 合同会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 所有と経営の関係 | 基本的に一致 | 分離することもある |
| 出資者の名称 | 社員 | 株主 |
| 議決権 | 社員1人につき1つの議決権 定款で自由に定めることもできる | 株式の保有割合に比例 |
| 利益の配当 | 出資の割合に比例 定款で自由に定めることもできる | 株式の保有割合に比例 |
| 設立時の登録免許税 | 資本金の1,000分の7 (最低6万円) | 資本金の1,000分の7 (最低15万円) |
| 設立時の定款の認証 | 不要 | 必要(手数料5万円) |
| 社員・取締役の任期 | なし | 2年(最長10年) |
| 決算の公告 | 不要 | 必要 |
(注)株式会社の議決権や配当については、権利の内容が異なる種類株式(優先株式など)を発行する場合は例外があります。
1-1-1.所有と経営の関係
合同会社は、株式会社と同様に有限責任であり、倒産時の責任が出資の範囲内にとどまります。
一方、株式会社とは異なり、所有(出資)と経営が一致するという特徴があります。
株式会社では、出資者である「株主」が必ずしも会社の経営に関与するわけではなく、所有と経営は分離しています。たとえば、上場会社の株式を買って株主になったとしても、その会社の経営者になるわけではありません。ただし、規模の小さな会社では経営者が自ら株主となることが多く、その場合は所有と経営が一致します。
一方、合同会社では、原則として出資者は「社員」として経営に直接関与します。
ここでいう社員とは、一般的にいう従業員のことではなく、株式会社でいう取締役、つまり経営者のことをさします。
1-1-2.議決権・利益の配当
合同会社は、議決権や利益の配当についても株式会社と異なる点があります。
株式会社では、議決権や利益の配当は株式の保有割合に比例します。
所有する株数が多いほど議決権は多く、配当も多くもらうことができます。
一方、合同会社では、社員1人につき1つの議決権を持つことが原則です。
ただし、定款で異なる定めをすることもできます。
利益の配当も原則では出資の割合に基づきますが、定款で異なる定めをすることもできます。
1-1-3.設立・運営のコスト
合同会社は、株式会社に比べて安い費用で設立でき、設立後の運営コストを抑えることもできます。
会社の設立登記に必要な登録免許税は、株式会社、合同会社ともに資本金の1,000分の7ですが、最低金額に違いがあります。株式会社は最低15万円であるのに対し、合同会社は最低6万円で済みます。株式会社の設立には公証人による定款の認証が必要で、5万円の手数料がかかりますが、合同会社の設立に定款の認証は不要です。
また、株式会社の取締役には任期があり、選任のつど登記が必要ですが、合同会社の社員に任期はありません。株式会社に義務づけられている決算の公告も、合同会社には義務づけられていません。
1-1-4.その他
合同会社は設立が認められて十数年と歴史が浅く、会社数も少ないため、知名度が低いことは否めません。また、社会的な信用という点では、株式会社のほうが優れているのが現状です。
ただし、個人の資産管理を目的とするのであれば、知名度や社会的信用については過度に意識しなくてもよいでしょう。
1-2.税制上のメリットは同じ
合同会社と株式会社にはさまざまな違いがありますが、以下のような税制上のメリットに大きな違いはありません。
- 相続税の財産評価で有利になる
- 所得を分散させることができる
- 広い範囲で経費が認められる
相続税対策として資産管理会社を設立するのであれば、合同会社でも十分でしょう。
資産管理会社を使う相続対策については下記の記事で詳しく解説しているので、あわせて参照してください。
(参考)資産管理会社を使う相続対策のメリット・デメリットを税理士が解説
2.合同会社を設立するときの注意点
資産管理会社として合同会社を設立する場合には、社員(出資者)が死亡した場合の対応を決めておくほか、社員の意見が1:1で割れないようにするといった対策が必要です。これらの対策がなければ、会社の運営ができなくなり、資産管理会社を設立した目的が果たせなくなることもあります。
2-1.社員が死亡した場合の対応を決めておく
合同会社の社員が死亡した場合は、原則として出資金額が払い戻されます。
一人しかいない社員が死亡した場合は、合同会社は解散します。
出資持分を承継させたい場合、あるいは合同会社を存続させたい場合は、社員が死亡したときに相続人が出資を承継できるようにしておく必要があります。
具体的には、以下のような内容を定款で定めておきます。
第〇〇条
社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人が、当該社員の持分を承継して社員となることができる。
相続人のうち誰が出資持分を承継するかについては、定款で定めるのではなく、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で決定します。もし、特定の相続人に承継させたい場合は、遺言にその旨記載します。
なお、社員の死亡によって出資持分を相続した相続人は、合同会社の社員として経営に携わることになります。
2-2.社員の意見が1:1で割れないようにする
家族どうしで出資するなど合同会社の社員が複数いる場合には、社員の意見が1:1で割れないように配慮する必要があります。
合同会社の意思決定では、原則として社員1人につき1つの議決権を持ちます。
社員の数が偶数になっていると、賛成と反対が同数になって意思決定ができなくなることがあります。
そのため、複数人で合同会社を設立する場合は、次のような対策が必要です。
- 社員の数を奇数にする
- 定款で業務執行社員を定める(業務執行社員の数は奇数にする)
- 定款で社員ごとの議決権の割合を変える
合同会社は所有と経営が一致していて、出資割合よりも社員どうしの関係が重視されます。
社員の関係が良好であれば問題はありませんが、一度悪化すると業務が立ち行かなくなる恐れがあります。
3.合同会社の出資持分の評価方法
合同会社の社員(出資者)が死亡した場合は、相続人が出資持分の払い戻しを受けるか出資持分を承継します。払い戻された出資持分や承継した出資持分は、いずれも相続税の課税対象になります。
この章では、相続税を申告するときの合同会社の出資持分の評価方法をご紹介します。
(参考)国税庁ホームページ 質疑応答事例 持分会社の退社時の出資の評価
3-1.出資持分が払い戻される場合
合同会社の社員が死亡した場合は、原則として相続人が出資持分の払い戻しを受けます。
相続税の計算上は、出資持分の払戻請求権として評価します。
具体的には、合同会社のすべての資産の相続税評価額からすべての負債を引いた金額に持分の割合をかけた金額となります。資産と負債の金額は社員の死亡日時点のもので計算します。
なお、合同会社から払い戻される金額には、出資の元本にあたる払戻請求権に加えて、出資から払戻までの間に得た利益の蓄積部分もあります。この利益の蓄積部分は「みなし配当」として死亡した被相続人の所得になり、被相続人の準確定申告の対象になります。
また、この利益の蓄積部分は源泉徴収税額が差し引かれて払い戻されるため、相続税申告では源泉徴収税額を引いた金額で評価します。
3-2.出資持分を承継する場合
定款に出資持分の相続についての定めがあり出資持分を承継する場合は、出資持分の価額は取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。
取引相場のない株式の評価方法についての解説は、下記の記事を参照してください。
(参考)非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価のすべて
4.合同会社を使った相続税対策のご相談は専門の税理士へ
合同会社は、株式会社に比べて設立や運営のコストが低いという特徴があり、資産管理会社に適しています。ただし、相続税対策で合同会社を設立する場合は、社員が死亡した場合の対応を定款で定めておく必要があります。
合同会社を使った相続税対策は、専門家のアドバイスを受けて実行することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、相続税申告を専門に扱う税理士法人です。
相続税に関する豊富な知識を生かして、生前の相続税対策のご相談も承ります。
不動産オーナーの方には、グループ内の不動産会社と連携して、相続税の節税とあわせて収益性向上のコンサルティングを行うことも可能です。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。